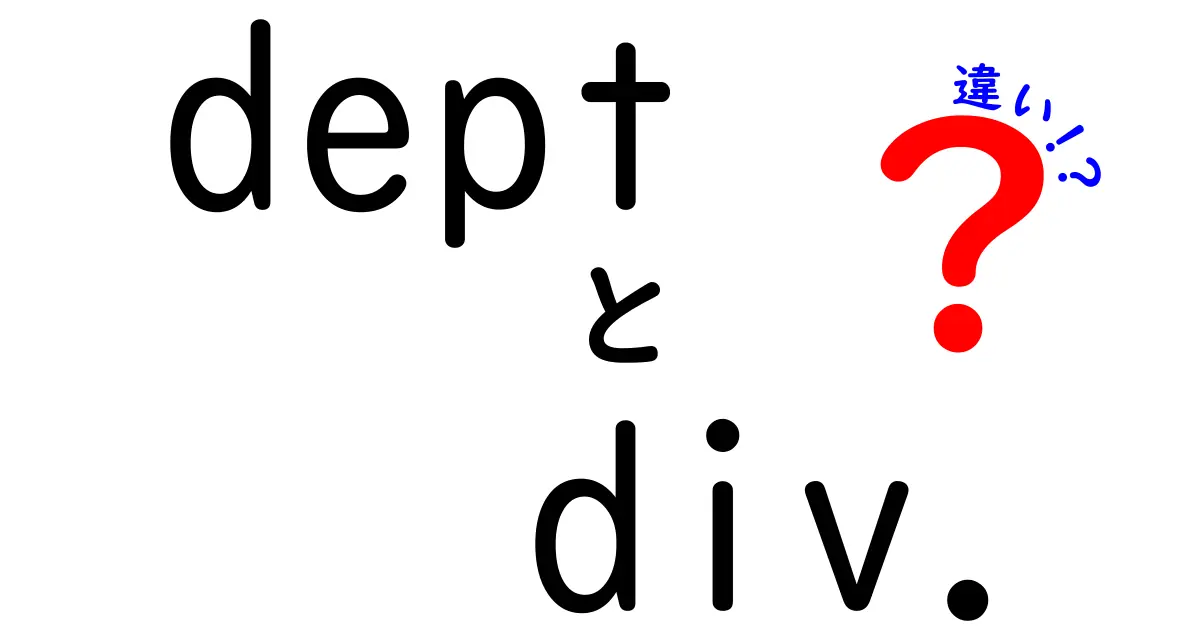

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
deptとdiv.の違いを徹底解説
deptとは英語の department の略で、日本語では部門と訳されます。企業の組織図を見てみると、総務部や人事部といった名前がありますが、これらは通常 dept の一部門です。
これらは「何をするか」という機能に焦点をあて、日々の業務プロセスを整える役割を担います。
一方 div. は division の略で、より大きな単位を指します。事業部や地域別の部門など、複数の dept を束ねて一つの大きな成果を出す責任を担います。
ここが決定的な違いです。総合的な戦略や収益性の責任を持つことが多く、製品群や市場ごとに独立して動くケースが多いのです。 なお、会社ごとに用語の使い方が異なるため、実務では自社の定義を文書化しておくと混乱を防げます。
たとえば新卒採用の説明資料では dept の職務範囲と div の責任範囲を別々に示すと理解が深まります。
dept とは?
dept とは正式には department の略で、日本語では部門と訳されます。部門は企業の機能を分担する最小の単位として、業務のやり方を定義し、日常の作業を回す仕組みを整えます。たとえば人事部は採用や教育、評価制度の運用、給与計算の確認といった人事機能を担います。総務部は社内の設備管理、庶務、文書管理などの事務的な機能を担います。部門は、主に「何をするか」という機能面の分類であり、収益を直接追求する責任を持つことは必ずしも多くないのが特徴です。従業員の数は div に比べ小規模になる場合が多く、組織図の中でも縦の連結が多い傾向にあります。企業によっては dept が複数の sub 部門を抱え、それぞれが特定の業務プロセスを最適化することで全体の効率を上げます。
したがって dept は機能の最適化と運用の安定化に強みを持つ単位であり、毎日行われる業務の標準化が重要な任務になります。
div. とは?
div. とは division の略で、企業の中の大きな単位を指します。事業部として知られることが多く、製品ラインごと、地域ごと、顧客セグメントごとなど、複数の dept を束ねて一つの大きな事業領域として機能します。
div には財務上の責任、戦略的な意思決定の権限、売上・利益の成果を直接追求する役割が含まれることが多いです。つまり div は「儲けを出す」という視点が強く、自立性・責任範囲の広さが特徴です。組織図では、div が上位のグループとして複数の dept を束ね、場合によっては複数の市場を横断して統括します。
ただし div の構造は企業ごとに異なり、製品別、地域別、顧客別などの切り方が採られます。
実務では div の枠組みが明確であれば、戦略の優先順位を説明しやすく、部門間の協力もスムーズになります。
実務での使い分けと表現のコツ
ここでは実務で dept と div をどう使い分けるかのコツを詳しく説明します。組織図を作成する際には、 dept は機能ベース、div は事業ベースと覚えると混乱を減らせます。説明資料や人材募集、採用時の表現では、次のような表現が有効です。
例1: 私の所属は人事部ですが、所属先の divX では新卒向けの採用戦略を担当しています。
例2: 当社の製品別 division では、複数の dept が協力して市場への供給を担っています。
また、内部文書では 部門間の責任範囲と権限を明記することがトラブルを防ぐコツです。
さらに伝え方としては、数字や指標を添えると理解が深まります。たとえばdiv. の売上目標、dept のKPIなどを併記すると、読者は全体の関係性をつかみやすくなります。
このように dept と div の違いを意識して使い分けると、組織の動きが読みやすく、説明の際にも自信を持って話せます。
div.という言葉を友達と雑談していると、なんとなく専門用語っぽい響きだけど実は身近な話題なんだよね。div.は事業部を意味することが多く、会社の中で“この事業は自分たちの責任で回していくんだ”という自立感を生む単位です。僕が入社したとき、先輩はdiv.の会議に参加しており、売上の話だけでなく市場の変化や競合の動きも同時に議論していました。 deptと違い、div.は“収益を生むチーム”という意識が強く、部員それぞれが戦略を考えて動く場面が多いです。だから、部門ごとの連携をうまく取るために、数字を共有することや責任の範囲をはっきりさせることがとても大事なんだと感じました。もし友達が div. について混乱しているなら、まずは“これは大きな箱、ここに入る部門はどんな成果を出すのか”とイメージするのがいいと思います。





















