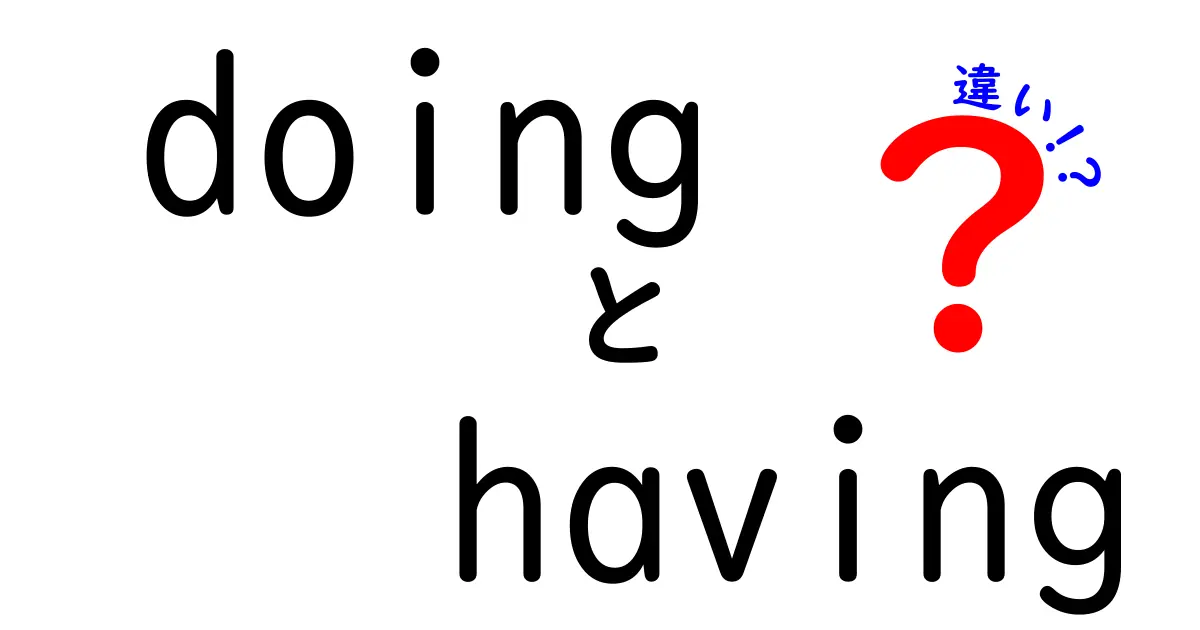

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
doingとhavingの違いを理解する基本のキ
英語には動作の時間軸を表すさまざまな形があり、その中でも doing(動名詞/現在分詞としての用法)と having(haveの現在分詞/過去分詞としての用法)の違いを理解することは、英語の理解を大きく深めます。
この2つはときに同じ文中で“動作の進行”や“完了の順序”を示すために使われますが、表す意味と使い方がまったく異なります。
まずは基本のイメージをつかみましょう。
・doing は「今起きている動作・行為そのもの」を表します。
・having は「すでに完了している動作・経験・状態」を前置きとして示します。
この違いを知ると、文章のニュアンスがぐんと豊かになります。
なお 名詞的用法としての doing や having の使い方は、場面によってはやや硬い表現になることがあり、日常会話ではもう少し分かりやすい表現へ置き換えることも多い点に注意しましょう。
実際の使い分けを理解するためのポイントは次の3つです。
1) 動作の「時間軸」が前提か後ろかで選ぶ。
2) 文章の主体は「行為そのもの」か「行為の結果・経験」か。
3) 固定表現かどうかを確認する。
例文を見ながらニュアンスを掴みましょう。
・I am doing my homework now.(今、私は宿題をしています)
・Having finished my homework, I watched TV.(宿題を終えたので、テレビを見ました)
・Having said that, I still think this idea is worth trying.(それを言った上で、私はこの案を試す価値があると思います)
この3つの例だけでも、doing と having の使い分けのヒントになります。
さまざまな場面での使い分けを押さえると、英語の読み書きだけでなく、リスニングやスピーキングの幅も広がります。
中学生のみなさんには、まずは身近な場面の文章で練習を重ね、時間の順序と状態の違いを意識する癖をつけると良いでしょう。
このセクションの要点をまとめると、doing は「いま進行中の行為そのもの」、having は「すでに完了している行為や経験を前提にする表現」という点です。
この考え方を頭に入れて、文章を読んだり書いたりすると、自然な英語表現にぐっと近づきます。
doingとhavingの実践的な使い分けのコツと注意点
実際の英語表現では、doing と having の使い分けを決定づける要因がいくつかあります。以下のコツを押さえておくと、会話でも作文でもミスが減ります。
第一のコツは 文の中心となる動作の時間軸を確認することです。現在進行中の動作なら doing を選ぶのが基本です。過去に完了した動作を前提にする場合は having を使います。
例を見てみましょう。
・I am doing homework.(私は宿題をしています)
・Having finished the homework, I went out.(宿題を終えた後、外出しました)
第二のコツは 固定表現や文型のパターンを覚えることです。たとえば Having said that は「それを言ったうえで」という意味の固定表現で、前の発言を受けて別の意見をつなぐときに使います。
・Having said that, there is another point to consider.(それを言った上で、もう一点考慮すべき点があります)
- 時間の順序が大切な文:Having + 過去分詞の形を使って、先に起きた出来事を説明する。
- 動作の進行を強調する文:現在分詞としての doing を使い、動作の過程を描く。
- 意味の切り替えを円滑にする:Having said that のような接続句を活用して、意見の変化を示す。
次に、中学生が使い分けを練習するための簡単な練習方法を紹介します。
1) 身近な出来事を時系列で並べる練習をします。例えば、朝ご飯を食べてから学校へ行く、という順序を英語で作ってみる。
2) 固定表現をノートに貼り付け、意味と使い方を自分の言葉で説明してみる。
3) 会話の場面を想定して、doing と having のどちらを使うべきかを自問自答する。
最後に、難しく感じる人へのメッセージです。最初は混乱して当然です。焦らず練習を積むこと、そして例文を声に出して読むことで、音と意味の結びつきを確実にしていきましょう。
英語は暗記だけでなく、感覚的な理解が大切です。文の意味を捉える力を養えば、doing と having の違いは自然と身につきます。
doing の深掘りトーク
\n友達と雑談しているような感覚で、doingのニュアンスを深掘りしてみましょう。
私たちが日常会話でよく使う doing は、進行中の動作を話すときの強力な道具です。例えば「今、宿題をしている」や「スポーツをしているところだ」といった表現は、現在進行形の感覚をじかに伝えます。
この「今この瞬間に起きていること」という焦点は、子どもから大人まで、言語感覚を鍛えるのに最適です。私が英語の授業でよく使うコツは、友だち同士の会話の中で doing の文を多く作ること。最初は文が長くなってもOK。
次第に、doing が「行為そのもの」を指すのか「その場の状況を説明する補足情報」を示すのかを自然と判断できるようになります。
結局のところ、doing は“現在の動作の実在感”を作る力を持つ言い方であり、練習を重ねるほど、話すリズムが滑らかになります。





















