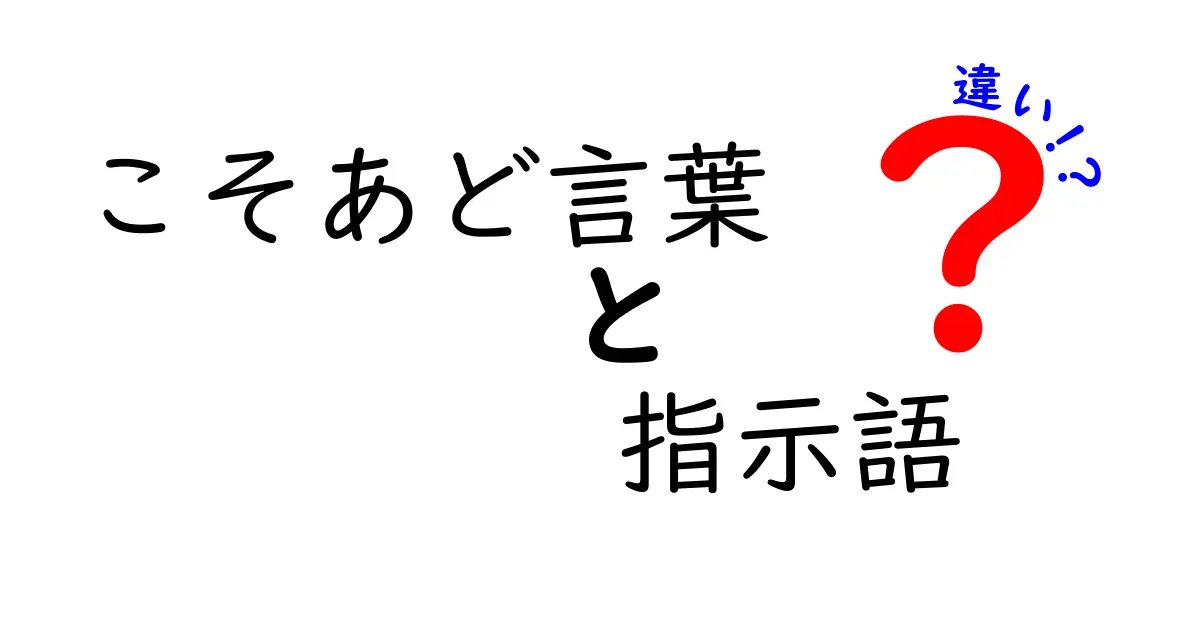

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに
このページではこそあど言葉と指示語の違いを、日常の会話で役立つように丁寧に解説します。こそあど言葉は話者の近さや位置を示す言葉の総称であり、ここ そこ あそこ どこ などが代表例です。指示語は名詞の前についたり後ろの名詞を指す言葉であり この この その あの などが含まれます。言い換えるとこそあど言葉は場所や関係を指すのに使われ、指示語は対象を特定する役割を果たします。話す場面や文章の中でどの言葉を選ぶかで意味が変わるため、少しの差が大きな伝わり方の違いを生み出します。本記事では中学生にも分かりやすい実例を交えながら、どの言葉を使うべきかの判断基準とコツを紹介します。
読み進めると自然と使い分けの感覚が身につき、学習や作文のときに困らなくなります。
こそあど言葉とは何か
こそあど言葉とは、話す人の立場や話題の対象との距離感を示す言葉の集合です。こは自分に近いことを、そは相手に近いことを、あは距離が遠い対象を示します。どはとりわけ場所や物事の位置を不確定に指すときに使われ、ここ そこ あそこ どこ などの派生語へとつながります。代表的な例としてここ そこ あそこ この その あの このように言葉が並ぶとき、話者と聞き手の関係性をすばやく伝える役割を担います。つまり、こそあど言葉は「どのくらい近いか」「どこにあるか」といった空間的情報の提示に強みがあり、文脈によって意味が微妙に変化します。
またこそあど言葉は単独で使われることもあれば、名詞と結びついて特定の物を指すこともあります。作文や説明文、会話の中で正確さを出すためには、距離感の判断が重要です。
指示語と代名詞の違い
指示語は対象を指し示すための語の総称であり、近いものを指すこの この、遠いものを指すあの、それらを指すつまりその など、文中の名詞と結びつく役割を果たします。代名詞は名詞の代わりに使われる語であり、私たちは文を短くするために代名詞を用います。例えば「猫がいます。猫はかわいいです」という文を「猫がいます。かわいいです」とするのは代名詞の活用ですが、指示語は「この猫はかわいいです」「あの猫は逃げました」のように、猫を特定する手がかりを示す役割を持ちます。つまり指示語は「この人」「その本」「あの場所」のように、名詞の位置関係を強く示す語であり、代名詞は名詞そのものを省略する役割が強いのです。
混同しがちなポイントは、同じ語が文脈次第で指示語にも代名詞にもなる点です。たとえば「この本」は指示語として使われつつ、同時に名詞の代わりとしての性質も持つ場合があります。学習時には、まず道具としての指示語か、名詞の代替としての代名詞かを区別して考えると混乱が減ります。
日常の例で学ぶ使い分け
日常の会話でこそあど言葉と指示語を使い分けると、伝えたい情報がクリアになります。例をいくつか挙げてみましょう。ここは今いる場所を指し、ここにある本は私のです。この本はこの教科書の中でも特に大事な章を表します。その章を読み終えたら、あそこにある黒板の前で発表します。このように距離感を意識して言葉を選ぶと、誰が何を指しているのかがはっきりします。
作文を書くときには、場所の距離感を揃えると読みやすくなります。例えば「ここにあるリンゴを食べる」「そこにある問題を解く」「あちらの学校へ行く」というように、話者の位置と対象の距離をそろえると、読者にもイメージが伝わりやすいです。さらに、複数の対象を指すときには「ここの本 そこのノート あの机」のように、位取りを明確にすることが大切です。
具体例と表で整理
こそあど言葉と指示語の関係性を整理するのに表はとても役立ちます。以下の表は、代表的な語とその意味の近さ、対象の指し方の違いをまとめたものです。表を見れば、同じように見える語でも距離感が異なることが分かります。
この表を覚えると、作文や日記を書くときにどの語を使えば伝えたい距離感がきちんと伝わるかを判断しやすくなります。
まとめとポイント
こそあど言葉と指示語の違いをつかむポイントは、まず距離感を意識することです。話している人と対象の距離を頭の中に描き、どの語が最も自然に近い距離を表すかを判断します。次に、文の中での機能を区別します。指示語は対象を“指し示す”ための語であり、代名詞は名詞の代わりとして使われます。最後に練習として、短い文章を自分で作ってみると良いでしょう。
こそあど言葉と指示語の使い分けが理解できれば、説明文や日記、作文の表現力がぐんと上がります。練習を重ねて、場面ごとに最適な語を選べる力を身につけましょう。
今日はこそあど言葉の深掘りをしてみよう。友だちと話しているとき、私が手に取っているノートを示すときはここ この それ あの などの言葉の使い分けが会話の流れを大きく変える。その場の距離感を感じ取り、どの語を選ぶかで受け手の想像する位置が変わるのを実感できるんだ。たとえば「ここにある本を読んでいる」と言うとき、あなたは本が自分のすぐ目の前にあることを想像する。一方「そこにある本を読んでいる」と言えば、聴き手がいる場所を基準に距離がずれる。こんな小さな差が、話のニュアンスや伝わり方を決める。だからこそ、語を選ぶ前に“誰に対して”情報を伝えるのかを考える癖をつけると、作文も会話もぐっと上手になるんだ。





















