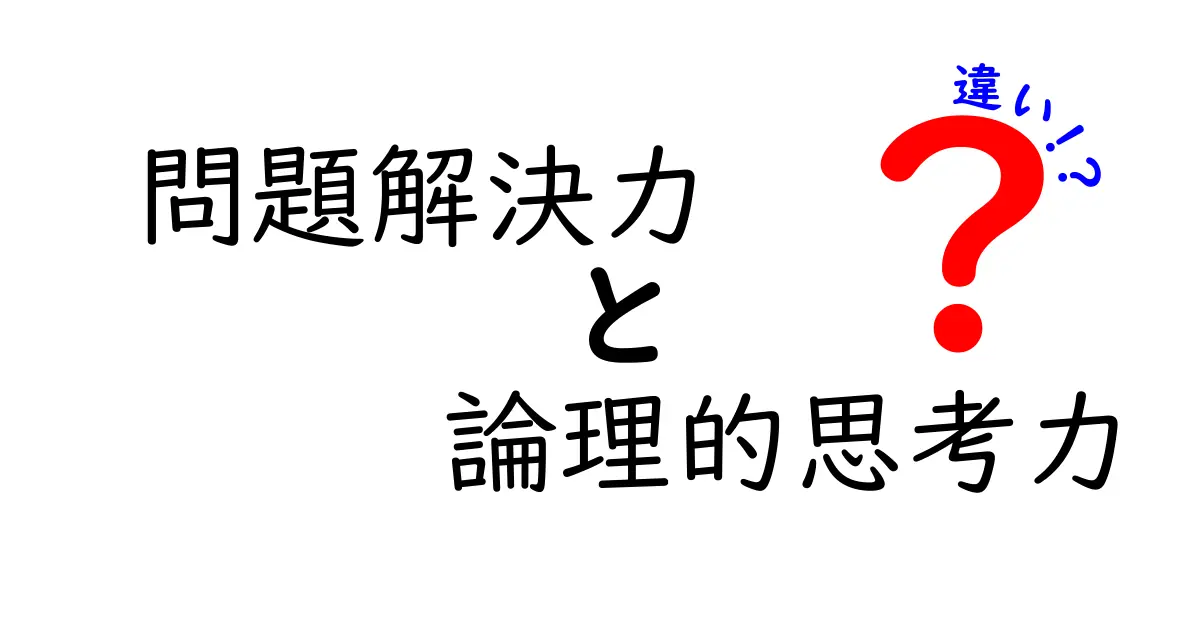

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
問題解決力とは何か
問題解決力とは、私たちが日常生活や学校の課題、さらには社会で直面する困りごとを、どうやって「解決に導くか」を考え、行動に移す力のことです。ここには 問題の認識、情報の収集、代替案の創出、実行と検証という複数の段階が含まれます。
まず第一歩は「何が問題なのか」を正しく捉えることです。目的をはっきりさせることが解決の出発点になります。次に、手元にある情報を集め、信頼できる根拠を見極める力が必要です。
この過程で考えるべきなのは「正解が一つだけとは限らない」という考え方です。複数の道を比較し、最も適した方法を選ぶ柔軟さが重要です。最後に、選んだ方案を実際に試し、結果を観察して、必要に応じて修正します。
この連続的な回路を回せる人が問題解決力が高い人といえるのです。
現場での例を想像してみましょう。学校のグループワークで「時間が足りない」という問題が出たとします。
まずは「何を達成するべきか」を明確にします。次に、作業の分担を見直し、効率的な進め方を考え、チーム全体で共有します。
進めるうちに新しい情報が出てくるかもしれません。そのときは計画を修正する勇気が必要です。これを繰り返すことで、最終的に良い成果を出す力が育ちます。
このようなプロセスは、学校の授業だけでなく、部活動、クラブ活動、さらには将来の仕事にも役立つのです。
問題解決力を鍛えるコツは、実際の場面を意識して練習することです。例えば、日々の課題を「どう解決するか」という視点で分解してみる、失敗しても原因を分析して次に活かす、という小さな訓練を積み重ねるだけで、だんだんと自分の力になっていきます。
また、チームで協力する力も大切です。こうした協力は、他人の意見を尊重しつつ自分の考えを伝えるコミュニケーション能力を高め、より良い解決策を見つける助けになります。
以下は、問題解決力を構成する要素を分かりやすく整理した表です。
この一連の流れを意識するだけでも、日常の問題に対する取り組み方が変わります。
重要なのは、答えを急がず、過程を大切にする姿勢です。
論理的思考力のしくみと違い
論理的思考力は、根拠に基づいて結論を導く力のことです。
この力は「前提」から「結論」へとつながる道筋を、論理的に組み立てることを重視します。
つまり、情報やデータ、証拠を並べて因果関係や矛盾点を検証する作業が中心になります。
一方で、問題解決力は「何を解くべきか」という目的設定から始まり、複数の選択肢を試すという現実的な行動プロセスを伴います。
この点で、論理的思考力は解決の道筋を整える道具であり、問題解決力はその道筋を現実の問題に適用して結果を作る力だといえます。
二つは互いに補完し合います。
具体的には、次のような関係があります。
・目的と根拠の整合:問題解決には「何を達成するか」が先にあるが、論理的思考力はその達成が正当な根拠に基づくかを検証します。
・仮説と実証:問題解決の過程で仮説を立てることが多いですが、論理的思考力はその仮説をデータや事実で裏付けます。
・柔軟性と厳密さ:問題解決力は現場の制約に合わせて柔軟に対応する力を要求しますが、論理的思考力は>厳密さと整合性を求めます。
この二つを日常生活で意識して使うと、困りごとに対する対応の質が高まるだけでなく、他の人と協力する際のコミュニケーションもスムーズになります。例えば、グループで企画を立てるとき、まず「何を達成したいか」を全員で共有します。次に、それを支える根拠やデータを整理し、各案の優劣を論理的に比較します。最後に、実際の行動に移して結果を検証します。この一連の過程を、論理的思考力と問題解決力を同時に意識して実践することで、成果は着実に上がります。
友だちのミコとユウの雑談から生まれる小さな発見。ミコは「問題解決力って、結局“どうやって解くか”を考える力だと思う」と言う。ユウは「でもそれを支えるのが論理的思考力だよね。根拠を並べて結論へつなぐ作業が大切」という。二人は、宿題の難問を前に、まず“何をゴールにするか”を話し合い、次に情報を集め、最後にいくつかの解決案を出して比較した。結果、最も現実的でコストの低い方法を選んだ。彼らは気づく。問題解決力と論理的思考力は別々の力だけど、現実の課題ではいつもペアで働く。この雑談から学ぶのは、まず目的を決めてから根拠を集める順序を守ること、そして試して修正する勇気を持つことだということだ。
次の記事: 着目と着眼の違いを一瞬で見抜く!日常で使い分ける超実践ガイド »





















