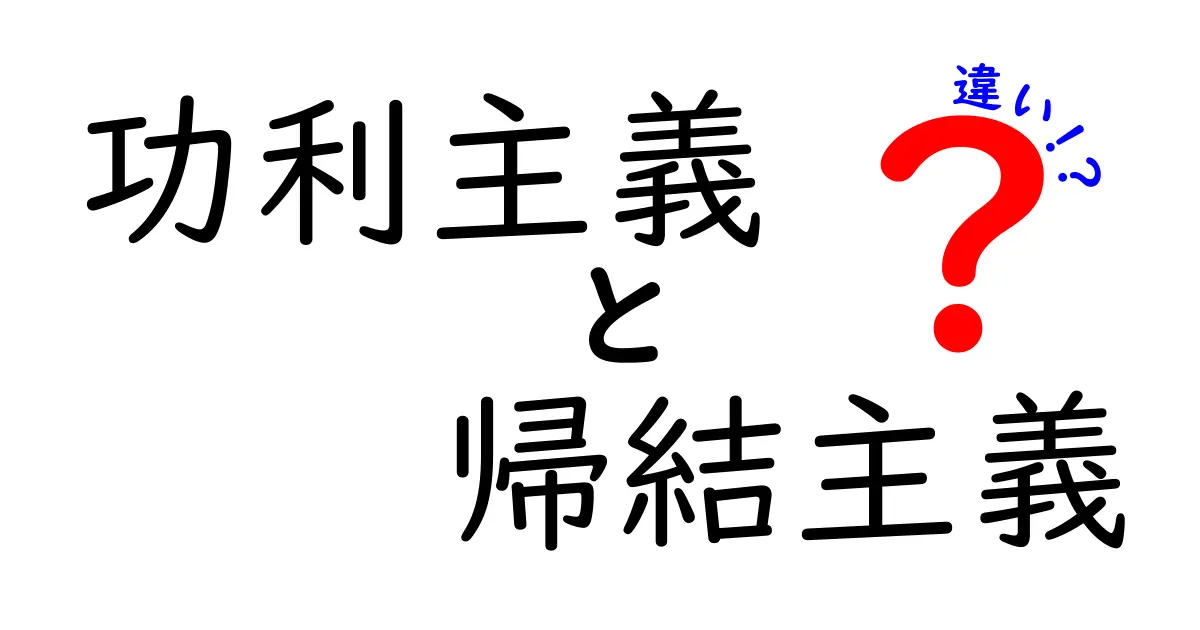

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:功利主義と帰結主義の基本を押さえる
人の道徳の話をするとき、よく出てくるのが 帰結主義 と 功利主義 です。これらは似ているようで違いがあり、日常の判断にも影響を与えます。まずは定義と基本的な考え方を整理しましょう。
帰結主義とは、ある行為の良し悪しを決めるのはその行為の結果です。つまり、結果が良ければ正しい、悪ければ間違いだと判断します。
一方、功利主義は「できるだけ多くの人の幸福を増やすこと」を最も大事な目的とします。ここでは幸福の量を最大化することが焦点です。
この二つは似ているようで、判断の軸が少し違います。たとえば、誰かを助けるとき、結果だけを見たら全体の善を優先しがちですが、具体的に「誰にとっての幸福か」を考えると、行動の選択が変わることがあります。
中学生の皆さんがニュースや議論を見るときにも役立つのは、結論を急いで決めず、理由と影響を整理する習慣です。
このあと、実際の場面でどう判断すべきか、簡単な言い換えとポイントを紹介します。
違いを理解するための要点整理
日常生活の中での判断を例に、帰結主義と功利主義の違いを観察してみましょう。例えば学校の合唱コンクールの練習で、全員の声がそろわない場合、発表を見送るべきか、全体の成功を優先して無理に進めるべきか、という問題が生じます。帰結主義は「結果がどうなるか」を第一に考え、発表してしまえば失敗の原因を誰かに特定できなくても、最終的な効果を重視します。一方、功利主義は「最大多数の幸福」を生み出す選択を探します。大勢が満足する状況を作るには、個人の意見や不満をどう扱うかが鍵になります。ここで重要なのは、幸福とは何かをどう測るかという基準の設定です。測定の難しさはあるものの、遊びや学習、友人関係の中で「誰が得をするのか」「誰が不利益を被るのか」を意識することで、判断力が少しずつ磨かれます。さらに、Act utilitarianismとRule utilitarianism という二つの考え方の違いにも触れると、実践場面のヒントが増えます。前者は個々の行為の結果を最優先に評価し、後者はそのルールを守ることで長期的に良い結果を生むかどうかを重視します。これらを混同せず、ケースごとに判断する訓練を積むことが重要です。
表で見る概要と誤解の解消
以下の表は、基本的な違いを視覚的に整理するためのものです。読み飛ばさず、表の横にある説明も読んでください。なお、ここでの「帰結主義」は行為そのものの結果を評価する考え方を指し、「功利主義」はその結果の中でも特に「最大幸福原理」を重視する具体的な型の一つです。
誤解として多いのは、これらを「何が正しいか」を一義的に決める絶対的な基準とみなす点です。実は、多くの哲学者は状況に応じて結論が変わる「容赦ない現実」を認めつつ、どう判断するかの指針を提供しています。
最後に、この表を通じて違いの要点を再確認します。結局、すべての判断は「結果がよいかどうか」と「人の幸福をどう広げるか」という二つの視点の組み合わせで動くことが多いです。日常生活での小さな選択も、この二つの視点を意識するだけで見方が変わることを覚えておくとよいでしょう。
まとめと日常への活かし方
この説明をふまえて、日々の決断をするときのヒントをいくつか挙げます。まず第一に、結果だけで判断しすぎないこと。結果がよくても、過剰な押し付けや不正が生まれると長い目で見てマイナスになります。次に、影響を受ける人の数だけでなく質も大事だと意識すること。友だち同士の約束や授業の発表、人を傷つけずに協力できる方法を探す訓練は、学業だけでなく将来の社会生活にも役立ちます。最後に、日常の会話で使える「二問法」を紹介します。“この判断の結果は誰にとって良いのか”“それ以外の人にとっての不利益はないか”を自問する癖をつけると、納得感のある決定を導きやすくなります。大事なのは、対話を通じて判断基準を共有することです。
今日の小ネタです。功利主義という言葉を初めて聞いたとき、私はお祭りの景品と比べてみました。景品をもらえる人を多くするには、全員に景品を配るのが一番良いのか、それとも高価な景品を少数にだけ渡すのが良いのか。直感だと前者ですが、深く考えると「幸福の質」も大事だと気づきます。つまり、数だけ追い求めると、心の満足感が薄くなることがあります。私は友だちと話して、時には全員が少しずつ幸せになる方法を一緒に探すのがいいと感じました。これが功利主義という考え方の面白さで、数字だけでなく人の気持ちにも目を向けるべきだという気づきにつながります。
前の記事: « 裁量と裁量権の違いを徹底解説!中学生にも分かる3つのポイント





















