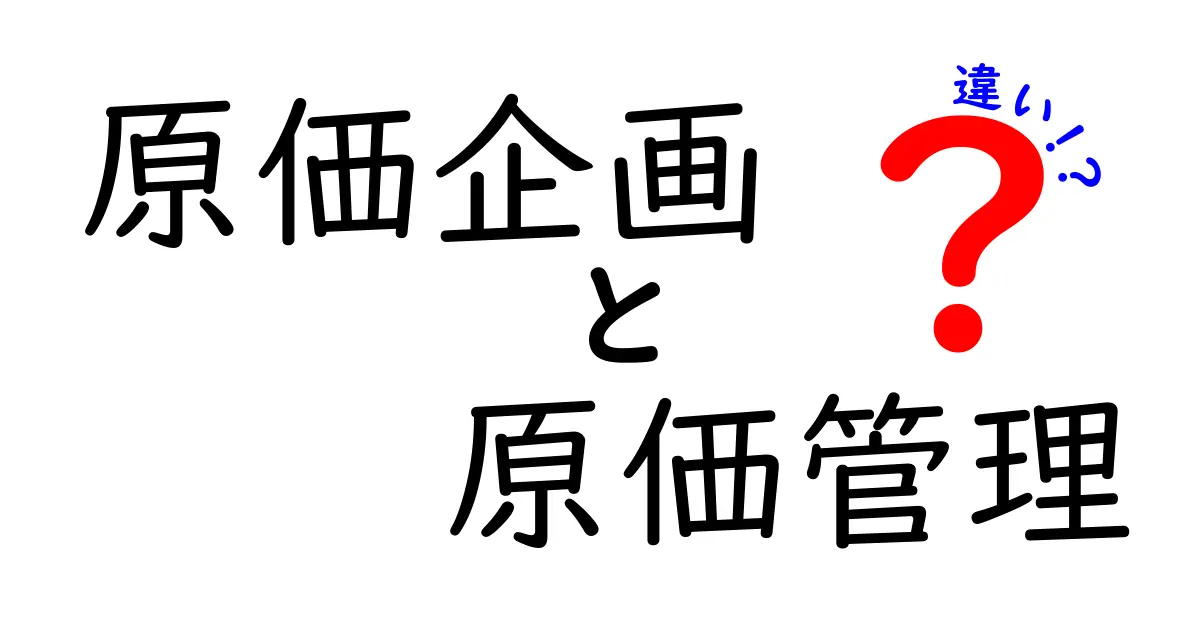

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
原価企画と原価管理の違いを理解する第一歩
原価企画は、製品やサービスが市場に出る前に「いくらかけて良いものを作るか」を決める設計の作業です。未来志向の設計力が求められ、試作・原材料の選択、製造方法の組み合わせ、数量割り、販売計画などを横断してコストの全体像を描き出します。これに対して原価管理は、実際に作ったもののコストを把握し、現状の数字を日々追いかけて問題を見つけ、改善を図る作業です。ここで大切なのは、原価企画が「どう作るかの設計書」を作ること、原価管理が「現場の数字を読んで検証・改善を行う」ことだという点です。
原価企画にはいくつかの基本的な枠組みがあります。まず「直接費」と「間接費」を分け、次に「変動費」と「固定費」を意識する癖をつけます。これらを組み合わせると、製品単位の原価がどのように動くかが見える化され、コストの主語を明確にすることができます。たとえば新製品開発では、原材料の価格変動や部品の代替案、生産ラインの稼働率、品質不良のコストまでを含めて仮説を立て、複数案を比較します。ここで原価企画は未来をデザインする力、そして原価管理は現状を検証する力、この二つが両輪となって初めて現実的なコスト戦略が動き出します。
原価企画と原価管理の実務での使い分けとその影響
日常の業務に落とし込むと、原価企画は新製品の設計会議や開発プロジェクトの初期段階で強く働きます。市場の競争状況、原材料の予想動向、製造の難易度、そして顧客の価格感度を総合的に評価し、いくつかの代替案を比較表としてまとめます。これにより、"コストの変動要因"を事前に捉え、最適な製品仕様や生産体制を決定します。
一方で原価管理は、月次・週次・日次の会計処理の中で、原価計算の正確さ、原材料の使用量の管理、廃棄や不良品のコストを追跡します。データの正確性と透明性が命であり、ムダを見つける指標(例えば「原価率」「原価差異」など)を設定します。ここで重要なのは、原価管理の改善提案は現場の実務と結びつくこと、つまり現場の作業手順を変えずにコストだけを削るのではなく、工程を見直すことで長期的な効果を生むことです。
具体的な使い分けとしては、原価企画が新製品開発や事業計画の初期段階で先制的にコストを設計するのに対し、原価管理は日々の生産・販売活動を支える現場での数字の安定化と継続的改善を担います。両者を連携させることで、未来志向の設計と現実的な運用改善が同じ言語で語られるようになり、コストの見える化が進み、意思決定の質が高まります。
放課後の教室で、友達Aが「原価企画って難しそうだよね」とつぶやくと、友達Bが笑って答えた。「難しいけど大事なのは未来を考えること。原価企画は『この製品をいくらで作るべきか』を設計する作業、つまり設計図を描くことだよ。一方、原価管理は現在の数字を追いかけて現状を改善する作業。例えば部品の在庫が過剰になっていないか、無駄な廃棄が出ていないかを毎月チェックする。二つが噛み合えば、未来の設計が現実の運用と結びつき、コストを効率よく抑えられる。結局、原価企画が“未来の設計士”、原価管理が“現場の検査官”みたいな役割分担になるんだ。
次の記事: 直接原価と直接費の違いを徹底解説:利益が見える費用の分け方 »





















