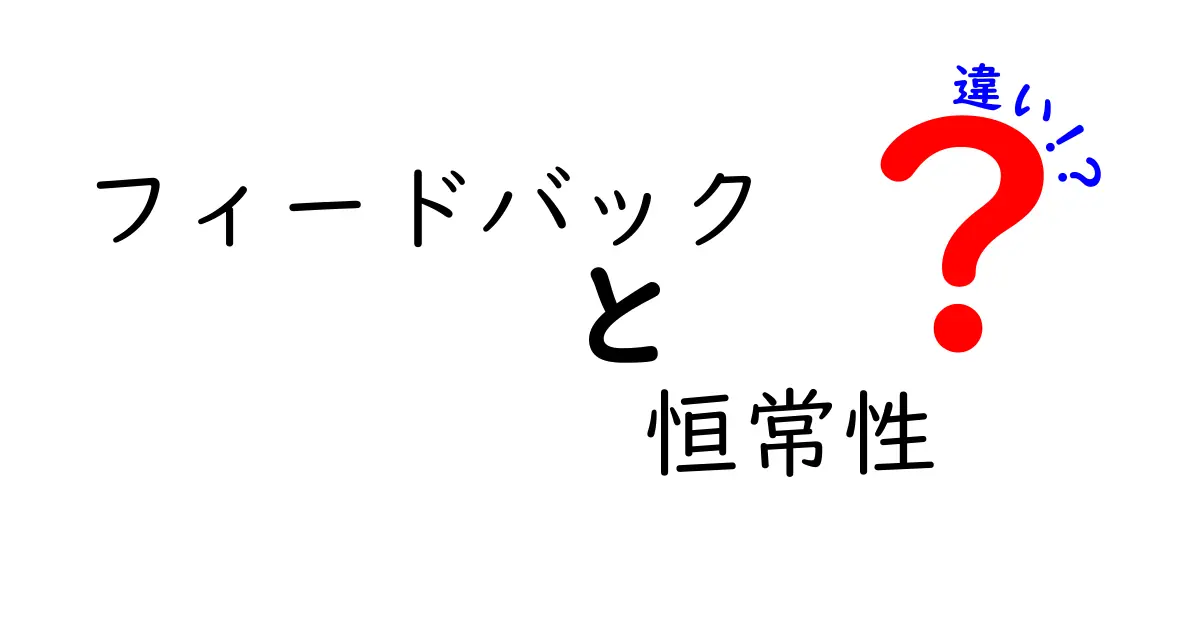

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
フィードバックと恒常性の違いを徹底解説
フィードバックとは何かをまず分解して理解しましょう。
たとえば部屋の温度を適温に保つとき、センサーが今の温度を読み取り、設定温度と比べて差を小さくするように動作を調整します。これを負のフィードバックと呼び、外部の変化を元に戻そうとする仕組みです。
一方で「恒常性」とは生物が体内の環境を一定に保つ大きな目標を指します。体温、血糖、酸性度などを一定の範囲に保つことを意味します。
機械の世界でもフィードバックは同じ考え方で使われ、温度計、エアコン(関連記事:アマゾンでエアコン(工事費込み)を買ってみたリアルな感想)、スマホのセンサーなどが活躍します。
しかし恒常性は生物の生存に直結する大切な機能であり、体が変化に耐えられるように多層構造の調整が働きます。
ここからのポイントは「何を調整するのか」「調整の目的は何か」「調整の速さはどれくらいか」です。
つまりフィードバックは情報のやり取りの仕組み全般を指す言葉であり、恒常性はその仕組みを使って体の内部を安定させる生物学的目的を指す、という違いになります。
また正のフィードバックと負のフィードバックという2つの形も覚えておくとよいです。
正のフィードバックは出力を増やして結果をより大きくする働きで、例として出産時の子宮収縮を強める仕組みが挙げられます。
負のフィードバックは出力を抑えて元の状態へ戻す働きで、体温調節のように変化を小さく抑える場面で見られます。
身近な例で理解を深める
身の回りの例で考えると理解が進みます。
例1 テレビの室温センサーが部屋が暑くなると冷房を強くするのはフィードバックの機能です。
例2 人が寒いと震えたり血管を収縮させて体温を守ろうとするのは恒常性の一部です。
例3 ダイエット中に血糖値が下がると、脳が空腹を感じるのは体の内部状態を安定させようとする恒常性の働きで、同時に食欲を調整するホルモンが働きます。
こうした現象には共通点と相違点があり、前者は機械や生物における情報の受け渡しの手段、後者は体内の状態を一定の範囲に保つ長期的な目標に近いということが分かります。
重要なのは「原因と結果の関係」をどう見るかです。
図や表を使うとさらに分かりやすくなります。以下の表は基本的な意味と例を並べたもの。
| 概念 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| フィードバック | 情報が戻ってくる仕組み | 室温センサーが冷房を調整する |
| 恒常性 | 内部環境を一定に保つ働き | 体温を安定させる |
この2つは似ているようで目的と使い方が異なります。日常の技術と生物のしくみを比べると、どうしてもの仕組みが違うかがよく見えてきます。今度は自分の生活の周りで見つけてみましょう。例えばスマホの通知設定と体温の安定、両方の観点から考える癖をつけると、科学の話が身近な話題として感じられるでしょう。
今日は放課後の雑談。フィードバックという言葉を深掘りしてみると、ただの指摘ではなく相手の行動を変える情報の流れだという感覚が大事です。友達に意見を伝えるとき、感情を傷つけずに伝える方法を選ぶのは、結果を良くするためのフィードバックの技術だからです。私たちは最近部活の練習で『こうすると動きがスムーズになるよ』というフィードバックを、相手の気持ちを傷つけず伝える練習をしています。フィードバックには正のフィードバックと負のフィードバックという2つの形があり、混同しやすい点を分けて考えると理解が早くなります。
正のフィードバックは成果を後押しする方向へ働くことが多く、成長のきっかけを加速させます。逆に負のフィードバックは現状を安定させる方向へ働くので、過剰な変化を防ぎ長期的な成長を支えます。
この二つを使い分けるコツは「何を改善したいのか」をはっきりさせ、具体的な行動へ結びつけることです。僕たちは友だち同士の話し方を工夫することで相互理解を深め、信頼関係を育てています。
次の記事: 体液と組織液の違いって何?血漿・間質・細胞外液をやさしく徹底解説 »





















