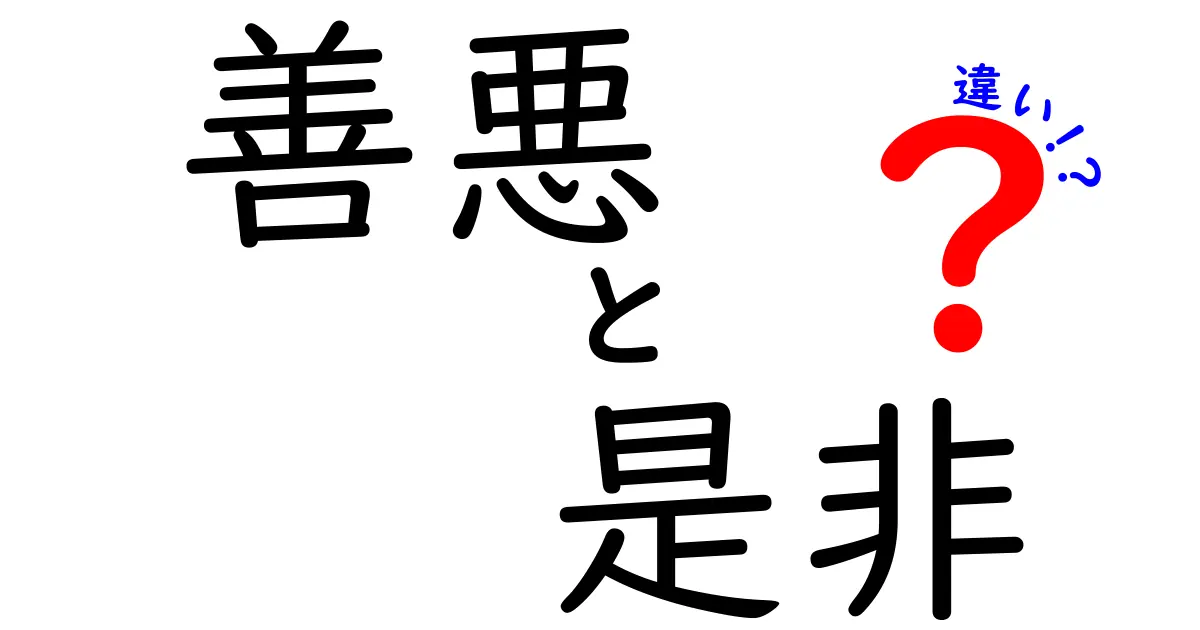

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
練習問題と日常の演習
善悪と是非の違いを身につけるには、練習が欠かせません。まずは自分の生活の中で起きている小さな出来事を観察してみましょう。例えば、授業中のスマホ利用、友人へ話す内容の選択、チームでの役割分担などです。練習のコツは三つです。第一に、状況を分解して「誰が」「何を」「どのような影響を受けるのか」を整理すること。第二に、是非の判断には「正しい理由と説明」が伴うかを問うこと。第三に、他者の視点を取り入れるために友人と意見交換をしてみることです。これを繰り返すと、善悪と是非の両方を結びつけて考える力が養われます。日常の出来事を記録して、後で振り返るノートを作ると、判断のクセが見つかり、次第に自信を持って意思決定ができるようになります。
ある日、僕と友達二人がカフェで話していた。僕は善悪と是非の違いについて話していて、友達の一人は『善悪は感情で動くことが多く、是非はルールや理由を探す作業だよね』とつぶやいた。その言葉を聞いて、僕はふと、日常の中で“正しいこと”と“正しい理由”を切り離して考える訓練を始めようと決意した。私たちは、友達が落とした財布を拾ったときの対応を例に取り、善悪的評価(届け出るべきか、落とし主が現れたらどう説明するか)と是非的判断(落とし物を自分の守秘義務とどう折り合いをつけるか、無断で持ち帰っていいのか)を別々に検討してみた。結果として、善悪は人間関係の中での倫理的評価、是非はその評価を裏づける理由と適用範囲を問う判断だという結論に至った。もし僕たちがこの区別を日頃から意識していなかったら、財布の扱い一つでも適切な説明ができず、後から大きな混乱を招いていたかもしれない。こうした“日常の小さな選択”を重ねることが、深い理解へとつながるのだと感じた。
前の記事: « 主体と自律の違いを徹底解説!中学生にもわかる実例付きガイド
次の記事: 倫理と道徳心の違いを徹底解説!中学生にも伝わる分かりやすさの秘密 »





















