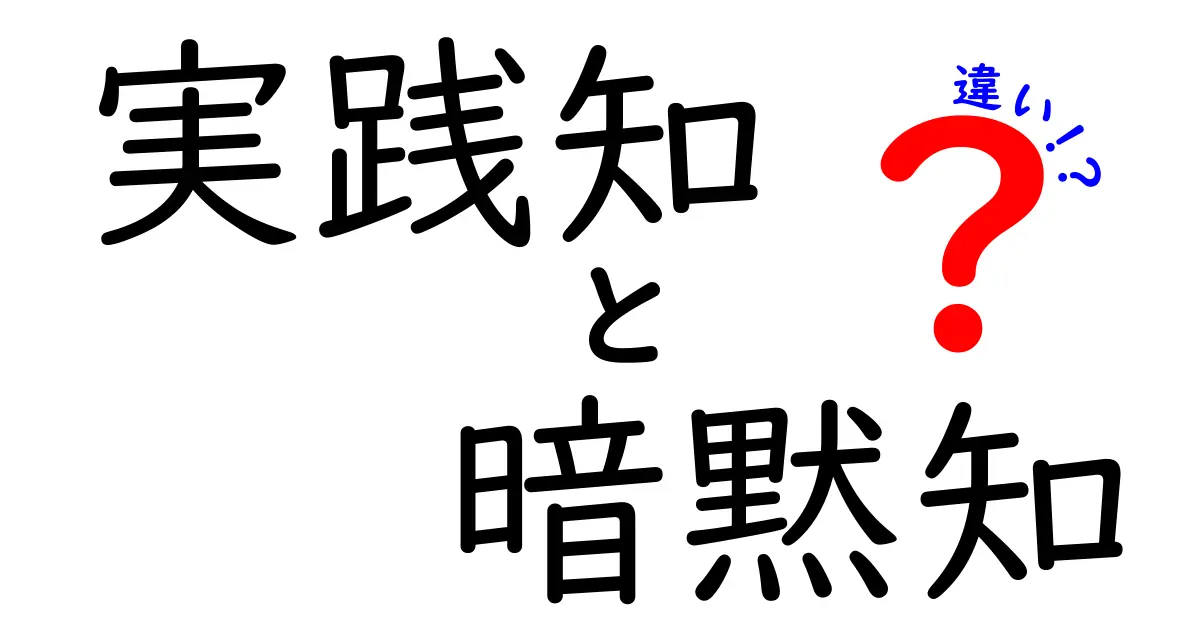

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
実践知と暗黙知の基本的な違い
まずは言葉の定義から整理しましょう。実践知とは、実際の作業や行動の中で役立つ知識のことを指します。これには手順、コツ、再現性の高い技術など、誰がやっても同じ結果を出せるように伝えることができる知識が含まれます。例えば、料理のレシピ、機械の操作手順、スポーツの基本型、プログラミングのアルゴリズムのように、文字や図で説明可能な要素が中心です。
一方で暗黙知は、言葉にして表現しきれない知識のことを指します。身体で覚えた感覚、場の空気を読む直感、経験を重ねて培われる判断力などが該当します。教科書には書かれていないが、現場で大きな役割を果たす知識です。例としては、熟練職人の手さばき、医師の微細な身体観察、スポーツ選手の感覚的判断などが挙げられます。
この二つは互いに独立しているわけではなく、相互に影響し合います。実践知は暗黙知を言語化して共有することで拡張され、暗黙知は長い経験を通じて徐々に実践知へと落とし込まれることがあります。組織や教育の現場では、この二つをどう橋渡しするかが成功の鍵になります。言語化の努力は現場の理解を深め、体感と感性を言語として伝える取り組みが重要です。
このように、現場での知識は「何をどうするか」を示す実践知と、「どういう感覚で判断するか」を支える暗黙知の組み合わせで成り立っています。教育の場では、まず実践知を言語化して教材化し、次に暗黙知を観察・指導・模倣を通じて伝えることで、学生や新人が現場の力を身につけやすくします。両方を意識した学びの設計が、実務の安定と創造性の両立につながります。
実践知と暗黙知の違いをめぐる3つのポイント
1つ目のポイントは、伝え方の差です。実践知は言語化・手順化が比較的得意で、マニュアルや動画・レシピとして共有しやすいです。2つ目のポイントは、難易度の差です。暗黙知は個人差が大きく、同じ作業でも人により難易度が変わることが多いです。3つ目のポイントは、習得の道筋です。実践知は反復練習とフィードバックで短期間に積み上げやすいのに対し、暗黙知は長い実務経験を通じて徐々に獲得されることが多いです。
この3つを理解すると、指導設計が変わります。新しく入った人には基礎となる実践知を丁寧に教え込み、熟練者には現場の感覚を言語化して共有する作業を促すと良いでしょう。実践知と暗黙知を分けて考え、適切に組み合わせることが、組織の学習力を高める第一歩です。
現場での使い分けと実例
学校の調理実習を例にすると、レシピは実践知の典型です。材料の分量、加熱時間、火力の調整など、誰が作っても同じ結果が出せるように整理します。いっぽうで、同じ料理でも気温の違いや鍋の焦げつき具合、盛り付けの美的感覚といった要素は暗黙知的な部分が強く、経験を重ねることでしか身につきません。こうした違いを理解しておくと、教える側も学ぶ側も「何を言葉にして伝え、何を手本で示すべきか」を判断しやすくなります。
組織全体で暗黙知を共有する方法としては、メンター制度・ペア作業・振り返りの場を設けることが効果的です。観察と模倣を繰り返すことで、暗黙知の要素が短期間で言語化され、新人の成長速度がぐんと上がることが多いです。実践知を教えるときは、失敗例の記録やチェックリストを活用して、再現性を保ちつつ、暗黙知を補完する解説を加えると良いでしょう。
実践知と暗黙知を深掘りたいとき、私は現場の写真や動画を使って“手の動き”や“判断の瞬間”を一緒に見ることを勧めます。言葉だけでは伝わらない微妙な手の角度や視線の移動、それが良い結果につながる瞬間を、友人と雑談するように話し合いながら言葉にしていくのがコツです。突然難しい理論を語るより、まず“どうやってうまくいくのか”を具体的な場面で共有すること。そうすることで、暗黙知の端っこが少しずつ形を持ち、集団全体の実践知へと昇華していくのです。





















