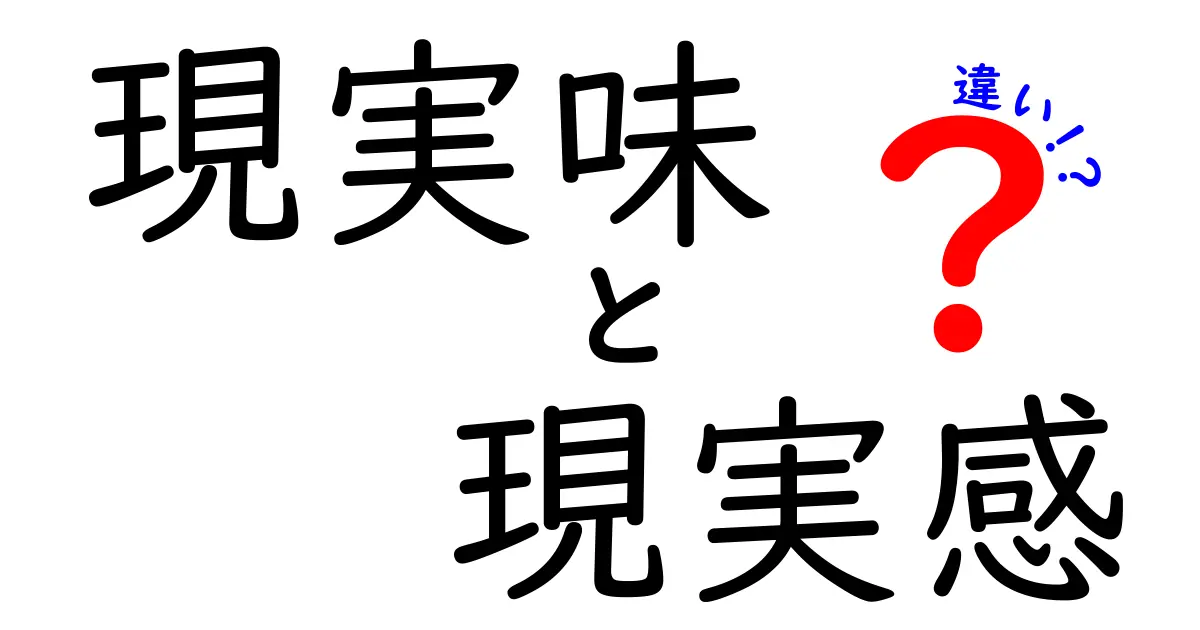

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
現実味と現実感の違いを理解するための基礎
「現実味」と「現実感」は、似ているようで使い分けが大切な言葉です。まずは二つの言葉の基本的なイメージを整理します。
現実味は、外部の世界がどれだけ“現実らしく見えるか”という客観的・説得的な度合いを表します。ニュースやドラマ、映画、小説などで使われ、読者や視聴者が「これは現実の出来事のようだ」と感じるかどうかを左右します。現実味を高めるには、データ・証拠・具体的な描写・整合性が重要です。
一方、現実感は、いま自分の身体や心がその場面を“現実として感じている”度合いを指す、主観的な感覚です。天気・温度・匂い・音・心拍のような感覚的な要素が強く影響します。現実感は人それぞれ感じ方が違うため、同じ場面でも受け取り方が異なります。
この二つは、外部の世界のリアリティと内側の体験のリアリティという、別々の軸で考えると理解しやすくなります。現実味が高くても現実感が薄い場合や、その逆の組み合わせもあり、場面ごとに使い分けることが肝心です。
現実味と現実感の関係をつかむコツは、次の二点です。
1) 文章の目的を意識する。事実性を伝えたいときは現実味を高める要素を増やし、読者の共感や感情体験を狙うときは現実感を重視します。
2) 証拠と体感のバランスをとる。データと描写の比率を調整し、過度な理想化を避ける工夫をしましょう。
次の章から、それぞれの意味をさらに詳しく見ていきます。
現実味とは何か
現実味とは、物事が現実のように「見える・感じられる」度合いを指す言葉です。現実味が高い文章や映像は、読者や視聴者が“現実の出来事として受け止められる”と感じさせます。現実味を高める要因には、時間の整合性、場所の具体性、人物の自然な行動、そしてデータの出典や根拠の提示などが挙げられます。現実味を上げすぎると、作者の解釈や創作の都合が露出するリスクもあるため、適切なバランスが重要です。
現実味は“何が起きているか”を明らかにする力であり、物語の信頼性や説得力を支える土台です。
読者・視聴者が「これなら信じられる」と思えるラインを見極めることが、現実味の設計には欠かせません。
現実感とは何か
現実感とは、いまこの場で自分が経験していることを、身体と心がどう感じているかという主観的なリアリティの度合いです。天候の冷たさ、部屋の匂い、音の響き、心の揺れといった感覚が重なるほど、現実感は強くなります。現実感は人によって異なるため、同じ場面を見ても共感の強さは変わります。現実感を高めるには、五感の描写を細かく、心の動きを丁寧に描くことが効果的です。感情の機微や身体反応を言語化すると、読者は自分の体験と結びつけやすくなります。
ただし現実感ばかりを追いすぎると、説明が重くなり、読み手が疲れてしまうこともあります。現実感と現実味のバランスを取りながら、体験の深さと証拠の正確さを両立させることが大切です。
日常の使い分け事例
日常の文章や会話で、現実味と現実感をどう使い分けるかの具体例を挙げます。
1) ニュース記事やレポート:現実味を最優先し、統計データ・出典・時系列を明確に示す。
2) 小説・ドラマの描写:現実味と現実感を混ぜ、現実的な出来事の描写と登場人物の感情体験を共存させる。
3) ブログやエッセイ:読者へ共感を呼ぶため、現実感を強調しつつ、必要に応じてデータを添える。
4) プレゼンテーション:説得力を高めるため現実味を使い、聴衆の感情に訴えるエピソードで現実感を補完する。
このように目的に応じて、現実味と現実感のバランスを調整することが、伝え方の幅を広げるコツです。
まとめと実践のコツ
現実味と現実感は、同じ場面を語るときでも異なる切り口を提供します。現実味は「外部の世界がどれだけ現実的に見えるか」という客観性に近い評価、現実感は「自分がその場をどう感じているか」という主観性に近い評価です。文章や話し方でこの二つを使い分けるには、最初に伝えたい目的をはっきりさせ、次に読者・視聴者があなたの言葉をどのように受け取りたいかを想像します。
具体的には、現実味を高めたいときはデータ・出典・現場描写を増やし、現実感を高めたいときは五感・感情・心の動きを丁寧に描く。
最後に、整合性と共感のバランスを意識することが大切です。現実味と現実感を適切に活用することで、読者は“信じられる現実”を感じ、あなたの伝えたいメッセージに強く引き寄せられるようになります。
友達と話しているとき、現実味と現実感の違いが会話のトーンを決めることがよくあります。例えば、ニュースの説明では現実味を高めるためのデータや時系列を重ねます。一方、友達との会話では現実感を重視して、匂い・温度・ざわめきといった身体感覚を共有すると、相手はその場面を自分ごととして感じやすくなります。現実味が現実の“証拠”なら、現実感はその場の“体験”です。二つを組み合わせると、作文もプレゼンもぐっと説得力と親しみが増すのです。





















