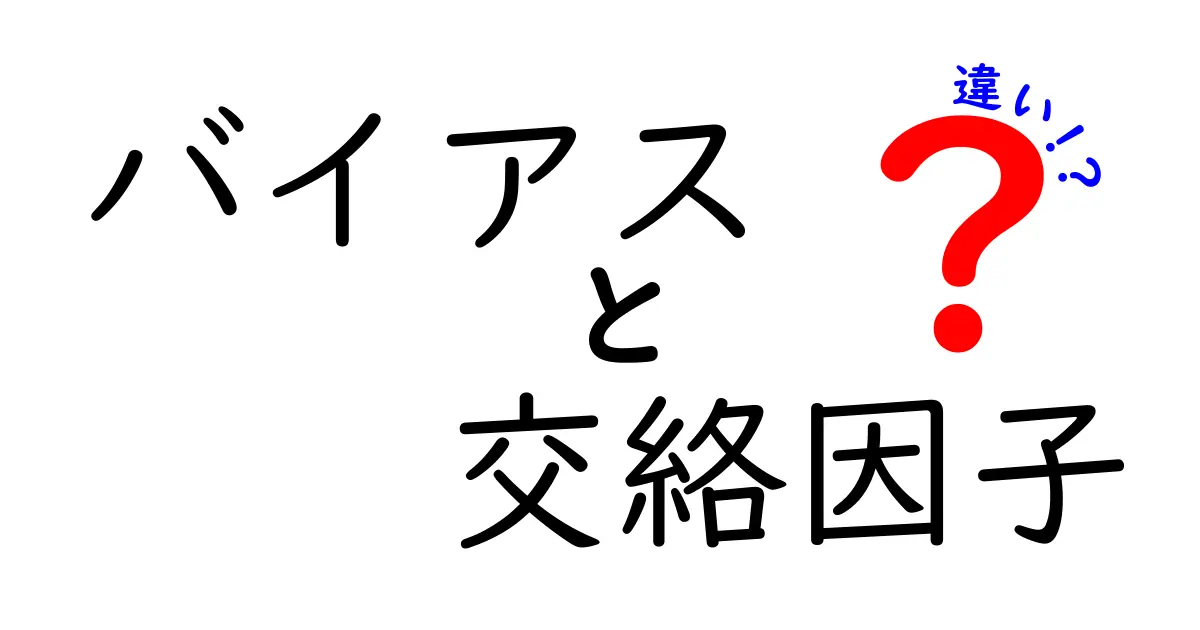

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
バイアスと交絡因子の違いを正しく理解するための基本概念
ここではまず両者の意味を整理します。バイアスとは研究の過程そのものに潜む歪みのことであり、データの収集方法や観察の仕方、測定の誤りなどが原因となって研究結果の「真の値」を近づけず遠ざけてしまいます。対して交絡因子とは観察している対象と結果の間に第三の変数が潜んでおり、その変数が曝露と結果の両方に影響を与えることで、曝露と結果の間にあると見える関係を実は別の要因が作っている状態を指します。
この違いをしっかり押さえることが、ニュースや論文を正しく読み解く第一歩です。例えばニュースで「ある食品を摂ると病気リスクが下がった」と報じられても、その結果が年齢や運動習慣などの要因によって説明できる場合、結論は安易には信用できません。ここでいうバイアスはデータの歪みや測定の誤りによって生じる偏りを指します。一方で交絡因子は研究設計次第で取り除くことが難しく、分析方法を工夫する必要がある場合が多いのです。
このような違いを日常生活の例で考えると理解が深まります。例えば、夏にアイスを食べる人は頭痛薬を多く飲む傾向があるとします。これはアイスのせいで頭痛薬を飲む人が増えたのではなく、暑さという外部要因が両方に影響している可能性が高いのです。これが交絡の典型的な例です。そしてこのような関係を分析で取り除くには、ランダム化、層別化、回帰分析などの手法が使われます。ここから、実際の研究で使われる語彙と考え方の地平が一気に広がります。
- 要点1 バイアスはデータの偏り、測定の誤りが原因で結果を歪める
- 要点2 交絡因子は第三の変数が原因となって関係を偽装する
- 要点3 対策には設計の工夫と分析の工夫の両方が必要
カフェで友達と雑談をしている雰囲気で。友達Aが『バイアスって難しそうだけど結局何が違うの?』と聞くと、友達Bは『バイアスはデータの取り方そのものの歪みだよ。たとえばアンケートで答えた人が元々質問に興味がある人だけだったら、結果は本当にみんなの意見を代表していないかもしれない』と説明します。続けて『交絡因子は別の要因が結果と exposure に同時に影響することで、観察された関係が実は別の理由で起きているように見える現象だ』と語り合います。彼らは暑い日にアイスを食べる人が多いからといってアイスが健康に良いとは結論づけられない理由を、ことわざ風に『夜更かしと風邪は因果の仲間割れ』と比喩して納得します。最後に、研究で正しく判断するには『設計を工夫する』ことと『分析で補正する』ことが大事だと結論づけ、日常の疑問を科学の視点で深掘りする雑談を締めくくります。





















