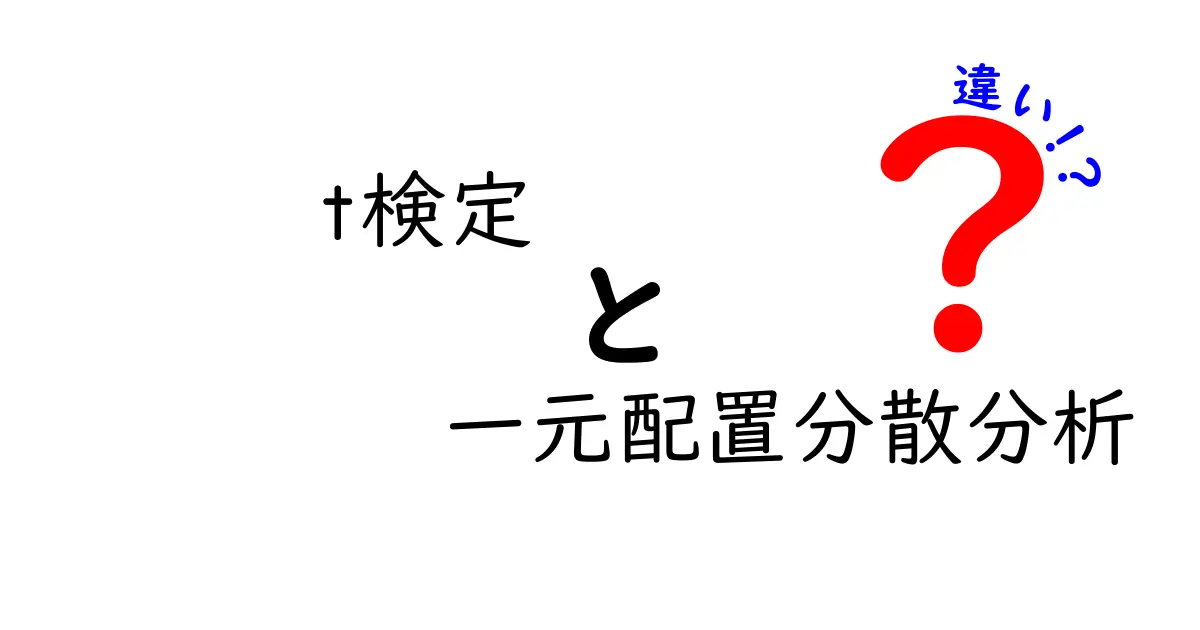

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
t検定と一元配置分散分析の違いを最初に掴もう
t検定は2つのグループの平均を比較するための手法で、独立して観測された2群における平均値の差が、偶然に生じたものかどうかを判断します。使用するデータが「正規分布に従い、各グループの分散が似ている」という前提を満たす場合に特に強い力を発揮します。ちなみに、対応のあるデータ(同じ人を2回測定するなど)は別の式を使い、2群の差を直接評価します。これに対して一元配置分散分析(ANOVA)は、1つの要因で複数のグループの平均を同時に比較するのが目的です。例えば「方法A」「方法B」「方法C」という3つのグループがあり、それぞれの平均点を比べたい場合に使われます。ANOVAは「どのグループの間で差があるか」を総合的に検出しますが、どの2つのグループ間で差があるかを特定するには別途の事後検定が必要です。
このため、研究デザインの段階で「比較したいグループ数」と「仮定」が決まると、どちらを使うべきかの判断がしやすくなります。後述する仮定の部分をよく理解しておくと、検定の結果を正しく解釈しやすくなります。
データの前提を理解する
二つの検定はいくつか同じ前提を共有しますが、適用範囲と前提の厳しさが異なります。正規性はデータが正規分布に近い形をしているかどうかで、t検定では特に重要です。等分散性は各グループの分散が似ていることを意味し、これが崩れると検定統計量が歪む可能性があります。独立性は各観測値が互いに影響を及ぼさないことを指します。現実のデータではこれらの前提がぬけやすく、検定の選択と解釈に影響します。例えば、教育実験で2群の生徒のテスト点を比較する場合、2群が同じ学校の生徒か、同じ時期に測定されたのか、などを確認します。
また、サンプルサイズの影響も大きく、サンプルが小さいと正確な推定が難しくなります。上述の前提を満たすかどうかは事前に確認するべきで、満たさない場合は別の統計手法や非参数検定を検討します。検討の過程で、研究の目的とデータの性質を明確にすることが、正しい結論につながる大事なステップです。
ざっくり比較表
以下の表は教科書的な要約です。数式の細かい導出や前提の厳密さまで網羅するものではありませんが、日常のデータ分析の判断材料として役立ちます。
実務的な使い分けのコツと例
実際にはデータの状況に合わせて選ぶのが基本です。2群の対比較であればt検定が分かりやすく、3群以上の比較ならANOVAを選ぶのが自然です。ただし、もしデータに欠測があれば両検定の扱い方が変わることもあり得ます。欠測データを除外して分析すると、サンプルサイズが減る一方で検出力が低下します。
また、複数の因子を同時に扱う場合は二元配置分散分析など別の手法が必要です。教科書だけでなく現場のデータで練習することが理解を深める近道です。普段の授業や部活動の記録、実験レポートなどを題材に、どの手法を選ぶべきか、どの前提が崩れると誤った結論に至るかを意識して練習すると良いでしょう。
放課後のカフェで友達とデータの話をしていたとき、彼は「t検定とANOVAの違いって実務でどう活かすの?」と尋ねてきました。私はこう答えました。まず2群のみを比較する場合はt検定を選ぶのが基本です。独立した2グループか、同じ人の前後データかで使う式が違う点を意識します。一方、3群以上のグループがあるときはANOVAが適切で、全体として差を検出した後にどの組に差があるかを調べるには事後検定が欠かせません。前提条件が崩れると検定の結果が信頼できなくなるので、正規性や等分散性、独立性を確認することが第一歩です。こうした話を通じて、 statisticsは難しい話題に見えても、身近なデータの「意味」を読み解くための道具だと気づきました。自分のデータにも同じ発想で向き合い、過度な結論を避け、欠測値の扱いにも慎重になることを心がけています。
次の記事: t分布とz分布の違いを徹底解説!中学生にも分かる基本と使い方 »





















