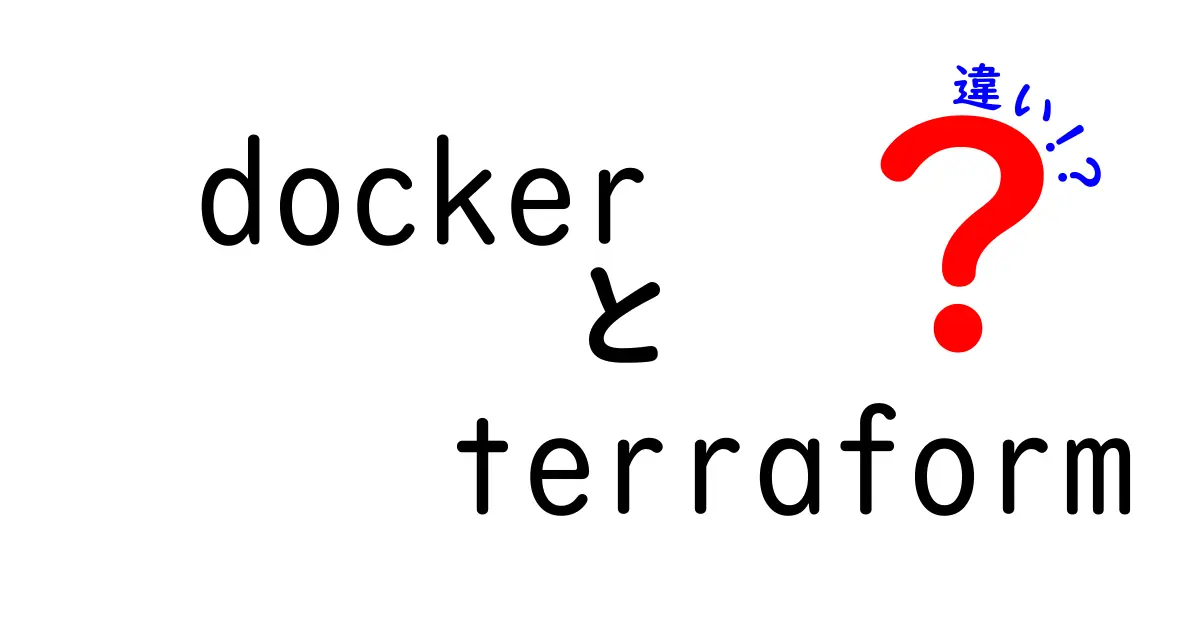

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
DockerとTerraformの違いを理解するための基礎
Dockerは「アプリケーションを動かす箱」を作る技術です。ソフトウェアとその依存関係をまとめて一つの単位にし、どんな環境でも同じように動作させることができます。
この考え方は「環境の再現性」を高め、開発者が動作の違いに悩む時間を減らします。
一方、Terraformは「インフラをコードで定義する道具」です。クラウド上のサーバー、ネットワーク、ストレージといったリソースを宣言的に記述し、実際の状態とコードを突き合わせて自動的に整えます。
つまり、Dockerは「何をどのように動かすか」を扱い、Terraformは「どんな基盤をどのようにつくるか」を扱います。ここが大きな違いの出発点です。
この二つを同時に使う場合も多いです。例えば、TerraformでクラウドのネットワークとVMを作っておき、そこにDockerを動かすコンテナを配置する、という使い方があります。
この連携は、インフラの安定性とアプリの再現性を両方確保するための現代的なやり方です。
ただし、運用の複雑さが増えることもあるので、目的に応じて使い分けることが重要です。
現場での使い分けの具体例と注意点
初心者向けの基本例として、ローカル開発環境を整える場合はDockerを中心に考えます。
開発者が手元で同じデータベースやアプリケーションを走らせるには、Docker Composeなどのツールを使うのが普通です。
一方で、クラウド上の環境を作って運用する場合はTerraformの出番です。VMを作るだけでなく、ロードバランサーやセキュリティグループまで含めて「どういう構成にするか」をコードで管理します。
ここでのポイントは、責任範囲を分けることです。Dockerはアプリ運用、Terraformはインフラ構成、この二つを混ぜすぎるとトラブルの原因になります。
また、状態管理の考え方も異なります。Dockerはコンテナの実行状態を扱い、基本的には「再起動すれば同じ動作をする」ことを目指します。
Terraformは「現在のクラウド資源の実際の状態」を保持し、それをコードと比較して差分を適用します。これを理解しておくと、バージョン管理やロールバックの設計が楽になります。
実務では、ドキュメントとコメントを丁寧に残す習慣をつけ、何をどう決めたのかを残しておくと、後から見直すときに役立ちます。
Dockerを語るとき、ただ“動く箱”という説明だけでは物足りません。実際には仲間と共通の箱を持つことで、動作環境の違いを気にせずに新機能の実装を進められる点が大きな利点です。例えば、同じDockerイメージを使えば別のパソコンでも同じ挙動が再現できます。とはいえ、これだけではクラウドの規模やセキュリティ設定まで自動化できません。そこで登場するのがTerraformです。DockerとTerraformを組み合わせると、アプリの実行環境とインフラの構成を両方コードとして管理できる世界が広がります。日常の会話の中では、「このイメージはどの環境で動くのか」を共有する習慣が、ミスを減らすコツです。





















