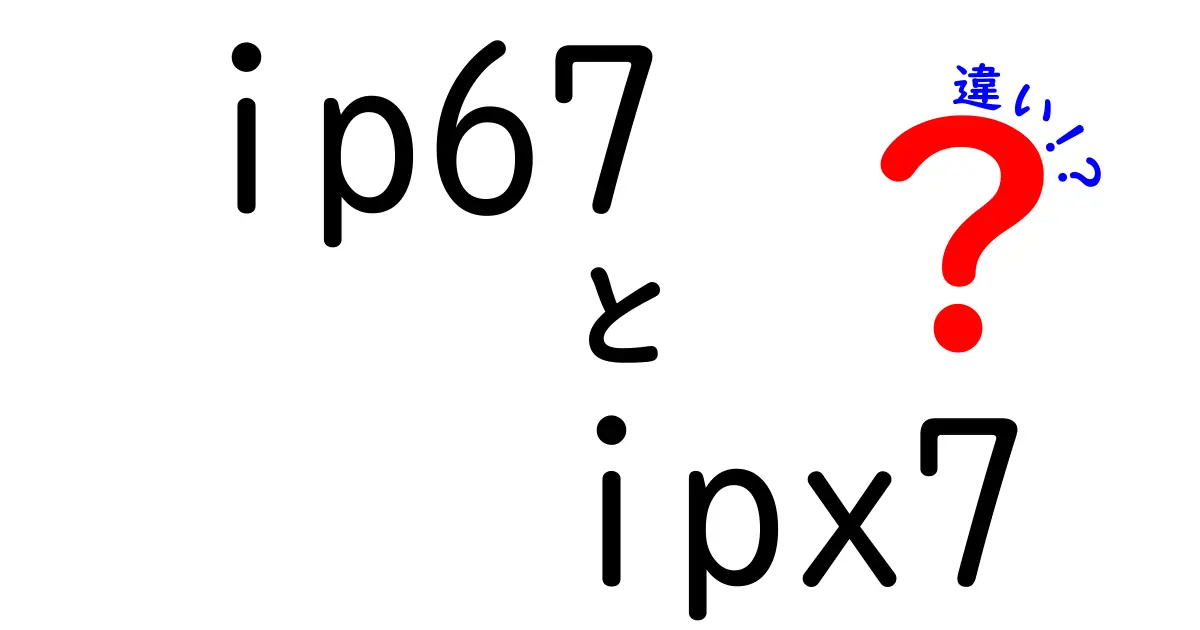

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
IP67とIPX7の違いを徹底解説:どちらが防水性能に優れているのか?防水規格の基礎から徹底比較
IP67とIPX7は、スマートフォンや時計、カメラなどの防水機能を判断するために使われる表示です。IPはIngress Protectionの略で、最初の数字は固体の侵入(粉塵など)、次の数字は液体の浸入を表します。数字が大きいほど防護性能が高いと理解してよいのですが、実際には「同じ7でも条件が違う」ことがあります。具体的には、IP67は「粉塵の侵入を完全に防ぐ」ことと「水深1mまでの浸漬に耐える」ことを同時に満たす組み合わせですが、IPX7は水の浸入耐性だけを評価し、粉塵の防護は公式には示されていません。誤解を避けるためにはこの点をきちんと確認することが大切です。
日常的には、IP67とIPX7の表示が同じように見えることがあります。たとえば雨に濡れる程度ならどちらも問題ないと思うかもしれません。しかし本当に重要なのは“水の深さと時間”と“埃の有無・環境”です。水深1mで30分の耐水試験をクリアしている場合でも、長時間の水中使用や温度の急激な変化には耐えられない場合があります。また、塵が多い環境ではIP67のほうが有利です。製品情報には、実際の耐水・耐塵は実環境と異なることがある点にも注意しましょう。
現場での見分け方と誤解を避けるポイント
現場で表示を読み解くときは、まず表記の有無だけで判断せず、規格の意味を理解することが大切です。IP67と書かれていても、塵のテスト条件を満たすか、日常的な雨や汗程度で十分かを現場のニーズと照らし合わせましょう。特に、埃が多い場所で働く人はIP67のほうが安心感が高いです。水辺での活動が多い場合はIPX7でも問題ないことが多いですが、長時間の水中利用には注意してください。さらに、長期使用でのパッキンの劣化や衝撃による隙間の発生も耐水性を低下させる原因になるので、定期点検を心がけましょう。
実務での選び方と注意点
選ぶときのコツは「想定される環境を具体的に挙げて、それに適合する規格を選ぶ」ことです。例えばスマホを日常的に持ち歩く学生ならIP67以上を選ぶと安心です。水辺で使う趣味のカメラやGPS機器はIPX7以上を目安にするとよいでしょう。製品の実測値は「試験条件と同じ環境で再現できるか」がポイントです。市場にはIPX7と表記されていて塵対策が弱い製品もありますので、塵の耐性が必要ならIP67の表記があるかを確認します。最後に価格と保証期間も判断材料です。
放課後、友達とスマホの防水の話をしていました。IP67とIPX7の違いを説明してと頼まれ、私は図解なしでも伝わるように言葉を選びました。IP67は塵を防ぎ水にも耐える組み合わせ、IPX7は水の耐性のみが保証されることが多い、という基本です。友達は「じゃあ雨に濡れても大丈夫?」とききました。私は「場所を想定して選ぶことが大事」と話し、砂埃の多い外で使うならIP67、室内や雨でも水没リスクが低い場面ならIPX7で十分なことがあると続けました。この雑談がきっかけで、私たちは日常の買い物で防水表記をどう読むべきか、実例を交えて理解を深めたのです。さらに、実際の場面で使うときのポイントとして、「水深・時間」「埃の有無」「ケースの密閉状態」を自分の使い方に合わせて判断する癖をつけると便利だと感じました。





















