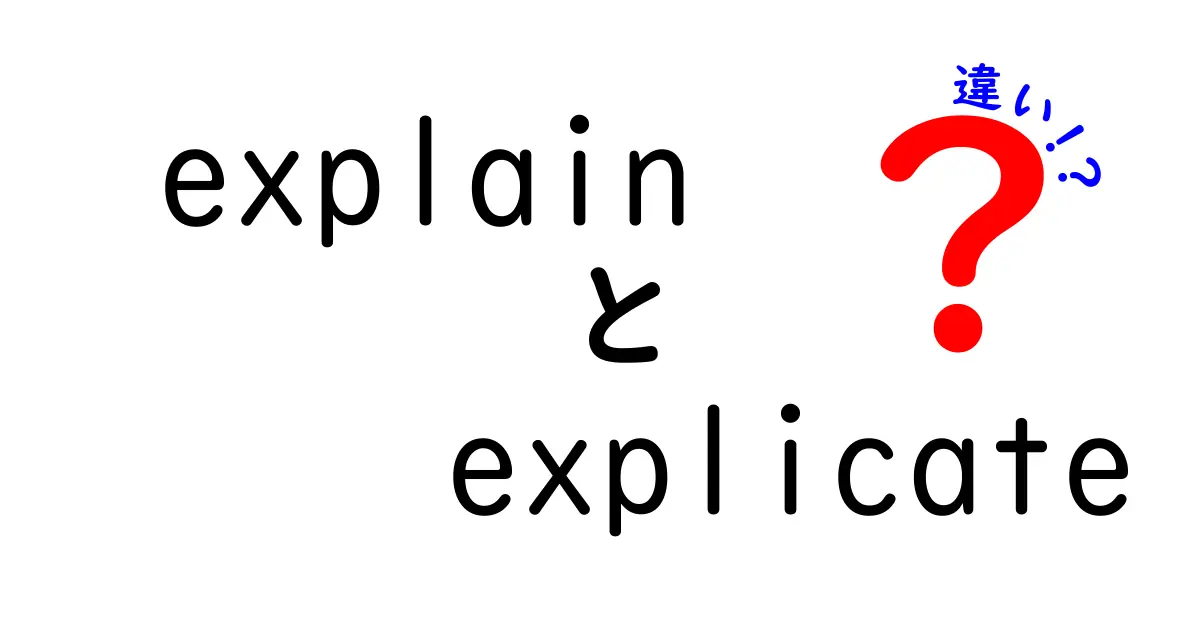

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
explainとexplicateの違いを徹底解説!中学生にも分かる使い分けのコツと例文集
explainとexplicate、この2つの英語表現は日常の会話でも使われますが、使い分けが難しいと感じる人も多いです。ここでは、まず基本的な意味とニュアンスを整理し、次に実際の文章での使い分けのポイントを、身近な例題とともに紹介します。読み進めるうちに、どちらを使うべきかの判断基準が自然に身についていくはずです。文章の長さや難易度、読者の想定知識レベルに応じて、説明の深さを変えることができるのもこの2語の特徴です。
なお、学術的な文脈では explicate の方が適切になることが多く、文学作品の解釈や哲学的論考、データの背後にある論理の分析など、深掘りした説明を求められる場面で頻繁に登場します。
本稿ではまず基本の意味の違いを押さえ、その後で使い分けのコツ、よくある誤用、そして具体的な例文を並べていきます。最終的には、説明の目的を明確にして適切な語を選ぶ力を養うことがゴールです。読み終えたとき、あなたが文章を読む相手の理解度をどう高めたいかを自分で問い直せるようになるはずです。
それでは、1章ずつ丁寧に進めていきましょう。
基本の意味と用途を整理する
explain の核は「人に理解させるための説明をする」ことです。説明の目的は、相手が前提知識を持っていなくても結論を納得できるよう、要点を整理して伝えることにあります。具体的には事実の提示、原因の列挙、手順の案内、事例の紹介など、受け手が理解の扉を開くための道筋を作る作業です。通常の会話や文章では、短く要点を絞った説明が好まれます。
これに対して explicate は「物事を詳しく分解して説明する」ことが中心です。物事の意味をただ並べるだけでなく、なぜそう言えるのかという根拠、仮定、前提、複数の解釈の可能性までを丁寧に提示します。学術的な文脈や分析的な文章でよく使われ、読者が結論へ到達するまでの筋道を透明にします。
つまり、explain は“分かりやすさを重視した説明”、explicate は“分析と解釈を重視した詳述”という使い分けの感覚をつかむことがポイントです。
すぐに結論だけ知りたい場面では explain が適しています。一方、論文や批評、深い理解を求める文章では explicate が好まれます。会話と文書、それぞれの場面での使い分けを実例で見ていきましょう。
なお、両者には重なる部分もあり、文脈によってはどちらを使っても意味が通じるケースもありますが、読み手の求める情報の深さと分析の程度を考慮して選択するのが良い方法です。これを覚えておくと、英語の文章を読むときの迷いがぐんと減ります。
使い分けのポイントと実践表現
このセクションでは、実際の文章での使い分けのコツを、具体的な例文とともに紹介します。
まず第一のポイントは「説明の深さの差」です。explain は短く端的に理由を挙げることで理解を助けます。対して explicate は事象の因果関係や論理構造を丁寧に分解して述べる場面で使います。次に「読者の立場を意識する」こと。初心者向けの文章には explain を、専門的な読者向けには explicate を選ぶと読みやすさが増します。最後に「前提を明示する」です。explicate の場合は前提条件や仮定を明確にすることで、読者が別解を検討する余地を残すことが多くなります。
具体的な使い分けの目安を以下の表で整理します。
この表を日常の文章づくりに活かすと、読者が読みやすい本文と、分析を好む読者のための深い解釈の両方を作ることができます。実践として、まず explain で要点を伝え、それを必要に応じて explicate へと展開するのが、バランスの良い書き方のコツです。
さらに、よく使われる表現例を挙げておきます。
- explain の例: “This study explains the effect of sunlight on plant growth.”
- explicate の例: “The paper explicates the underlying mechanisms by which sunlight influences cellular processes.”
誤用の典型と例文集
誤用の原因は、相手の理解度を過信して explanation を過剰に短くしてしまうことや、逆に複雑さを過度に強調して reader に負担をかけることです。以下の例で正しい用法を確認しましょう。
1) 誤用例: “We will explain the theory by explicating it in detail.”
正解例: “We will explicate the theory by outlining its main ideas and then explain how they relate to the evidence.”
2) 誤用例: “She explained the poem, and then she explicated the author’s intention.”
正解例: “She explained the poem and then explicated the deeper themes and historical context.”
このように、説明の深さと分析の程度を意識するだけで、誤用を大幅に減らすことができます。英語の文章を読み解く力は、日常の説明力にも直結します。日々の授業ノート、日記、ブログ記事など、使う場を広げて練習してみましょう。
ある日の放課後、友だちと英語の話題で盛り上がっていた。私は explain と explicate の違いを説明してみようと、ノートに例文を書き出してみた。友だちは最初「なんとなく分かる気がする」と言ったが、私が具体的な場面を挙げて説明すると目を輝かせた。私たちはまず explain で要点を伝え、次に explicate で背後の前提や論理を詳しく解説する形を練習した。日常の会話から学術的な文章まで、使い分けのコツを実感できた瞬間だった。
次の記事: 事業部長と本部長の違いを徹底解説:役割の境界線をわかりやすく »





















