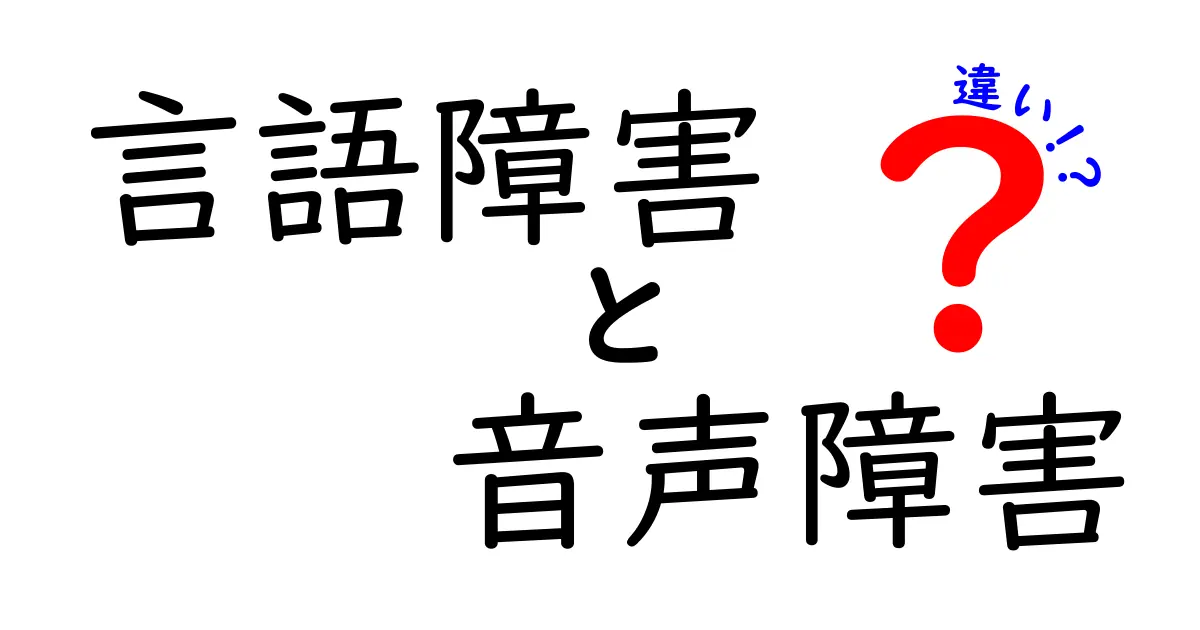

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:言語障害と音声障害の基本を知ろう
言語障害は、言語そのものを扱う脳の機能がうまく働かないことで起こります。話す言葉が出にくい、意味を理解するのが難しい、文章を組み立てるのが難しいなど、学校生活にも影響を及ぼすことがあります。対して音声障害は、声を出す仕組み自体や発声の動きに関わる障害です。声がかすれる、はっきり発音できない、どもりが生じる、舌や唇の動きがうまくいかないなどが典型です。
これらは似ているようで違いがはっきりあります。まず、言語障害は『言葉を理解し使う能力』の問題で、話し方だけでなく読み書きや会話の意味の理解にも影響します。音声障害は『声を出すための器官と発声機能』の問題で、実際の音の出し方や声の質が変わることが多いです。原因が異なるので対応も変わります。
言語障害は言語処理・理解の障害であり、音声障害は発声・音声出力の障害として現れます。こうした違いを知ることで、学校と家庭が協力して適切な支援を考えやすくなります。
早期の評価と適切な訓練が重要で、支援は個人の状況に合わせて組み立てるべきです。言語障害には読み書きの訓練、音声障害には発声練習・呼吸法・機器の活用など、目的に応じて異なる対応が必要です。
このページの結論としては、障害の根っこの性質を理解し、早めに専門家の評価を受けることが大切だという点です。子どもが学ぶ機会を最大限確保するには、家族・学校・医療・リハビリの連携が不可欠です。私たちは決して諦めず、子どもの強みを伸ばす道を探していくべきです。
違いを見分けるポイントと日常での対応
見分けるポイントは、子どもが何に困っているかを観察することです。言語障害は意味理解や語彙力、文章構成、質問への適切な返答などの分野で困難が見られます。音声障害は声の質、発音の正確さ、話す速さ、息継ぎのタイミングなど、声の出し方自体に問題があるかどうかで判断します。専門家の評価を受けることが安心で、診断結果に応じた訓練が進められます。
- 観察ポイント1:話すスピードが速すぎる/遅すぎる、口の動きが不自然かどうか
- 観察ポイント2:言葉の意味がつかみにくい、説明がうまく伝わらないかどうか
- 観察ポイント3:声の質が一定でない、かすれ・嗄声が続くかどうか
- 支援のコツ1:家庭と学校で同じ言葉づかいを使い、短い説明を繰り返す
- 支援のコツ2:聴覚支援や発音練習、呼吸法の導入を検討する
- 支援のコツ3:本人のペースを尊重し、プレッシャーをかけすぎない環境づくり
このような違いを理解しておくと、子どもが困っている場面を見逃さず、適切な支援を受けやすくなります。
周囲が過干渉にならず、本人のペースを尊重することも大切です。
私たちは、本人の強みを伸ばす支援を探し、日常生活の中で学習しやすい工夫を一緒に考えましょう。
友人とカフェで音声障害についての話をしていたとき、彼は自分の声を出すのに苦労していると話してくれました。私が最初に思ったのは、音声障害は単なる「声が出にくい」だけではなく、呼吸と発声を結ぶ体の使い方に深く関わっているということです。彼は授業中に発音がうまくいかず、友だちの前で話すのを避けがちでした。そこで私は、まず周囲の人が「どう伝えたいか」という意味を重視してくれる環境づくりが大事だと感じました。音声障害を抱える人は、テキストやメモだけでは伝わりにくい感情やニュアンスを伝えるのが難しいことがあります。そこで、私たちは短い文を繰り返し確認する、視覚的な補助(ジェスチャー・絵・テキストの併用)を使う、必要に応じて発声訓練の支援を受ける、などの工夫を一緒に探しました。結局、言語理解の部分は落ち着いて学習できるよう、発音の練習と聴覚面のサポートを並行して取り組むのが良い解決策だと感じました。つまり、音声障害は声の出し方と呼吸の連携を整えることがポイントで、周囲の理解と適切なサポートが学びの機会を広げるのです。
前の記事: « 大半と過半数の違いを徹底解説!意味・使い分けのコツと実践例





















