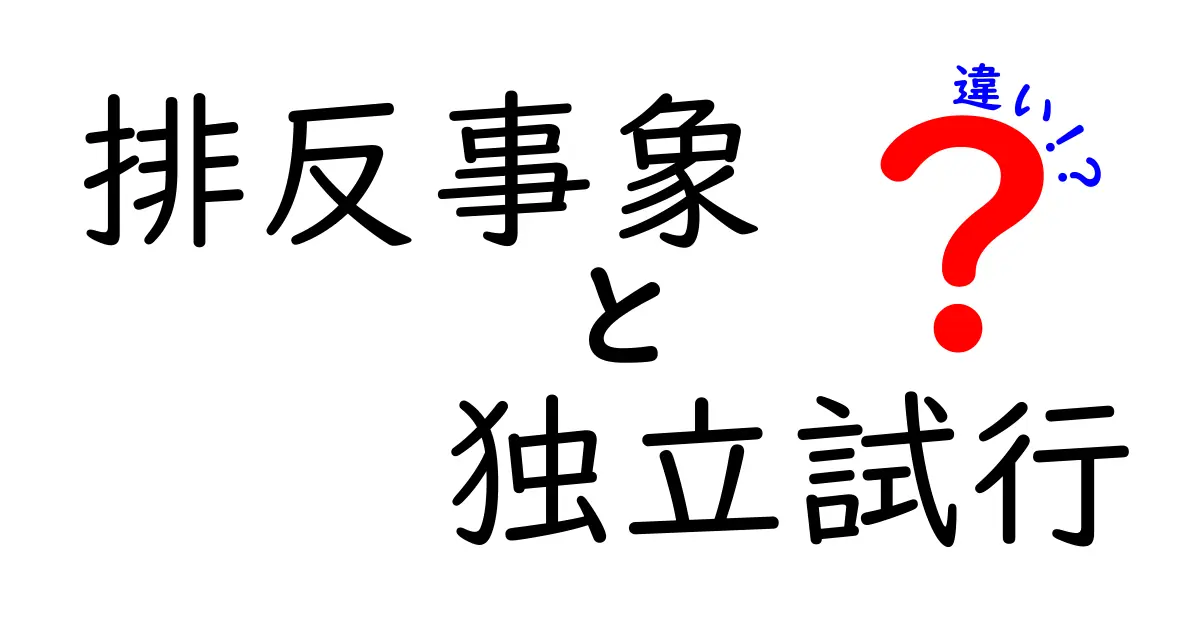

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
排反事象と独立試行の基本を押さえる
排反事象とは、同じ試行の中で同時に起こり得ない出来事のことを指します。たとえばコインを1回投げるとき、「表」が出ることと「裏」が出ることは、同時には起こりません。従って、Aを「表が出ること」と置けば、Bを「裏が出ること」と置くと、AとBは排反です。ここで重要なのは「同じ試行の中での関係」であって、試行の回数が増えると話が変わってくる点です。つまり、ある試行で排反であっても、別の試行では別の排反が起こる場合があるのです。数学的には、排反事象AとBが同時に起こる確率は0になるのが標準的な理解ですが、P(A ∪ B)=P(A)+P(B)となる場合が多く、P(A∩B)=0を満たすことが多い、という基本ルールを押さえます。これを把握しておくと、複雑な確率の計算を短く、正確に組み立てられるようになります。
さらに、排反の概念は「可能性の空間」を整理する助けにもなります。例えば選択肢が2つだけの場合を想定すると、どちらか一方が起こる確率と、もう一方が起こる確率の和が全体の確率の総和になることを前提に、残りの組み合わせを除外する作業が進みます。
このように、排反事象は「同時に成立しない」という基本的な直感をベースに、確率の加法性と全体の確率の分布を理解する土台になるのです。
強調すべき点は、排反は“同じ試行の中の関係”であり、独立試行とは別の概念であるということです。独立試行では、複数の試行が互いに影響を与えないという性質があり、AとBが独立である場合にはP(A∩B)=P(A)P(B)となり、排反とは同時成立の可否という性質が異なります。学習を進めると、排反と独立の違いがだんだんと頭の中でつながってくるはずです。
排反事象の実例と独立試行との違いを見分けるコツ
ここでは具体的な例を挙げて、排反と独立の違いを日常の場面に落とし込んで理解を深めます。例1として、サイコロを1回振る場面を考えます。出る目は1〜6のどれかですが、特定の「A」が出る確率と「B」が出る確率を同時に考えるとき、排反の考え方は「Aが出たらBは出ない」という前提になります。このとき、AとBは同時には起こり得ないためP(A∪B)=P(A)+P(B)が成り立ち、P(A∩B)=0であることを確認します。
この考え方を拡張すれば、例えば二回の独立した試行を同時に考えるときの関係が見えてきます。独立試行の鍵は「前の試行の結果が次の試行の確率に影響しない」という点です。例えばコインを2回投げる場合、1回目が表か裏かは2回目のコインの結果に影響を与えません。この場合、P(表1 ∩ 表2)=P(表1)P(表2)が成り立ち、AとBは独立です。つまり、排反であるか独立であるかを判別する基本ルールは「同じ試行の中の関係」か「試行間の関係」か、そしてそれぞれの組み合わせの確率計算でどう変わるかという点です。
さらに、日常の場面での区別をつけるヒントとしては、次のような観察が有効です。1) 同じ試行内で同時に起こりうるかどうか。2) 連続する試行で前の結果が次に影響を及ぼすかどうか。3) P(A∪B)の値がP(A)+P(B)で計算できるかどうか(できない場合は排反ではなく独立もしくは互いに影響する関係の可能性が高い)。こうした視点を日々の問題に当てはめて考えると、排反と独立の違いが頭の中で整理され、困ったときにもすらすらと答えを導き出せるようになります。
最後に覚えておきたいのは、排反と独立は別物だというシンプルな原則です。排反は同時成立を否定する概念、独立は結果が影響を与えないという関係。これをセットで覚えると、確率の問題がどんどん扱いやすくなります。
友達とくじ引きをしてみたときの会話を思い出そう。排反事象は、1枚引くと他の番号が同時に当たることはない、という感覚だよ。つまり、Aが成立したらBは必ず成立しない、というイメージ。だから『1が出るか2が出るか』で、同時にはもう片方は起きない。実はこの感覚が最初は難しいんだ。僕らは普段、“両方あり得ること”を勘違いしてしまいがちだけど、排反はその逆、“両立しない”という一点に着目して考える練習をすると、確率の世界がぐっと近づくんだよ。





















