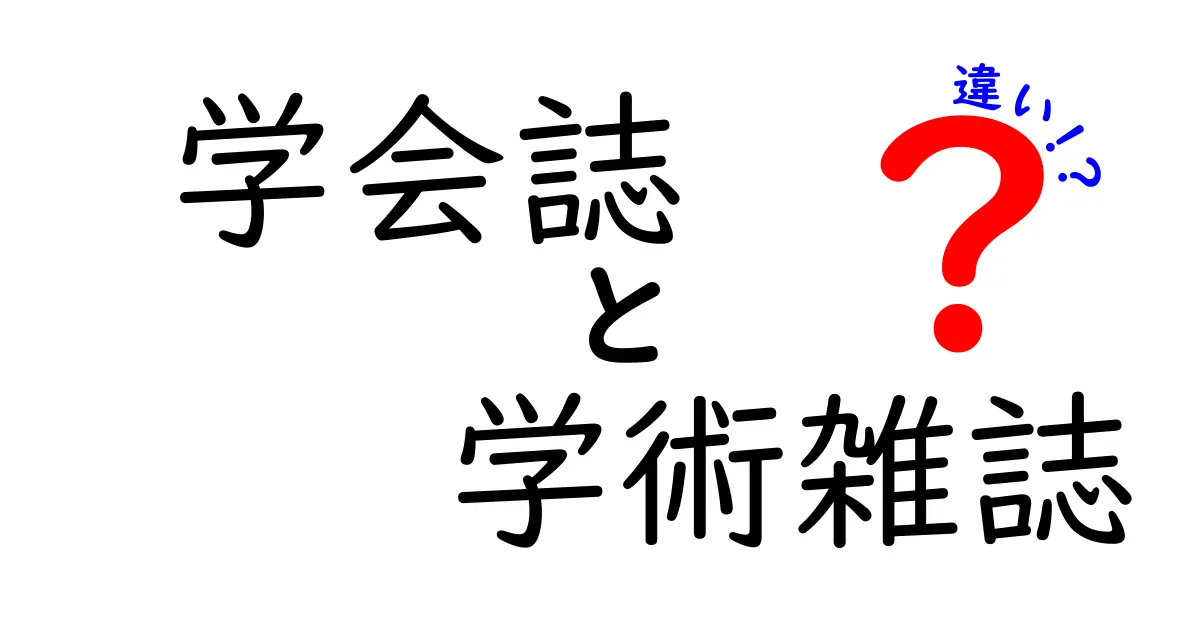

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
いまさら聞けない学会誌と学術雑誌の違い
学会誌と学術雑誌は、見た目は似ていることが多いですが、実際には目的や読者、発行体の考え方が大きく異なります。
まず大事なのは「誰が作っているか」です。学会誌は学会という組織が発行します。会員向けの情報提供や会合の案内、研究の速報などを中心に掲載されることが多く、研究者だけでなく学会員の活動や会の歴史を伝える役割も持ちます。読者は学会の会員が中心であることが多く、会員同士の情報共有や学会イベントの案内が重要なコンテンツになります。
一方、学術雑誌は出版社が刊行し、研究者が投稿した論文を審査して掲載します。こちらは主に研究の新しい成果を世界中の研究者に伝えることを目的としており、分野を越えた学術的な情報の蓄積にも寄与します。読者は国内外の研究者、教師、学生など広く多様で、学術的な評価指標や引用の影響力が重要な要素になります。
この2つの違いを理解しておくと、何を調べたいのか、どこに投稿したいのか、読むべき資料はどれかを判断しやすくなります。使い分けの基本は読者と目的の違いを意識することです。学会誌は教育的・組織的な情報を得るのに向いており、学術雑誌は研究成果を査読付きで広く共有する場として適しています。これを覚えておくと、正しく資料を選ぶ手助けになります。
小ネタ:査読の奥には人と時間がある
学会誌と学術雑誌の違いを話すと、よく耳にするキーワードのひとつが査読です。私たちが目にする論文の裏側には、複数の研究者が厳しく読み解くプロセスがあります。
この査読は、単に文章の正しさを確認するだけでなく、研究の背景や方法、データの扱い方、解釈の妥当性を第三者が検討する行為です。査読者は専門家としての時間をかけて論文を読み、質問を投げ、不足点を指摘します。そのやり取りの中で、著者は自分の研究を改良し、透明性と再現性を高めます。
だからこそ、学術雑誌に掲載された論文は信用度が高く、後の研究に影響を与えることが多いのです。学会誌の記事も貴重ですが、学術雑誌の査読済み論文は特に“長く残る価値”を持つことが多いと覚えておくと、研究の読み方が一段と深まります。
私たちが情報を鵜呑みにせず、背景や検証の過程を意識して読む習慣をつけると、学びはより深く、楽しくなるはずです。
次の記事: 幹部と指揮官の違いを徹底解説|組織を動かす役割の本質を理解しよう »





















