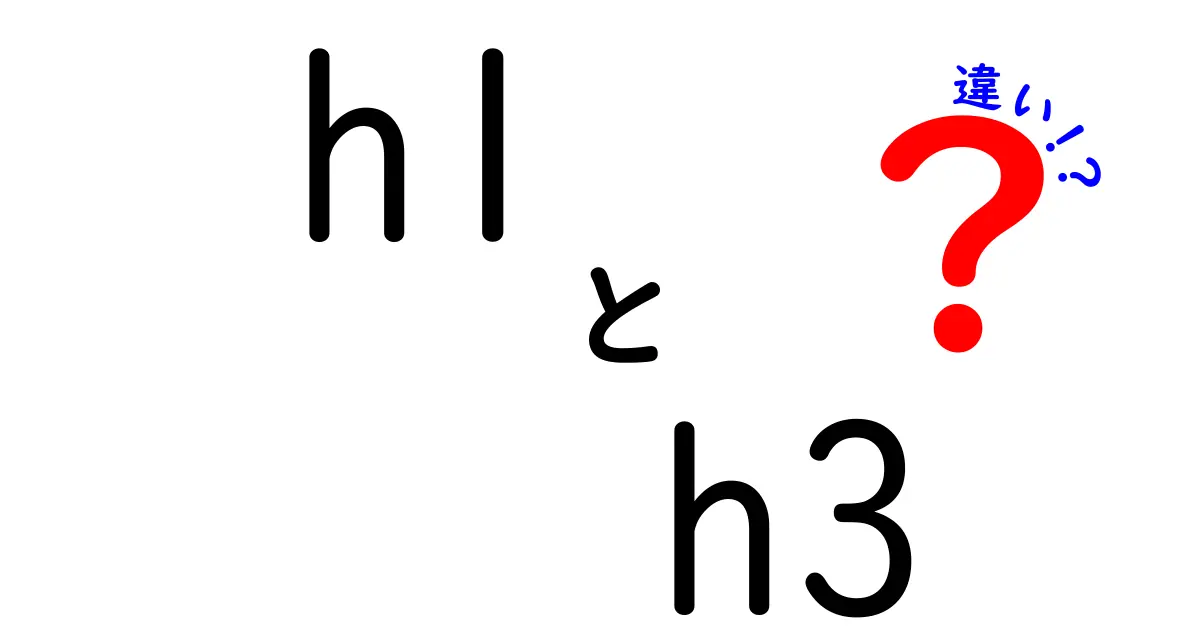

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
h1とh3の違いを徹底解説する背景と狙い
このテーマはブログやウェブデザインの現場でよく話題になります。h1とh3は見出しの階層を作る道具であり、読み手の理解と検索エンジンの評価に大きく影響します。多くの人が誤解する点は、ページ内に複数の h1 を置いてしまうケースや h3 を長文の前に使いすぎるケースです。そこで本記事ではまず基本の定義を押さえたうえで、実務での使い分けを具体的な例とともに丁寧に解説します。読者が混乱しがちなポイントは「見出しの階層は論理的につながっているべき」という点と「アクセシビリティのために順序を崩さないこと」です。これらを意識すると、記事の構成が読みやすくなり、検索エンジンにも伝わりやすくなります。
また、見出しの階層を正しく使うことはスクリーンリーダーを使う読者の体験にも直結します。
本記事では h1 と h3 の違いだけでなく、日常の文章やブログ記事での実践的な使い分け方を、チェックリストと具体の例を交えて紹介します。
h1の基本的な意味と使い方
h1 はページの主題を示す最上位の見出しであり、読者にとってページ全体の核となる情報を一言で伝える力を持っています。多くのケースでは1ページにつき1つの h1 を設定するのが基本ですが、HTML5 では複数の h1 を許容する設計もあります。しかし、複数の h1 を使うと構造が分かりにくくなるおそれがあるため、実務では1つの h1 を中心に他の見出しで階層を補う運用が安全です。日常の例としては、記事の最初の見出しに主題を置き、続くセクションで h2 を使い、さらに具体的な話題に対して h3 を用いる流れが分かりやすいです。
h1 を決めるときのコツは、語数を抑えつつ「そのページの最も伝えたい要点」を1つに絞ることです。長すぎる見出しは読み手の集中を削ぐ原因となるため、 要点を一つ絞る工夫 が求められます。
h3の基本的な意味と使い方
h3 は h2 の下位に位置する副見出しで、セクションの中の話題を整理します。h3 を適切に使うことで長い文章の中の話題の切り替えが明確になります。複数の h3 を用いて話題を段階的に細分すれば、読者は情報の流れを自然に追うことができます。SEO の観点でも、見出しの論理構造を保つことが重要です。h1 がページの核、h2 が大きなブロック、h3 がそのブロック内の具体的な話題というように階層を整えると、検索エンジンにも理解されやすくなります。
ただし h3 を多用して長くなると読者の集中が途切れることもあるため、要点を端的にまとめ、必要最低限の語を選ぶ工夫が必要です。
h1とh3の共通点と相違点
共通点として、どちらも見出しとして文章の流れを作る役割があること、そして検索エンジンに対して情報の階層を示す目印になることが挙げられます。相違点は主題の位置づけと使い方の頻度です。一般的には h1 はページの核となる要素であり、h3 はその核を補足する情報の分節を担います。デザインの面ではデフォルトの太さやサイズが異なる場合がありますが、最も大切なのは 見出しの階層を崩さず、情報の流れを自然に保つことです。
またアクセシビリティの観点からも、見出しの順序を正しく保つことでスクリーンリーダーの読取が安定します。
実務での活用と具体例
実務での基本ルールはシンプルです。1つの h1 をページの顔として設定し、そこから大きな話題を h2、次にそれぞれの話題の細部を h3 で分けます。
これにより、読者は記事の全体像をすぐに理解でき、知りたい箇所へ迷わず進めます。さらに accessibility を重視するなら、見出しの順序を崩さず、各セクションごとに内容を短く要約して書くと良いです。以下の表は実務での目安をまとめたものです。
注意点として、h1 を複数作る必要がない限り避ける、h2 や h3 の階層を飛ばさず連続させる、過度に長い見出しを作らない、などがあります。
この表を日常の作業チェックリストとして活用すると、見出しの構造が整理され、文章全体の可読性と検索エンジンの理解度が高まります。
なお、実践ではデザインとコンテンツのバランスを見ながら、必要に応じて h4 や h5 の活用も検討しましょう。
今日は h1 の話題を友達と雑談する形で深掘りします。私たちがブログを書くとき、最初に決めるべきはページの“顔”になる h1 です。友人のAさんはタイトルを長くしてしまいがちで、結局何を書きたいのか分かりにくくなっていました。そこで私はこう提案しました。h1 はそのページの主題を一言で伝える入り口なので、できるだけ短く、そして要点を一つに絞ると良いと。次に登場するのは h2 や h3 で、そこから話題を分けて階層を作るのが基本だと。Aさんは納得し、見出しの順序を整えるだけで読みに来てくれる人の導線がぐっと良くなると実感しました。もし友人が難しく感じるときは、まず「このページの最も伝えたいことは何か」を一行で書き出してみると良いでしょう。その一行を h1 に、次に大きなトピックを h2、細かい話題を h3 へと整理していくと、自然で読みやすい文書構造が生まれます。





















