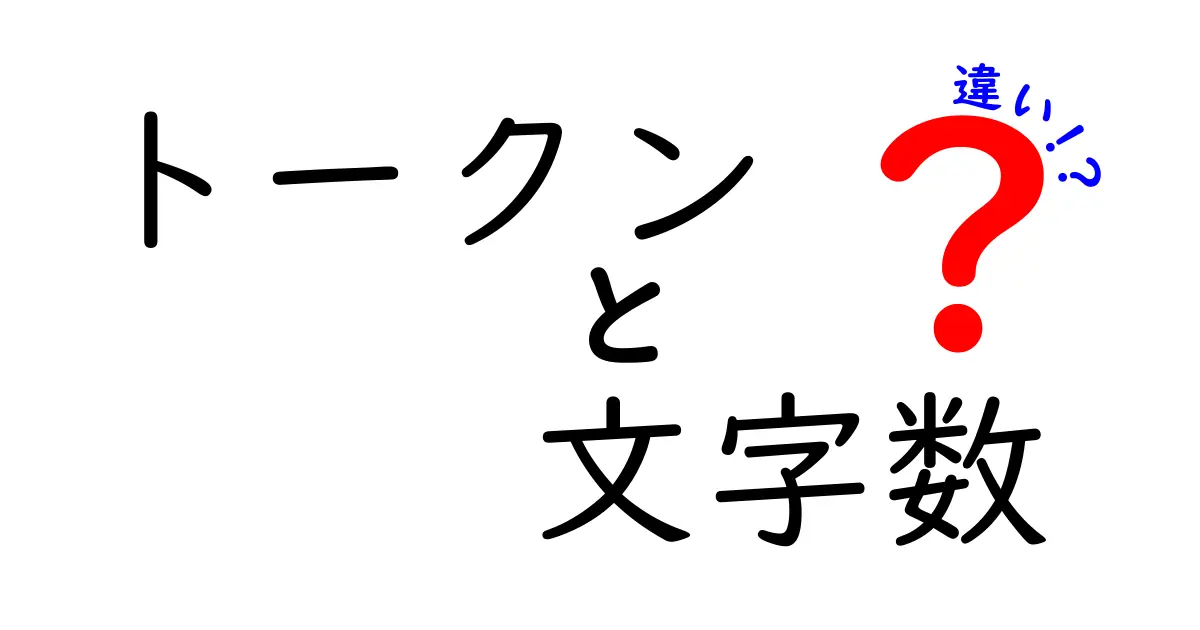

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
トークンと文字数の違いを理解するための導入
トークンと文字数の違いを理解するうえで大事なポイントは、数える対象が別のものだということです。文字数は画面に見える文字の数を数えます。例えば日本語なら一文字ずつ、漢字もひらがなもカウントします。しかしトークンは、文章を語や意味のかたまりとして数える“単位”です。日常生活の感覚とは違い、機械学習の世界では同じ意味を持つ文章でもトークンの数が変わることがあります。つまり、同じ長さの文章でも、どのように分かち書きや中間言語処理をするかによって、トークンの数は変化します。ここが大きな違いの出発点です。
この違いを理解すると、AIを使うときの“料金”や“動作速度”の見積もり方が変わります。文字数だけでなく、トークン数を意識することで、文章を短くまとめる工夫や、意味を損なわずにシンプル化するコツが身につきます。わかりやすく言えば、同じ文章でもトークンに分かれると何回処理されるかが影響し、結果として時間とコストの差が生まれるのです。
文章作成の観点からも、トークンと文字数の違いは重要です。授業のレポートやブログ記事を作るとき、伝えたい内容を損なわずに文字数を抑えるには、語のつながり方や助詞の扱いを見直す必要があります。こうした理解は、読者にとって読みやすい文章づくりにも直結します。ここから先は、具体的な例と実践的なコツを見ていきましょう。
トークンとは何かと文字とは何かを押さえる
まず基本を整理します。トークンとは、AI が文章を理解する際の“意味の最小単位”のことです。文字数は文字そのものを数えます。日本語のように語の境界が曖昧な言語では、トークン化の方法によって同じ文でも分解のしかたが変わります。形態素解析という技術を使うと、動詞・名詞・助詞などが別々のトークンとして扱われることが多くなります。
実際の例を挙げると、文「私は学校へ行く」は文字数で数えると7文字ですが、トークン数は分析の手法によって4〜6程度になることがあります。日本語は語の境界が曖昧なぶん、トークンの数え方は柔軟です。トークンの数は意味の切れ目と処理の段階に影響されるため、同じ文章でもモデルや設定次第で変わる点を理解しておきましょう。
この理解を把握しておくと、AI に頼る学習や研究での見積もりが正確になり、結果的に効率的な作業ができます。特に要約や翻訳、質問応答の場面では、トークンの最適化が全体の品質とコストに直結します。次の節では、具体的な数値の感覚と日常の活用例を見ていきましょう。
使い分けのコツと実務での影響
実務での使い分けには、いくつかのコツがあります。まず、文章を簡潔にする場合は、意味を保つ範囲で不要な語を削ることが大切です。日本語では助詞や接頭語の扱いを工夫すると、トークン数を抑えつつ読みやすさを保てます。次に、長い文章を要約する際は、要点だけを抽出して再構成する練習をすると、トークンの削減に効果的です。最後に、新しい表現を使うときは、意味が変わらないかどうかを確認するチェックリストを作ると安心です。
授業の課題や個人のブログ作成など、身近な場面で役立つ具体例を挙げます。たとえば、ニュース記事の要約を作るとき、文字数とトークン数の双方を意識します。短い文章でも、同じ情報を伝えるにはトークンをどう組み立てるかがポイントです。こうした視点を持っておけば、文章のリライトや翻訳のときにも混乱せずに進められます。
最後に覚えておきたいのは、トークン数はモデルと設定に依存するという点です。つまり、同じ文章でも利用するツールが変われば、表示されるトークン数も変化します。学習の段階でこの事実を意識しておくと、教材づくりの段階で誤差を減らせます。
放課後の教室で、友達と AI の話をしていて、トークンという言葉が出てきたときの雑談です。最初はトークンを『文字のかたまり』と覚えやすく説明していましたが、実際にはそれだけではないと気づきました。私たちはさらに深掘りし、同じ文を別の方法で tokenizer してみると、 token の数が大きく変わることを実感しました。結局、トークンは単なる文字の数ではなく、使う言語モデルの内部ルールと実装次第で変わる“動く指標”だと分かったのです。学習を効率化したいとき、トークン数を意識することは不可欠で、文章の構成を工夫するヒントにもなりました。授業の雑談を経て、私たちは学習のコツとして、まず文を分解する基準を決めてから書くようになりました。トークンの概念を知れば、AI との対話がずっと身近に感じられ、将来の学習にも役立つと確信しています。





















