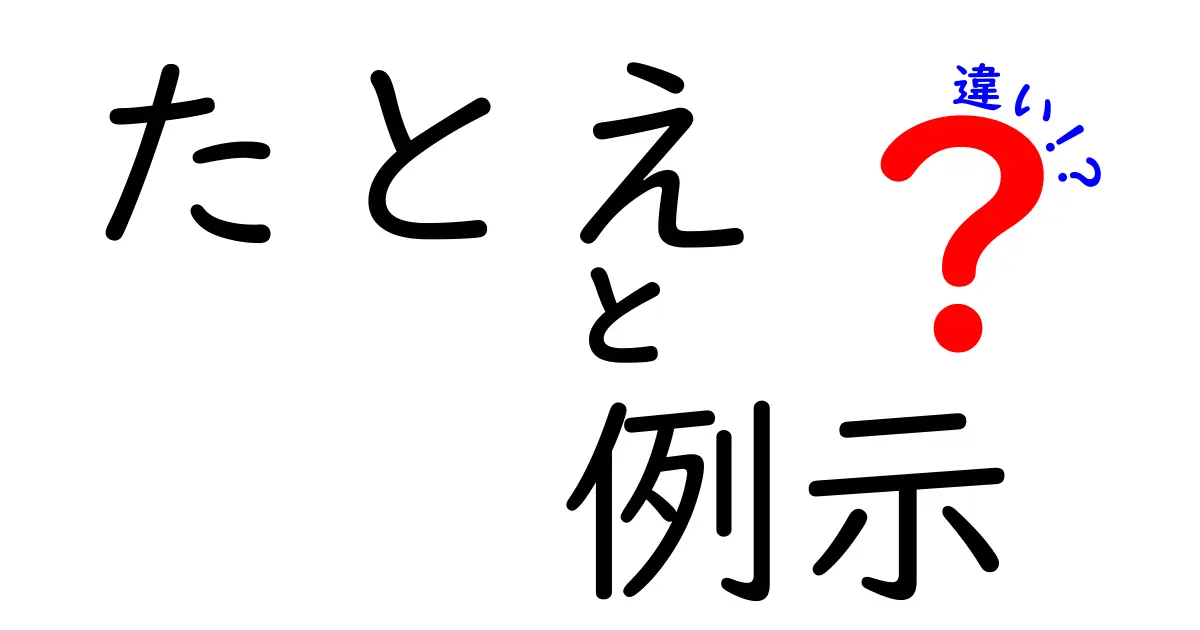

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
たとえ・例示・違いを徹底解説する総論
「たとえ」「例示」「違い」という三つの言葉は日常や授業、作文でよく使われる表現の道具です。混同されがちですが、それぞれ役割が違います。まずたとえとは何かをはっきりさせると、たとえは物事を別のものにたとえる言い方の総称です。話の中で難しい概念を分かりやすくするため、身近なものと結びつけて説明します。
また、たとえ話と呼ばれる短い物語の形でも使われ、登場人物や場面を通して読者の想像力を広げる役割を果たします。
一方で例示は具体的な事例を挙げて説明する方法で、「具体例を並べて理解を深める」ことが目的です。抽象的な説明だけでは伝わりにくい部分を、現実の状況や身近な出来事に結びつけて示します。
最後に違いです。違いは単純な意味の差だけでなく、文章の目的や読者の前提、説明の順序にも影響します。
この総論を押さえると、授業ノートも作文も、読み手にとって理解しやすい形へと整います。
たとえと比喩・たとえ話の違いを整理する
ここでは三つの言葉の関係を整理します。たとえは文中での仮定の話や別のものへの置き換えを表します。たとえば「雨が降るかどうかは分からない、たとえ晴れても外には出ない」など、現実における仮定を提示します。比喩は実際の意味を離れ、別のものになぞらえる表現です。「彼の心は石のように固い」は比喩です。一方たとえ話は物語形式で、登場人物の行動や出来事を使って概念を説明します。
これらは似ているようで、使う場面が違います。たとえば論理的な説明にはたとえ話を使わず、例示で具体性を高める方が適していることがあります。
以下のポイントを押さえると、混乱を避けやすくなります。ポイントA: 文章の目的を最初に決める、ポイントB: 反対の例を使うかどうかを判断する、ポイントC: 読者が身近に感じられる事例を選ぶ。
例示の使い方と注意点
例示は理解を深める強力な道具です。ここでは効果的な使い方と注意点を具体的に紹介します。まず目的をはっきりさせます。次に読者の興味に合わせて具体的な事例を選び、必ず一つの文章につき一つの例を挙げるよう心掛けます。さらに複数の例を並べるときは、難易度を順序立てて提示すると読みやすくなります。反対の例(反例)を併記すると、主張の信頼性が高まります。最後に例示の前後で言い換えを用意して、読者が「この例は自分の状況にどう当てはまるか」を結びつけやすくします。
実際の文章演習として、次のような流れで練習すると効果的です。
1) 目的の明確化、2) 具体例の選定、3) 反例の挿入、4) まとめの言い換え。
実践練習問題の例と解答
ここでは実際の練習問題を出して、どう使い分けるかを考えてみましょう。次の二つの文を読んで、どちらがたとえ・例示・その他の表現に近いかを判断してください。文A: ある人が新しいルールを受け入れるまでの戸惑いを、子どもたちの成長になぞらえた話として描く。文B: 新しいゲームのルールを説明する際に、現実の生活にある具体的な場面をいくつか挙げて順序立てて説明する。
解答のヒント: 文Aはたとえ話と結びつく比喩的要素がありつつも、物語性が強く読者を引きつける目的がある場合が多いです。文Bは例示が中心で、具体的事例の列挙を通じて理解を促します。
このように、文章の目的と読者像を想定して、たとえ・例示を選び分けると、伝わりやすさが格段に上がります。
最後に、実際の文章に組み込むときのコツとして、過度な比喩を避け、具体的で日常的な場面を選ぶことをおすすめします。
このまとめを覚えておくと、作文やプレゼン、授業ノートでの説明がぐんと分かりやすくなります。読み手の立場に立って、たとえと例示を適切に組み合わせる練習を重ねていくことが大切です。
今日は放課後のおしゃべり風味で小ネタをひとつ。友だちに『たとえ』と『例示』がどう違うかを説明しようとすると、よく迷子になるよね。僕はこう考えることにしている。たとえは仮定や比喩の道具箱、例示は現実の一場面を切り抜く写真アルバム。つまり、たとえは「もしもこうなったら」で話を広げ、例示は「この場面でこれが起きる」という具体を示す。両方を上手に使えば、説明がぐっと生き生きして、読者は頭の中で映像を思い浮かべられる。たとえば勉強のコツを説明する時、まず具体的な身近な場面を挙げて読者の共感を得たうえで、最後に抽象的な結論へとつなぐ。そうすることで、難しい言葉も自然と自分ごととして受け取られやすくなる。話の中盤で「仮定の話」へ進むときは、読者がついてこれるように順序立てて、馴染みのある例を選ぶのがコツです。結局のところ、たとえと例示は友だちの会話にも、教科書の文章にも、うまく使えば相手の理解を深め、伝えたい気持ちをしっかり届けてくれる道具なのです。
次の記事: 作者と語り手の違いを徹底解説!物語の視点が変わるとこう読める »





















