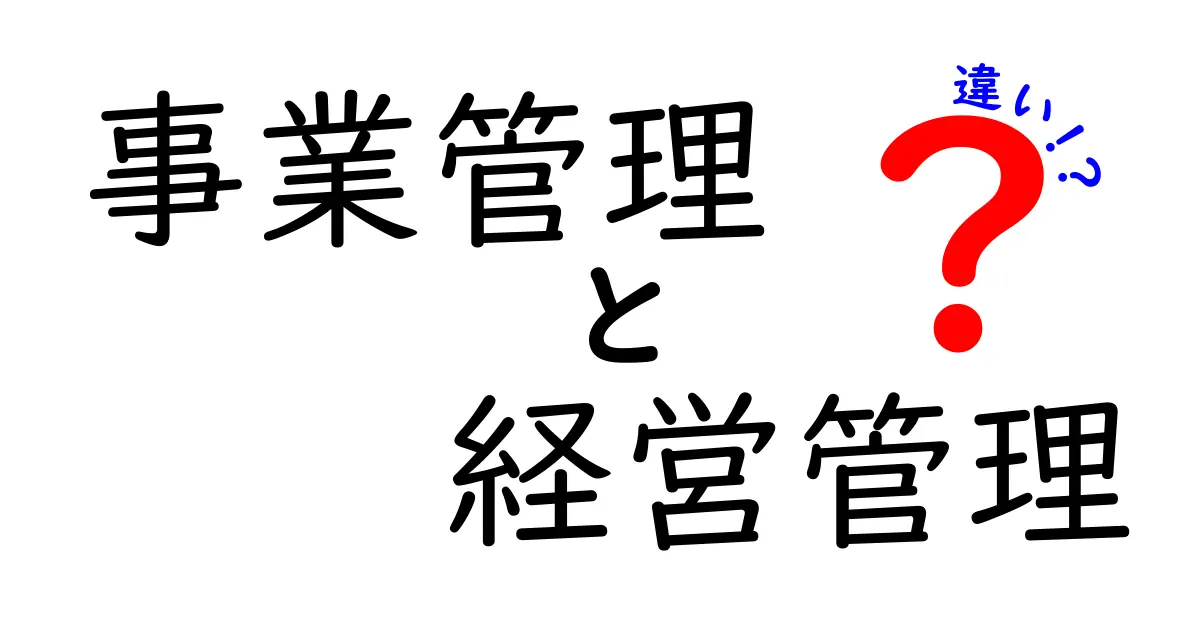

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
事業管理と経営管理の違いを丸ごと理解!現場と経営をつなぐ実践ガイド
本記事では、事業管理と経営管理の違いを、中学生にも分かる言葉で丁寧に解説します。
まずは「何を管理するのか」という基本の認識を共有し、次に現場の動きと経営の意思決定がどう結びつくのかを具体的な例で見ていきます。
結論から言うと、事業管理は日々の運用と数字の改善を担い、経営管理は長期の方向性と資源配分を決める役割を持っています。
この二つは別々の機能ですが、互いを支え合いながら、組織の成長を押し上げる大切な柱です。
事業管理の定義と現場での役割
事業管理とは、現場レベルでの実務と数字を結びつけ、日常の業務を効率化・最適化する作業のことです。
売上の推移、費用の内訳、原価計算、在庫回転、納期遵守、品質管理、顧客対応のスピードなど、さまざまな指標を追跡します。
現場のチームが何を達成すべきかを明確に伝え、進捗を可視化することが大切です。
課題が出たときには原因を特定し、改善策を現場のルールとして落とし込み、再発を防ぐ仕組みを整えます。
経営管理の定義と意思決定の場面
経営管理は、企業全体の長期的な方向性を決めるための考え方と手法です。
・予算編成・資金計画・投資判断・リスク管理・事業ポートフォリオの最適化などを含みます。
この領域では、データを元に「何を捨て、何を伸ばすか」を判断します。
意思決定はトップだけでなく、中間管理職もデータを持ち寄り、会議やレビューを通じて合意を得ていきます。
良い意思決定には、現場の現実と外部環境の動向を統合する力が必要です。
実務での使い分けと失敗事例
実務では、状況に応じて二つの管理を使い分けることが重要です。
日常の運用改善には事業管理の視点が欠かせません。
長期戦略や資源配分の判断には経営管理の視点が不可欠です。
ただし、両者が噛み合わないと、現場は数字だけを追い、戦略が現場に落ち着かないという失敗が起きます。
例えば、現場が追い込まれて短期の数字に偏りすぎると、投資が後回しになり、将来の成長機会を逃すことがあります。
逆に、経営陣が長期ばかり語って現場の実情を無視すると、組織の実行力が落ちます。
大切なのは、定期的な見直しと、現場と経営の対話を続けることです。
このように、二つの管理は役割が違いますが、互いの結果が会社全体の健康状態を決めます。
読者のみなさんも、学校の部活やクラブ活動を例に考えてみると分かりやすいでしょう。
日々の練習をきちんとこなす技能と、将来の大会へ向けての作戦を立てる戦略。
この二つがバランスよく動くと、クラブは強くなります。
そして企業も同じように、現場と経営の橋渡しを上手にすることで、安定的な成長を実現できるのです。
経営管理って、学校の運動会の総括役みたいなものだと思ってください。運動会では出場種目を決めるだけでなく、誰がどの役割を果たすか、予算はどう組むか、天候のリスクにはどう備えるかを決めます。経営管理もそれと似ていて、長期の方向性を決める力、資源の配分を決める判断、そして外部環境の変化を見越す力を持っています。日々の競技練習は事業管理が担当しますが、学年全体の方針を決めるのは経営管理。私たちが日常で使うデータにも実はこの二つの視点が混ざっているのです。





















