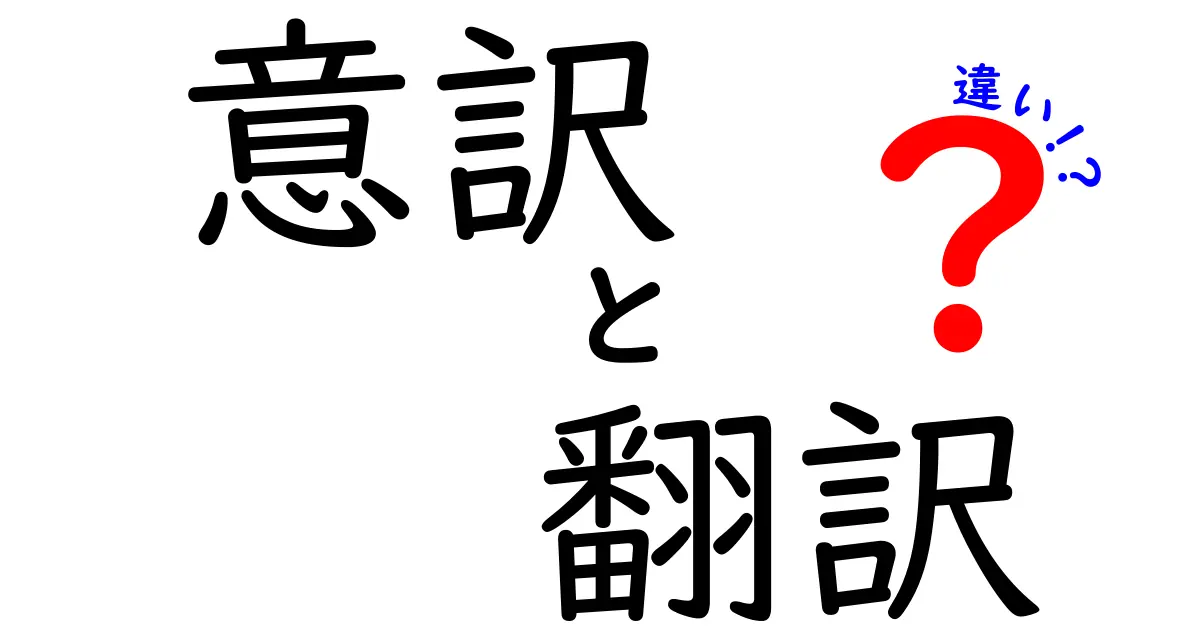

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
意訳と翻訳の違いを徹底解説
翻訳とは、ある言語の文章を別の言語へ移す作業です。意味を正確に再現することを最優先し、語彙や語法の選択、固有名詞の扱い、専門用語の解釈を丁寧に合わせていきます。とはいえ言葉は文脈と文化に深くつながっているため、原文の文字どおりの意味だけを追いかけると、読み手にとって不自然だったり理解しづらかったりすることがあります。そのため、翻訳では正確さを第一にしつつも、読み手が違和感なく読めるようにする工夫が必要です。
これに対して意訳は原文の意味や意図、雰囲気を重視し、読者が自然に理解できる表現に置き換えることを目指します。英語の慣用表現や文化的背景を日本語にそのまま直訳すると意味が伝わらない場合があり、その場合には別の表現へ置き換える判断が求められます。
つまり翻訳は正確さの確保、意訳は意味の伝達と読みやすさの確保を中心に置く作業です。言い換えれば、翻訳は"文字の移動"、意訳は"意味と感覚の移動"と言えるでしょう。ここで大事なのは、どちらを選ぶべきかを状況に応じて判断する力です。
この判断力を養うには、原文を読み解く力と、読み手の立場に立つ力の両方を鍛えることが必要です。読者が誰で、どんな場で使われる文章なのかを考える癖をつけると、自然と適切な方を選べるようになります。
また、学習のコツとしては、まず意味の核となる部分を拾い、それを別の言語で最も伝わる言い方に変える練習を繰り返すことです。意味の伝達を最優先しつつ、読み手の体験を損なわない表現を選ぶことを心がけましょう。
以下の表は、翻訳と意訳の違いを簡単に比べるための目安です。
例を一つ挙げてみましょう。原文の慣用表現を直訳すると直感が伝わりにくいことがあります。たとえば長い英語の慣用句をそのまま訳すと意味は明確にならず、読者には違和感が生まれます。翻訳は直訳を基本にしつつ、必要に応じて補足を入れて意味を保つ方向へ進みます。一方で意訳ではその慣用句がもつニュアンスを理解し、日本語で一般的に使われる比喩表現へ置き換えます。結果として読者には同じ気持ちや印象が伝わり、読書体験が自然で心地よくなります。
このような判断は最初は難しく感じられますが、練習を重ねると徐々に感覚がつかめるようになります。
次の節では、具体的な例を見ながら翻訳と意訳の違いをさらに詳しく確認します。
実例で見る翻訳と意訳の差
実際の英文を用いて翻訳と意訳の差を見ていきましょう。例1: 原文は It's raining cats and dogs. 直訳すると猫と犬が降っている、となりますが、日本語としては不自然です。翻訳としては土砂降りだと直訳の語感を生かしつつ自然な表現へ整えるのが安全です。意訳では土砂降りの意味合いを最も伝える日本語表現へ置き換え、長さやリズムを日本語に合わせます。例2: 原文の慣用句 never say die は文字通りには never だめだといった意味にはなりません。翻訳なら元の英語の語感を保ちつつ Never say die の意味を「諦めない心を失わないこと」といった表現に近づけることがあります。意訳ではより自然な日本語へ変換し、動機や情緒を読み手に伝える表現を選択します。
このように同じ原文でも翻訳と意訳は異なる道をたどります。重要なのは読者が理解できるかどうかであり、意味の伝達と読みやすさの両方をどうバランスさせるかです。読解力を高めるには、日常的な文章と難解な文章の両方で練習することが有効です。
場面別の使い分けと練習法
現場の状況に応じて翻訳と意訳を使い分ける練習を積むと、言語感覚が磨かれます。まずはニュース記事のように情報が明確で読者が実用的な文章を求める場面では翻訳寄りに保つのが安全です。物語やエッセイ、広告、演説など、読者の感情や印象が重要になる場面では意訳を選ぶと効果的です。練習のコツとしては、以下のような視点を持つことです。
1) 原文の核となる意味を明確にする。
2) 読者層を想定し、適切な語彙と文体を選ぶ。
3) 不自然な箇所があれば別の表現へ置換する。
4) 文化的背景が読み手に理解されにくい場合は補足を検討する。
5) 最終的な文章を自分以外の第三者に読んでもらい、自然さを確認する。このような手順を踏むことで、翻訳と意訳の両方を適切に使い分ける力が養われます。
最後に、学生時代の自分に伝えるなら、先入観を捨てて「伝える側の立場」で文章を見つめ直す習慣をつけると良いでしょう。読み手の体験を第一に考える姿勢が、よりよい翻訳とより自然な意訳を生み出します。
ねえ、意訳と翻訳の話って難しそうだけど、実は友だちとの会話に近い感覚で捉えると分かりやすいよ。翻訳は原文の意味をできるだけ正確に移す作業で、難しい語彙や専門用語も正しく扱うことが要求される。対して意訳は、原文の意味だけでなく雰囲気や話の流れを読者が感じられるように、自然な日本語へ置き換える作業。慣用表現の直訳は避け、場面に合わせて言い換える練習を積むと、意味を伝える力がぐんと伸びるんだ。たとえば日常会話のニュアンスを活かせるかどうかは、相手が何を感じてほしいのかを想像する想像力の差とも言える。私自身、英文を読んでほしい気持ちを日本語でどう伝えるかを考えるとき、まず意味の核をつかみ、それを読み手に合わせて表現する練習を繰り返している。最初は難しく感じても、少しずつ感覚がつかめてくるはずだよ。
次の記事: 口語訳と逐語訳の違いを徹底解説|意味のズレを防ぐ使い分けのコツ »





















