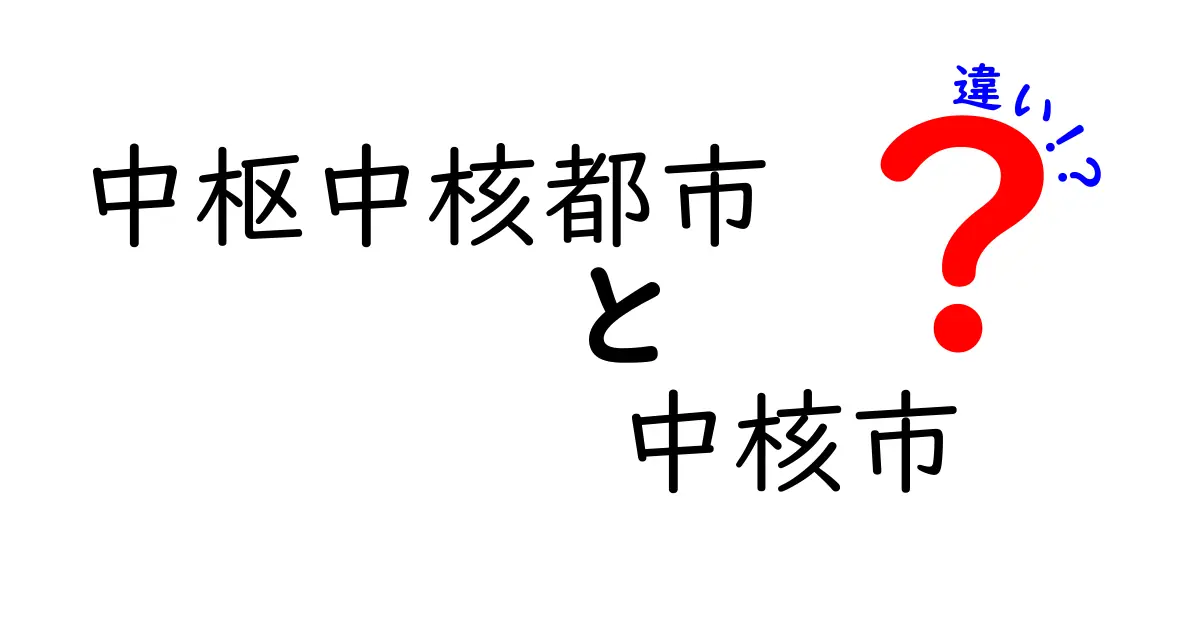

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに
日本には市の種類がたくさんありますが、特に「中枢中核都市」と「中核市」は似ているようで大きく役割や権限が異なります。
この記事ではこの二つの違いについて
分かりやすく、丁寧に解説します。
中学生の方も理解しやすいように、専門用語はなるべく使わずに説明しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
中核市とは?
まず「中核市」についてです。
中核市は、地方自治体の中でも比較的大きな市で、人口が20万人以上の市が基本条件です。
中核市になることで、今まで県が担当していた一部の事務 を市が担当できるようになります。例えば、
病院の管理や保健・衛生の分野での権限が移譲されることが代表例です。
また、中核市は地方自治法に定められた特別な位置づけがされているので、市の自治体としての自由度が高くなります。
中枢中核都市とは?
一方、「中枢中核都市」はまた違った意味合いを持ちます。
これは地域の中心となって、その周辺の街や町と密接な連携を取る都市のことを指します。
例えば、東京の足立区や名古屋市などの大規模な都市圏の中で、他の自治体と協力して
広いエリアの経済や生活を支える役割を担います。
中枢中核都市は「政令指定都市」や「特例市」の中から選ばれ、地域の中心として役割を果たします。
違いのポイント
では、この二つの違いをもっとはっきりと理解してみましょう。
| 項目 | 中核市 | 中枢中核都市 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 県からの事務権限の移譲 (保健衛生、病院管理など) | 地域中枢として広域の調整や連携 |
| 人口条件 | 原則20万人以上 | 政令指定都市や特例市の中から選出 |
| 権限の広さ | 県に代わり一部の行政機能を担当 | 複数自治体の代表として調整役 |
| 地域の範囲 | 市単独の範囲 | 周辺の町や市を含む広域 |





















