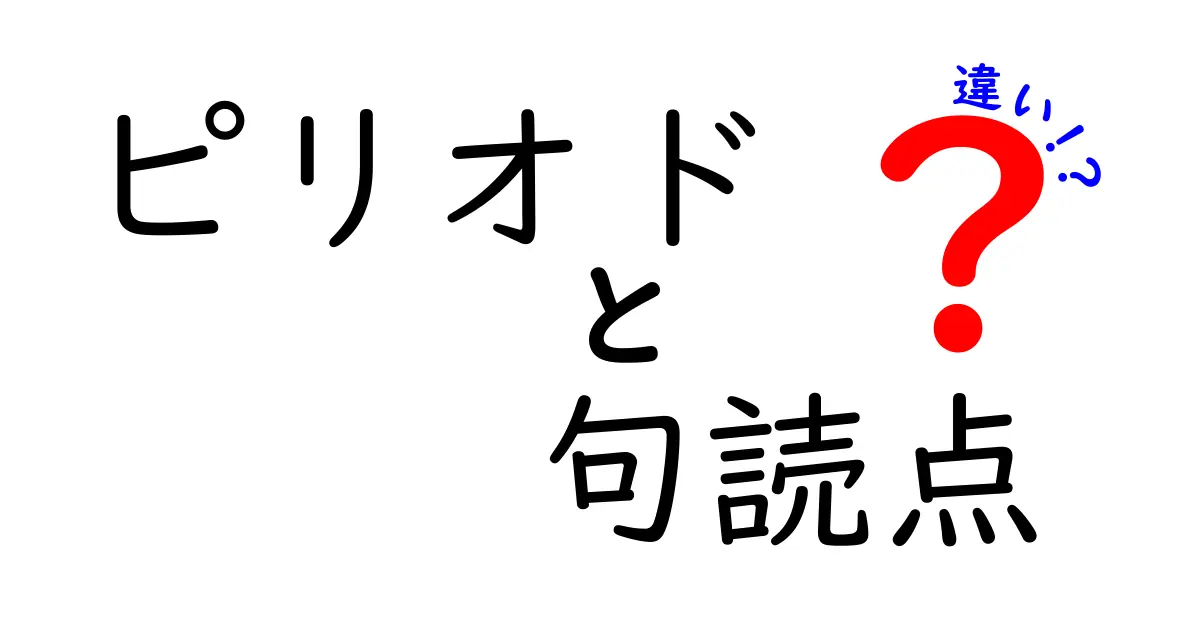

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ピリオドと句読点の基本的な違い
このセクションではピリオドと句読点の基本的な違いを中学生にも分かるように丁寧に解説します。
まずピリオドとは英語圏の文章で文の終わりを示す記号であり、形は半角のドットです。略語や頭字語の末尾、小数点としても使われます。例えば Dr. や U.S. のような略語の終わりにも登場しますが、日本語の文中で頻繁に使われるわけではありません。これは英語の文章を書くときの基本的なルールと一致します。
次に句読点とは日本語の文章を区切り読みやすくするための記号の総称です。代表的なものに句点の「。 」と読点の「、」があります。句点は文章の終わりを示す印として働き、読点は文の中の間を取る役割を担います。これらは日本語の自然なリズムを作るうえで欠かせない存在です。
ここでのポイントは二つの記号が使われる場面が異なり、意味する範囲が違うという点です。英語の文章を書くときはピリオドを使い、日本語の文章では基本的に句読点を使います。混在した文章では適切に切り替えることが読みやすさの決め手になります。
これを理解するだけで、英語風の文体と日本語の文体の差がすぐに感じられるようになり、文章の質が高まります。
使い分けのコツとよくある誤解
ここでは日常の文章作成での使い分けのコツと、よくある誤解について詳しく解説します。
まず前提として、日本語の文章では基本的に句読点を使います。特に長い文章や本文の中での区切りには読点を使い、文の終わりには句点を置きます。これに対して英語の文章では文の終わりを表す記号としてピリオドが使われるのが一般的です。日本語と英語が混ざる場面では、どの言語で書いているかを意識して適切な記号を選ぶことが大切です。
次のコツとしては読みやすさを第一に考えることです。例えば長い列挙や複数の節が続く場合にも読点を適切に使い分け、文の節と節の間に呼吸のような間を作ると良いでしょう。ピリオドを見かけた場合、それが英語の文末か日本語文章の終わりかを一目で判断できるように、前後の語彙や文体を確認してみてください。
また誤解としてよくあるのは、ピリオドは日本語の終末としても使えるという思い込みです。実際には日本語の正式な終わり方は「。」であり、英語風の文末を日本語の文章にそのまま混ぜると読みづらさの原因になります。英語風の文章を書くときはピリオドを使い、日本語だけの文章では句点を使うという基本ルールを守ることが大切です。
この理解を実践すると、作文のときに言語間の違いがはっきり見え、読み手に伝わる情報の「リズム」が大きく改善します。
ある日の放課後、友だちとカフェでピリオドと句読点の話題を深掘りしました。英語の教科書を日本語ノートに写すとき、行末に現れるドットをどう読むべきか迷っていたのです。私は「ピリオドは文の終わりを示す記号であり、英語圏の表現に欠かせないもの」と伝え、同時に「日本語の文章では基本的に句読点を使う」と補足しました。数字の小数点もピリオドと呼ぶ人がいますが、日本語では通常小数点と呼ぶこと、浮き出る場面は限定的だと説明しました。結局、日常のコミュニケーションでは読みやすさを最優先にして、文中の停滞を避けるための工夫として句読点を活用するのが良いと結論づけました。
次の記事: 中黒と句読点の違いを徹底解説!使い分けのコツと例文付き »





















