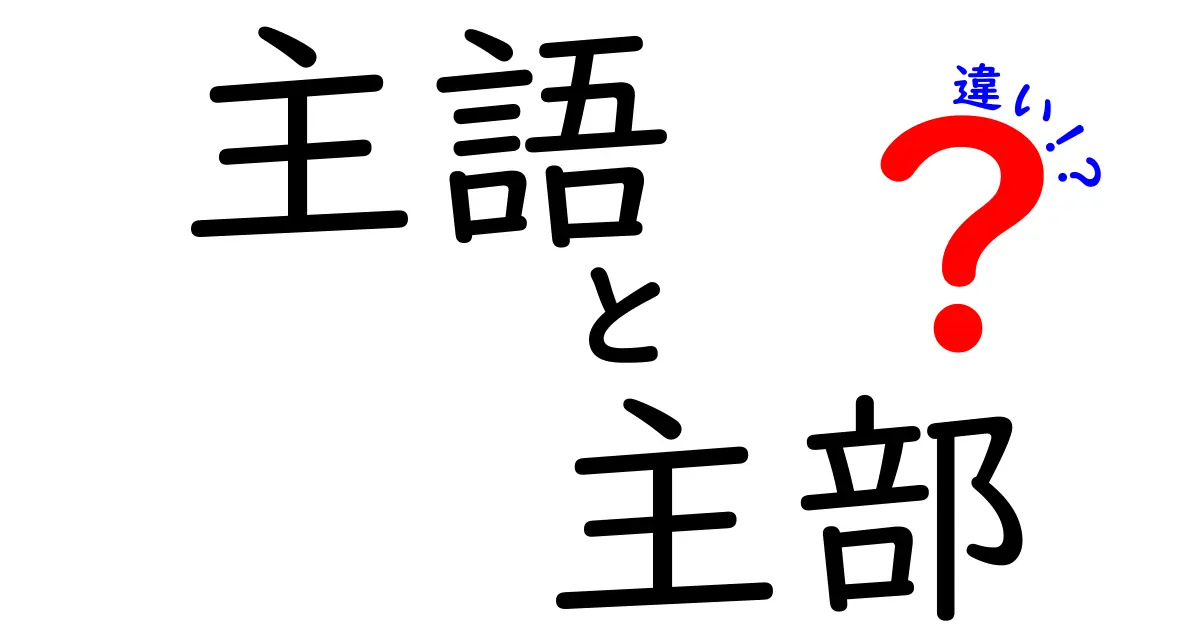

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
主語と主部の基本をおさえる
日本語の文には「誰が」「何が」が動作の主体になることが多いです。ここでのポイントは二つの用語、主語と主部を混同しないことです。
日常の会話では、主語を省略することもありますが、文の意味を決めるのは主語の役割が大きいです。
このセクションでは、まずそれぞれの基本を押さえ、次に実際の文でどう見分けるかを学びます。
以下のポイントを覚えておくと、文章の構造が見えやすくなります。
まず主語とは、文の中で「動作の主体」や「話題となる語句」を指します。
普通はが/はという助詞で marking します。例文として「太郎が走る」や「本は机の上にある」などが挙げられます。
主語は文の中心となる語が位置する部分で、他の語とつながることで意味を作ります。
文の意味を決定づける最初の鍵は、この主語の特定です。
ただし日常の会話では主語を省略しても意味は伝わることが多い点に注意しましょう。
一方で主部という用語は、学習者向けの文法書で使われることがある技術用語です。
多くの人には馴染みが薄いですが、厳密には「文の中心となる部分を指す枠組み」を表すことがあり、時には主語を含む名詞句や話題としての名詞句を指すことがあります。
つまり主部は必ずしも「主語そのもの」を示すわけではなく、文全体の中心を示す役割を担うことがあるのです。
このあいまいさが、主語と主部を混同してしまう原因の一つにもなります。
以下の例で違いを見ていきましょう。
この区別を理解するうえで大切なポイントは、主語が「誰が・何が」を示す語句であること、そして主部が文の中心となる部分を指し、場合によっては主語を含むこともあるという点です。
混同を避けるコツは、まず主語を特定してから、文が何を述べているのか(述部)を確認すること。
この順序で見れば、主部が何を指しているのかが見やすくなります。
例をもう少し増やして考えてみましょう。
「犬が吠える」では、犬がが主語であり、吠えるが述部です。
「この本は面白い」では、この本はが主部(トピックとしての部分)で、面白いが述部です。
このように、主語と主部は文の中で異なる役割を持つことがあり、状況によっては同一の語が両方の役割を担うこともあります。
実例で見る主語と主部の違いと使い分け
実際の文を使って、主語と主部の違いと使い分けを見ていきましょう。
高学年の入門として、まずは基本の考え方を押さえ、次に語順や助詞の使い方で微妙なニュアンスを学ぶのがよい方法です。
以下の例は、日常会話でも使われやすい文を選んでいます。
それぞれの例で主語と主部の関係を分けて考える練習をします。
例1: 日本語の省略現象を使った文です。
「明日、学校へ行く。」この文は主語を省略していますが、話者が学生であることを前提にすれば意味は通ります。
この場合、主部は「明日、学校へ行く」という文全体の中心となる部分を指します。
過去形や否定形にしても基本の考え方は同じです。
例2: トピックとしてのはの使い方。
「この本は難しいです。」この場合のこの本はは主部として機能し、難しいですが述部です。
「この本は難しいです」を「この本が難しいです」と言い換えると、ニュアンスが少し変わります。
この差は、話し手が話題を強調したいときに重要です。
例3: 部分的に主語が変わる場合。
「私が作ったケーキはおいしい。」ここでは私が作ったが主部として機能し、おいしいが述部です。
この文は、誰が作ったかを強調しつつ、ケーキ自体の美味しさを述べています。
主語と主部の組み合わせによって、伝えたい情報の焦点が変わる点を覚えておきましょう。
次に、誤解を避けるコツをまとめます。
第一に、文の中心となる動作や状態を示す部分を必ず特定すること。
第二に、助詞の役割を理解すること。
第三に、作文や話す前に「この文の主題は何か」「この文の述部は何か」を自問してみること。
この三つのポイントを押さえれば、主語と主部の違いをより正確にとらえられるようになります。
まとめと使い分けのコツ
本記事の要点をまとめます。
主語は文の主体を指す基本的な概念で、通常はが/はで示されます。
一方で主部は文の中心となる部分を表す技術的な概念で、教科書や文法の枠組みによって扱い方が異なることがあります。
実際の文章では、主語と主部が必ずしも別々に現れるとは限りません。
文の意味をすっきりさせるコツは、まず主語を特定し、次に述部が何を伝えようとしているかを確認することです。
日常の練習として、簡単な文章を声に出して読んでみると、主語と主部の位置が自然と分かるようになります。
友達と雑談していて、ふと「主語と主部って同じじゃないの?」と聞かれたんだ。僕は「違うけど切り分けると解きやすいよ」と答えた。例えば『この本は面白い』、この『この本は』は話題としての主部みたいに働くことがある一方、『面白い』は述部で、意味は本当に“この本が面白い”って伝えてる。そんな話をしているうちに、二人とも“主語は誰・何が動くか”を探すゲームみたいだと気づいた。学べば学ぶほど、作文や発表の時に伝えたい焦点をうまくコントロールできるようになるよ。
前の記事: « 句と文節の違いを徹底解説!中学生にも分かる日本語の文づくりガイド
次の記事: 【完全版】係助詞と助詞の違いを中学生にもわかる図解つきで解説! »





















