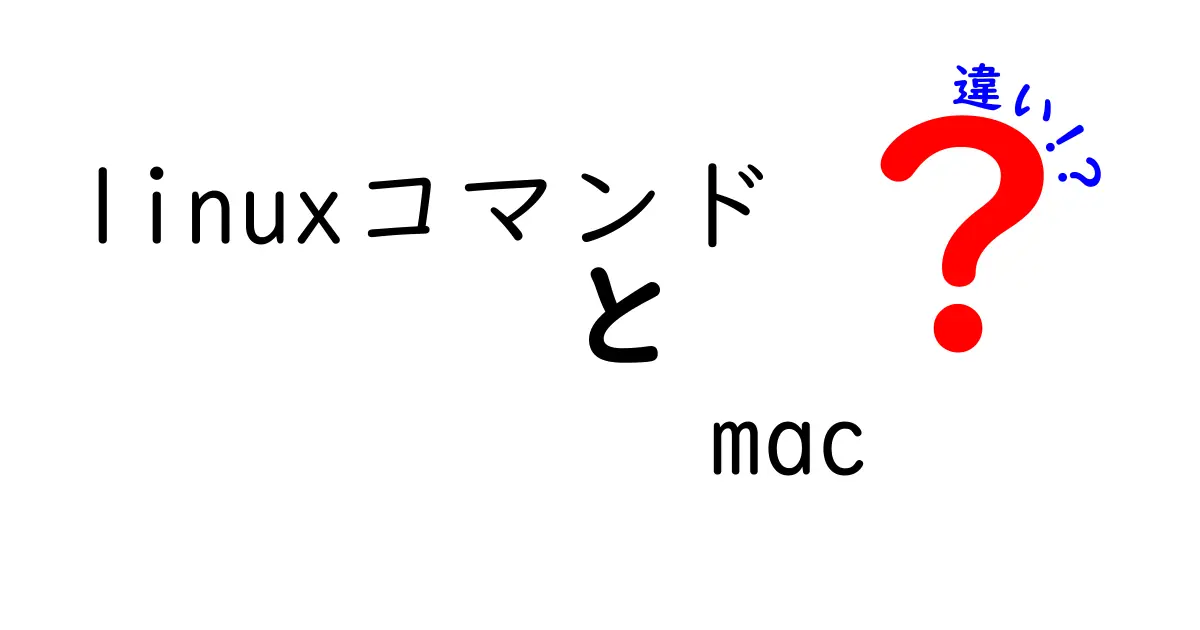

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
LinuxコマンドとMacの違いを徹底解説:初心者でも分かるポイントを丁寧に
現場でよくある質問の一つに Linux と Mac のコマンドが同じ名前でも挙動が違うのかという点があります。結論から言うと、基本動作は似ていますが細かい仕様やデフォルトのツール構成、パスの扱いなどが OS によって異なるため、スクリプトや日常の作業で予期せぬ結果になることがあります。たとえば Mac は BSD 系の sed や ps などが標準で入っており GNU 版とのオプション設計が異なることが多いです。この違いを理解する第一歩は、コマンドのリファレンスだけでなく、どの OS で実行しているのかを前提として覚えることです。さらに、近年 Mac に Homebrew を導入して GNU ツールを追加するケースが一般的になっており、GNU 版と BSD 版の挙動差を意識して使い分ける癖をつけると混乱を避けやすくなります。これらの背景を知っておくと、連携する人が違う OS を使っていても自分の作業を正しく伝えやすくなるでしょう。結局のところ、OS の違いを理解することは新しい環境に飛び込むときの心の準備にもつながり、学習の速度を上げる鍵になります。
ファイル操作の基本の違い
ファイル操作の基本の違いは、ディレクトリの表示やファイル名の扱いだけでなく、シンボリックリンクの扱い方や検索の挙動にも影響します。Linux の多くは GNU 版のツールを前提に動くことが多く、オプション名や挙動が Linux 用と BSD 用で微妙に異なることがあります。例えば ls の色分けや表示形式、場合によってはファイルサイズの表示桁が違う場合があります。Mac ではデフォルトで BSD 系のツールが使われるため、オプションの意味が同じでも挙動が異なる場面があり、スクリプトを移植するときには注意が必要です。パスの表現としては、Mac は /Users/名前 という形を使い、Linux は /home/名前 が一般的ですが、どちらの環境でもパスは必ず正確に書くことが大切です。さらに、ファイルの権限や所有者の扱いは共通ですが、ファイルシステムとして APFS か EXT4 かなどのファイルシステムの差が将来の挙動に影響する場合があります。こうした点を把握しておくと、同じコマンドを使っても出力が変わる場面を前もって想定でき、トラブルの防止に役立ちます。
パイプとリダイレクトの扱いの差
パイプとリダイレクトはコマンド同士をつなぐ基本テクニックです。実際には Linux も Mac も大半のケースで動作は同じですが、デフォルトのシェルの違いが混乱の元になります。Mac の現行デフォルトは zsh で、これによりパイプの書き方や glob の解釈、配列の扱いなどが Linux の Bash とは微妙に変わることがあります。さらに、標準入力と標準出力の混在処理やファイルエンコーディングの扱いにも気をつけるべきです。リダイレクトの基本、たとえば出力をファイルに保存する > の挙動は同じですが、エラー出力の扱いは OS によって微妙に異なる場合があります。つまり、複数のコマンドを組み合わせて結果を得るときには、OS ごとの挙動差を意識してテストすることが安全です。
ねえ、さっきの話なんだけど、Linux と Mac のコマンド差は単純な名前の違いだけじゃなく背景にある設計思想の差まで及ぶんだ。ぼくはこの話題を友だちと雑談しながら解くのが好きで、Linux 側の自由度と Mac 側の安定性という対比を思い浮かべる。grep のパターンマッチングの挙動は版によって微妙に変わることがあり、同じスクリプトでも Mac で実行すると異なる結果になることがある。だからこそ、スクリプトはできるだけ POSIX 準拠で書くのが無難だと僕は考える。もし OS をまたぐ環境で作業するなら、Shebang に /bin/sh を使い、使うコマンドが POSIX 仕様に準拠しているかを事前に確認する癖をつけたい。結局のところ、その小さな差を理解しておくことで、読みやすく移植しやすいコードを書く可能性が広がるし、勉強にもなるよ。





















