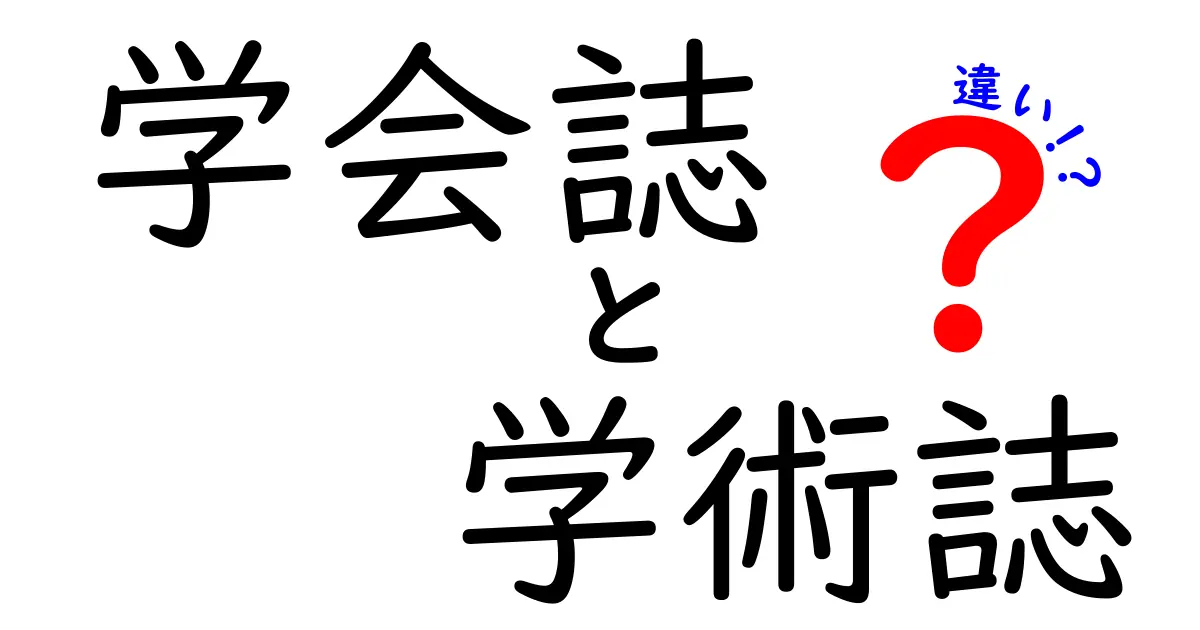

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
学会誌と学術誌の違いをやさしく解説
学会誌と学術誌という言葉を聞くと、似ているけれどどこが違うのか分からなくなる人が多いです。とくに研究を始めたばかりの人や、論文を読むのが初めての中学生にも分かるよう、具体的な例と身近な比喩を使いながら説明します。まずは「学会誌」がどんなものかを押さえ、その後「学術誌」とはどう違いがあるのかを順番に見ていきましょう。学会誌は研究者だけでなく、研究を支えるスタッフや会員向けの情報も多く含みます。研究の最新動向を追う人にとっては、会員になるメリットが大きいことがあります。
一方、学術誌は世界中の研究者が読み、引用され、評価されることを目的に作られることが多く、論文の質を公的に評価する仕組みが整っています。読者は同じ分野の研究を深く理解したい人が多く、学術誌の論文は大学の授業や研究計画にも使われます。これらの違いを把握することで、論文を探すときに「どの本を読めばいいのか」「どこに投稿すれば良いのか」を判断しやすくなります。
以下の説明と表を読めば、学会誌と学術誌の特徴が見える化され、実務の場面での使い分けがしやすくなるはずです。
学会誌とは?発行元・目的・特徴
学会誌は、主に学会という組織が発行します。発行元が学会そのものという点が大きな特徴です。学会誌には、以下のような情報が多く含まれます。
・会議の案内や報告、会員ニュース
・研究の速報性が高い特集や短報
・分野の動向解説、実務に役立つ情報
学会誌の目的は「会員のつながりを深め、分野の発展を支えること」です。そのため、最新の研究成果だけでなく、教育的な解説や現場の事例紹介も多い傾向があります。研究の新しい成果がまだ正式な査読を経ていない段階で掲載されることもあり、速度と実務性を重視する場合に向いています。
読者は主にその学会の会員や、同じ分野の研究者・教育者・実務家です。学会誌には、研究者同士のネットワーク作りや、学会イベントの情報収集にも役立つ特徴があります。
| 観点 | 学会誌 | 学術誌 |
|---|---|---|
| 発行元 | 学会 | 学術団体・学会を含む複数機関 |
| 主な目的 | 会員向け情報・速報 | 査読付き論文の公開・評価 |
| 査読 | 必須でないことが多い | 必須または厳格な査読 |
| 読者 | 会員・分野の実務関係者 | 研究者・学生など広範囲 |
| 掲載内容の性質 | 解説・事例・ニュース中心 | 研究論文・総説・特集 |
学術誌とは?査読と評価の仕組み
学術誌では、提出された論文が「査読」という評価プロセスを通ります。査読は、同じ分野の専門家が研究の新規性・正確さ・方法の適切さを厳しく点検する仕組みです。査読を経て、編集部が最終的に掲載可否を決めます。査読には主に以下の3つのモデルがあります。
1. ブラインド査読(著者を隠して行う)
2. オープン査読(著者と査読者が互いに名前を明かす)
3. ハイブリッド査読(公開と非公開の組み合わせ)
- 掲載の可否は、研究の新規性・再現性・透明性などが基準になります。
- 学術誌は引用されやすくなることで研究者の評価にも影響します。
- 著者は研究データの透明性・再現性を示すことが求められることが多いです。
この査読制度の有無と厳しさは、学術誌を選ぶ際の大きな判断材料になります。査読があることは研究の品質保証の一つの指標となり、学術誌を読む読者にも信頼性を伝えます。
違いを日常や研究現場でどう使い分けるか
研究の第一歩として、論文を探すときには自分の目的に合わせて刊行物を選ぶことが大切です。新しい情報を速報で知りたい場合は学会誌の特集やニュースを活用、学術的に深掘りして理解したい場合は学術誌の論文を読むのがよいでしょう。さらに、論文投稿を考えている人は、学術誌の投稿規程・査読ガイドラインを事前に確認することが重要です。
例えば、研究デザインの再現性が問われる領域では、データの入手方法・解析コードの公開状況が重要な評価ポイントになります。
また、学術誌は広く国際的な読者を想定していることが多いので、英語での要約(アブストラクト)や図表の説明が丁寧であることを確認すると良いでしょう。
読者によって求められる情報の粒度が違うため、自分が何を知りたいのかを最初に決めておくと、読むべき刊行物を絞り込みやすくなります。
会話っぽい雰囲気で、キーワードの“査読”を深掘りします。友だちとカフェで、「査読って本当に役立つの? どうして論文って厳しくチェックされるの?」と話し合う場面を想像して書きました。私たちが学校で提出するレポートにも、事実確認とデータ整合性が大切ですよね。査読は、研究者同士が互いの研究をチェックし、間違いを減らす“共同作業”の一部です。査読の方法にはブラインドやオープンなどの形式があり、それぞれに良さがあります。結局は、読者が信頼して読める成果物を作るための仕組みです。
前の記事: « 実験手順と実験方法の違いを徹底解説 どちらを使い分けるべきか





















