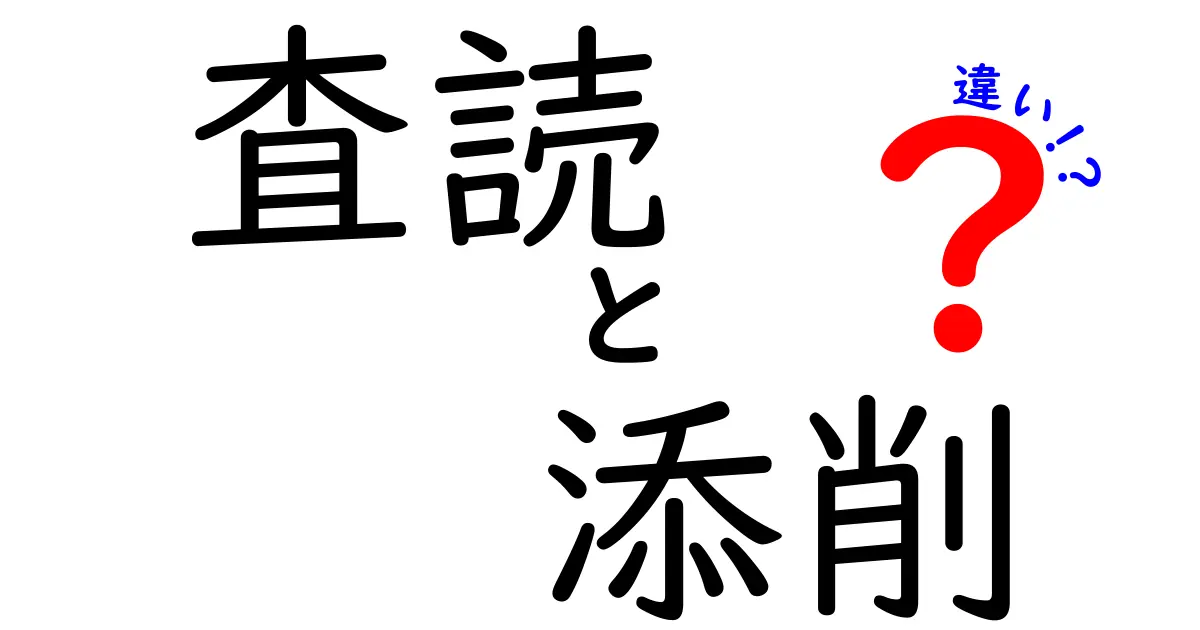

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
査読・添削・違いを徹底解説するガイド
この章では、まず「査読」と「添削」がどう違うのかをやさしく説明します。
学術的な場と教育の場の違いを同時に押さえ、なぜ二つが別の作業として必要なのかを理解します。
「査読」は専門家が論文の内容の正確さを確かめ、研究の新しさや再現性を評価します。
一方で「添削」は文章の読みやすさや表現の正確さを整える作業で、学力や学級の授業でよく使われます。
この違いが分かれば、課題の提出物をどのように準備すればよいかが見えてきます。
以下のセクションで、それぞれの特徴・目的・実際の場面を詳しく比較します。
ポイントを押さえておくと、今後の学習や研究の場面で役立ちます。
「査読」と「添削」の基本的な違い
「査読」と「添削」は見た目が似ていても、役割と権威がぜんぜん違います。
まず、査読は学術論文が公表される前に、同じ分野の専門家が内容を評価する仕組みです。匿名性があることが多く、投稿者の名前が分かっても審査員は自分の意見だけを伝えます。目的は「正確性・新規性・再現性・方法の妥当性」を確保することです。
査読を通過することで、論文は学術誌に掲載される可能性が高くなり、研究の信頼性が高まります。
次に、添削は、学校の宿題や普段の文章で使われるもので、教師や編集者が文章のミスや読みやすさを整えます。文法の誤り、語彙の選択、段落のつながり、らぶるなどの配慮を直します。
添削の結果は、評価や点数に直結することもあります。読者が読みやすいように、文体を統一したり専門用語をわかりやすく置き換えたりします。
このように、査読は研究の信用を守る仕組み、添削は文章の伝わりやすさを高める作業だと覚えておくと理解が深まります。
なお、査読は通常、複数の審査員によるフィードバックが集約され、原稿の修正を求めることが多いです。添削は個人の editor の腕に左右されることが多く、対象も学術論文だけでなく、作文・レポート・論文の体裁など多岐にわたります。
ポイント:査読は「公表の前提となる評価」、添削は「表現の改善」です。
現場での使い分けと実践例
現場の場面を想像してみましょう。修士課程の学生が新しい研究をまとめた原稿を提出する際には、まず「査読」を想定します。研究の新規性、データの解釈、統計の使い方、再現の可能性などを専門家がチェックします。この時、著者の名前は隠されることが多く、評価は原稿そのものの質で語られます。査読を通過するためには、方法の詳しさ、データの透明性、限界の正直な説明などが求められます。
一方、学校の作文や学習ノートを直すときには「添削」を使います。先生は文法、語彙、表現、段落のつながりを直してくれます。ここでは「読み手が分かりやすいか」が最も重要です。添削では、指摘の仕方や修正の根拠を丁寧に示してくれると、学生は自分の書き方のクセを理解し、次回から自分で修正できるようになります。
このセクションでは、両者の使い分けを、学校の提出物と学術論文の例を並べて見せました。
もしも研究者が日々の研究ノートを公開する場合、そこで得られた内容が将来「査読付き論文」に発展することも現実的です。そんな時には、ノートの段階での添削も役に立つでしょう。
表にまとめて比較することで、何を変えるべきかが見えやすくなります。以下の表を参照してください。
この表を見ると、同じ“直す作業”でも目的や対象が大きく違うことが分かります。
次の章で、実際の使い分けを日常の課題に生かすコツをまとめます。
結論のヒント:研究の信頼性を高めたいときは査読、伝え方を整えたいときは添削を使い分けるのが基本です。
放課後、友だちと話していたときのこと。私は「査読って難しく感じるよね」と言うと、友だちは「研究者が書いたものを、専門家が読んで“こう直せ”って指摘するんでしょ?」と尋ねてきました。私は「そう。査読は論文が正しく、再現性があるかを専門家が厳しく見る仕組み。公表の前の最終チェックみたいなものだよ」と答えました。続けて添削の話をすると、友だちは「添削は先生が文章のミスを直してくれるイメージかな?」と納得。私たちは、ノートの英語表現を整える練習を想像しながら、どうして二つの作業が必要なのかを具体的な場面で整理しました。査読は“学術の信用”を守る盾、添削は“伝わる文章”を作る道具。この二つがあるおかげで、学びの世界はより正確で読みやすくなるんだと感じました。
次の記事: 原稿と草案の違いを徹底解説!意味・使い分け・実務での活用法 »





















