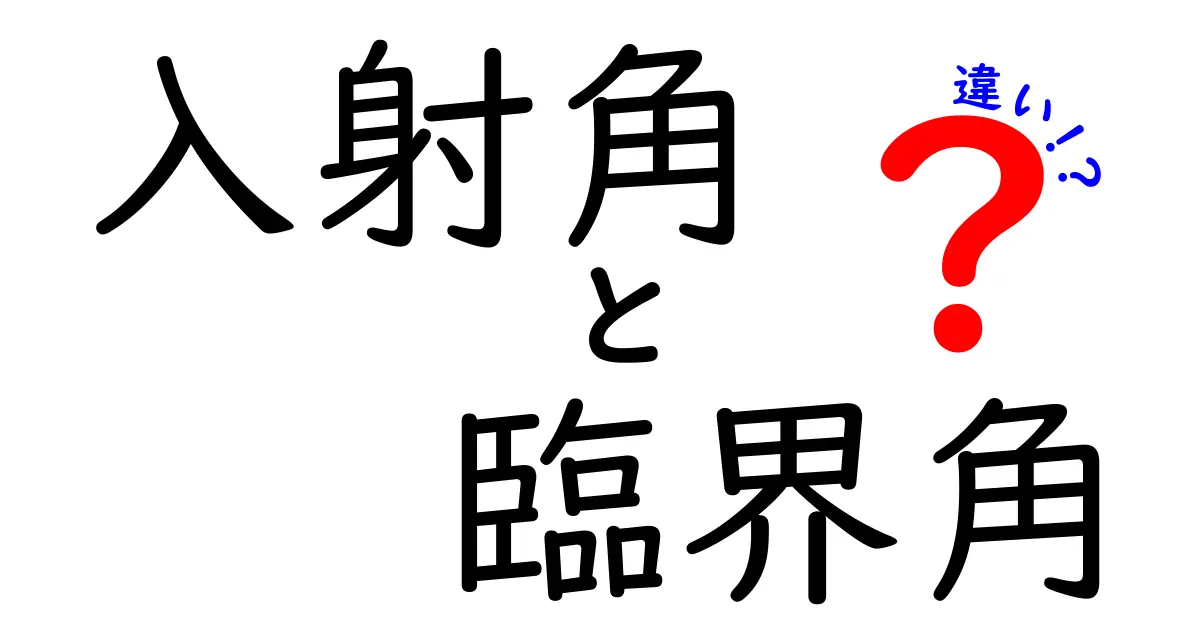

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
入射角と臨界角の違いを徹底解説!中学生にもわかる実例つきガイド
入射角とは光が媒質の境界に入るときの進行方向の角度のことです。普段の生活では、太陽光や懐中電灯の光が境界を越えるときに見かける現象として、鏡に映る像や水面の反射などが挙げられます。
この角度は観察者の位置や媒質の性質で変わり、角度が違えば光の通り道も違います。
私たちは入射角を知ることで、光がどう境界を越えるか、あるいは反射するかの予測ができるようになります。
入射角の性質を理解すると、鏡を作るときの角度決定、プラスチック板の屈折実験、光ファイバの通信設計など、身の回りの技術に役立つ考え方が身についてきます。
入射角とは
入射角は境界に接した場所で、入ってくる光線と境界に垂直な法線との間に作られる角度です。
法線とは境界に対して直角に引かれる想像の線のことです。
入射角が小さければ光は境界を斜めに越えて屈折しますが、角度が大きくなると光の一部が境界で反射されます。
日常の例として水面に落ちる棒が見え方を変えるのは入射角が関係しているためです。
また、光が水中から空気中へ出ると、見かけの角度が変わる現象も同じ原理です。
臨界角とは
臨界角は光が高い屈折率の媒質から低い屈折率の媒質へ移るとき、屈折光が境界をちょうど90度で出るときの入射角のことです。
たとえば水から空気へ光が進む場合、臨界角より大きい入射角になると全反射が起こり、境界を越えて出ていく光はなくなります。
この現象は水中で光が泳ぐように見える演出や、光ファイバの芯で光を閉じ込める基礎になります。
臨界角は媒質の性質に左右され、nが高いほど臨界角は小さくなります。
違いと実用例
入射角と臨界角の違いを理解するには、まず前述の法則を思い出しましょう。
入射角は光が境界に入る角度、臨界角は光が境界を越えるときの閾値の角度という意味です。
臨界角以上の入射角では全反射が起こり、境界を越えず光が戻ってくる特徴があります。
この性質を活かすのが光ファイバ通信や潜在的なセンサー設計です。もし水槽の端から光を送るとき、どの角度で送ると最も効率よく信号が伝わるかを考えるのは、臨界角と入射角の違いを理解しているからこそ可能です。
家の窓際で太陽光をどう集めるか、鏡を設置して部屋を明るくするなど、日常の工夫にもつながります。
まとめとして、光の道筋を決めるのは角度と媒質の性質です。
日常生活の中にも、反射の美しさや光をつなぐ仕組みのヒントがたくさん潜んでいます。
この学習を通して、なぜ水の中の棒が曲がって見えるのか、どうしてティッシュの光が屈折して見えるのかといった身近な現象にも答えが見えてきます。
臨界角について、ただの用語の説明だけで終わらせず、友人と雑談するような雰囲気で深掘りします。境界で起きる全反射の話題を持ち出すと、学校の理科の授業だけでなく、スマホのカメラレンズの工夫やガラスの窓から入る光の見え方にもつながることに気づきます。臨界角を意識すると、私たちが見る世界の光の道筋が少しずつ変わり、身の回りの装置や自然現象の仕組みをもっと楽しく理解できます。
前の記事: « 回帰反射と拡散反射の違いを徹底解説!中学生にもわかる光の秘密





















