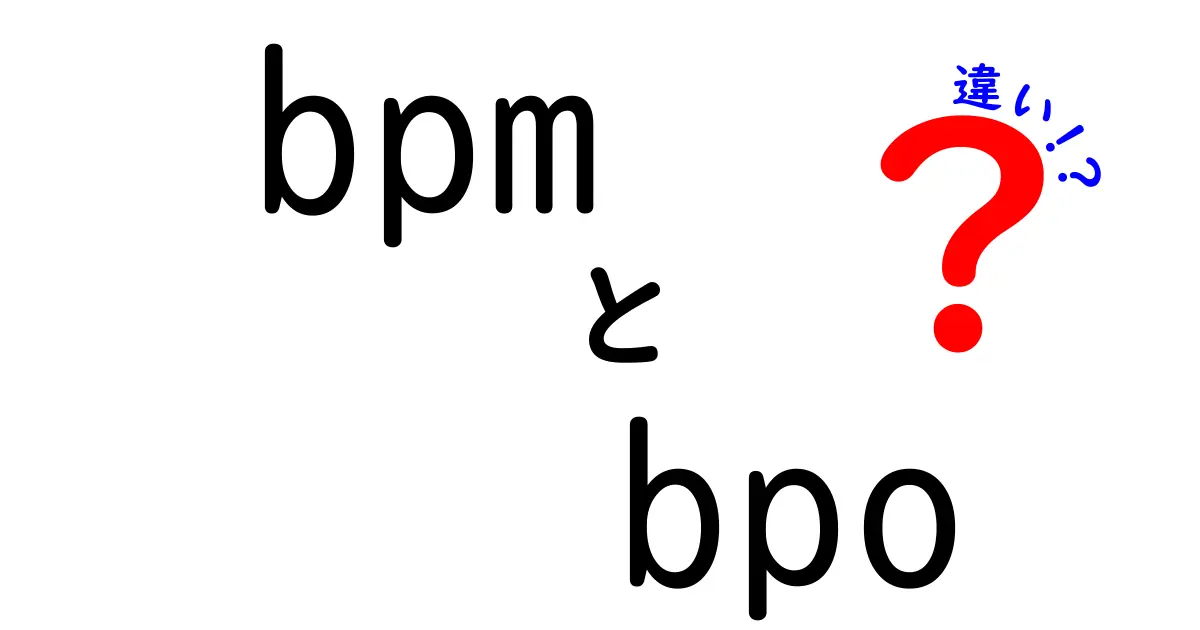

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
bpmとbpoの違いを徹底的に理解するための基本ガイド
ビジネスの世界にはよく出てくる言葉がいくつかありますがその中でもBPMとBPOはよく混同されがちです。ここではまずBPMが何を指すのか、続いてBPOがどういう場面で使われるのかを、日常の例えを使って分かりやすく説明します。BPMは企業の仕事のやり方を設計し改善するための考え方や手法を指します。つまり作業の流れを見つけ出し無駄をなくすための設計図のようなものです。これに対してBPOはその設計された作業を外部の専門業者に任せることを意味します。自分たちの強みは別の仕事に集中しつつも必要な作業だけを外部へ委託する仕組みです。この二つは似ているようで役割が違います。例えば学校の文化祭での準備を考えると分かりやすいです。学校側が全体の計画を立てて各クラスに役割分担を指示するのがBPMのイメージです。
一方その計画の一部を外部の業者に任せる決定をするとします。ポスター作成や印刷など専門の会社に任せて自分たちは他の準備に集中します。これがBPOの考え方に近いです。つまりBPMは“どう動くかの設計図”でありBPOは“実際の作業を任せる相手”です。ここを混同すると予算の使い方や責任の所在があいまいになりやすくなります。よくある誤解として、BPMがBPOを必ず必要とすると捉える人がいますが実際には両者は連携して初めて効果を発揮します。
この章の要点をまとめると、BPMは組織の作業の流れを設計・改善する枠組みであり、BPOはその設計された作業を外部に任せる選択肢の一つです。両方を上手に組み合わせると効率だけでなく品質の安定やコスト削減にもつながります。これを理解すると企業の運営の仕組みが少し見えやすくなります。
次の章ではそれぞれの意味と現場での具体的な使い方を詳しく見ていきます。
BPMの意味と現場での使われ方
ビジネスプロセスを「どう進めるか」という考え方がBPMの核心です。日常の例で言えば、学校行事の準備を前もって計画するようなイメージです。まず現状の作業を把握し、どこに無駄があるのかを整理します。次にその作業をどう組み替えると効率が上がるかを設計します。このときルールや手順書を作り、誰が何をするのかをはっきり決めます。ここで大切なのは「改善を続ける姿勢」です。BPMは一回やったら終わりではなく、定期的に見直すことで初めて意味を持ちます。
現場での実践例としては、学校の給食の献立作成や日常の授業の準備、部活動のスケジュール管理などが挙げられます。これらはすべて「作業の流れをどう組み立てるか」という問いに答えるものです。適切な指標を設定して評価を行い、成果を数字で追うこともBPMの特徴です。指標を決めると作業が見える化され、改善の方向がはっきりします。
このようにBPMは現場の実務と直結します。目標を決め、現状を分析し、手順を整え、結果を測定する循環を作るのが基本です。組織全体を見渡せば、BPMの考え方は人材の配置、設備の使い方、情報の流れといったさまざまな要素に影響します。難しく考えず、まずは日常の作業で「何をどの順番で誰がやるのか」を紙に書き出してみるのが第一歩です。
こうした試みを積み重ねると、無駄が減り、時間とコストの両方を節約できます。
BPOの意味と利用され方
一方のBPOは「業務プロセスを外部へ委託する」という考え方です。ここで大事なのは“何を外部に任せるのか”をはっきり決めることです。例えば大量のデータ入力作業や、専門的な技術を要する設計作業、定期的なバックオフィス業務などを外部の専門業者へ任せると、内部の人はより価値の高い仕事に集中できます。BPOの魅力はコストの削減だけでなく、最新の専門知識や最新のツールを活用できる点にもあります。急速に変わる市場環境の中で、内部リソースを柔軟に拡張する手段として活用されます。
ただしBPOを選ぶときにはいくつかのポイントがあります。委託先の信頼性、作業の品質管理、機密情報の扱い、連携時のコミュニケーションの方法などを事前に取り決めておくことが重要です。BPMとBPOを組み合わせて使うと、設計と実行の双方をしっかりコントロールできます。つまりBPMで業務の道筋を決め、BPOでその道筋に沿った作業を外部へ委託するという組み合わせが最も効果的になる場合が多いのです。
比較表と実践的な使い分け
以下の表はBPMとBPOの違いを視覚的に理解するためのものです。
このように
ある日友だちと勉強会をしていたときの話。先生がBPMとBPOの違いをどう説明してくれたか、私のメモを読み返していると、作業の設計と実際の作業の外部委託という二つの役割がはっきり分かれていることに気づきました。BPMは地図のような設計図で、BPOはその地図に沿って動く道の案内役です。もし地図だけあっても道案内がなければ目的地には到達しません。だから両方を組み合わせることが大切だと思います。





















