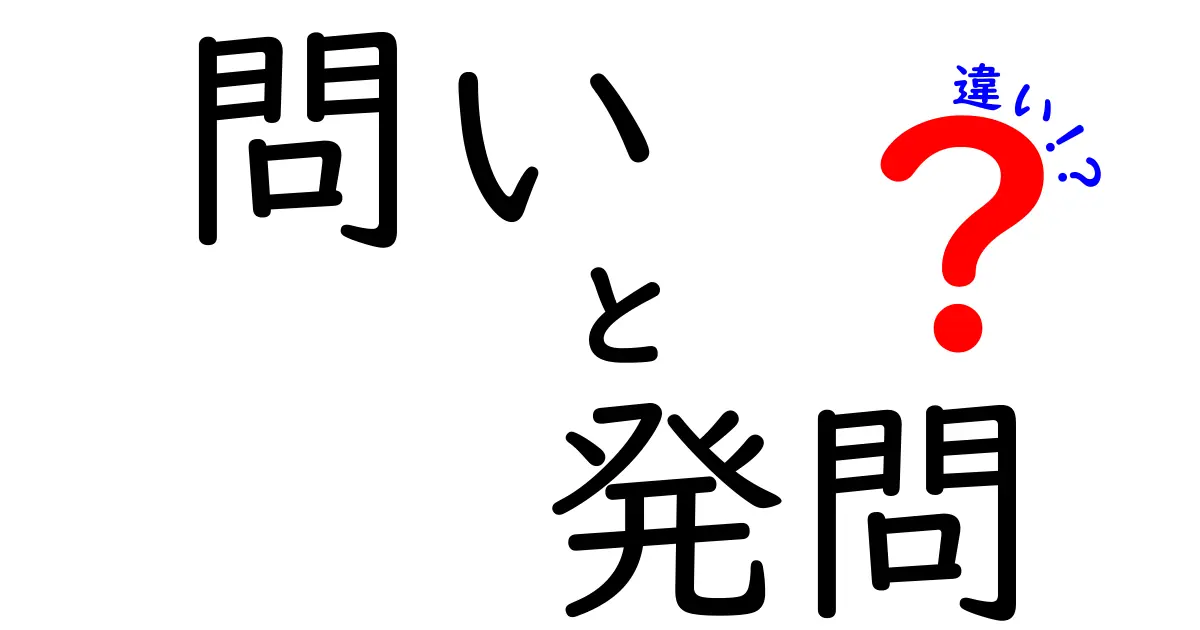

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
問いの基本と使い方
問いは日常の会話から学びの場まで広く使われる基本的な道具です。問いには「情報を求める」目的と「理解を深める」目的の2系統があり、使い分けることで話の深さが変わります。学校の授業で先生が出す問いは生徒の思考を動かすきっかけです。事実を確認する問いと価値観や意見を引き出す問いの2つに分けて考えると、準備が楽になります。ここで大切なのは受け手の現在の知識量や経験に合わせて問いの難易度を調整することです。例えば実験の結果を尋ねるときは具体的で短い問いにしますが、生活や社会の意味を問うときは抽象性を少し取り入れて考えを広げてもらいます。
問いを上手に活用するコツは三つあります。第一に目的をはっきりさせること。第二に答えの幅を想定して聞くこと。第三に相手を否定せずに聴く姿勢を保つことです。
重要なポイントは問いの形を選ぶとき相手の知識量と関心を考慮することです。初心者には具体的で短く、上級者には抽象的な問いを用意するのがよいでしょう。
日常の会話にも応用できます。家族や友人との会話で問いと発問のニュアンスを意識するだけで、話の展開が変わることを体感できるでしょう。
日常の会話にも応用できます。家族や友人との会話で問いと発問のニュアンスを意識するだけで、話の展開が変わることを体感できるでしょう。
発問の役割と違い
発問は授業や研修の場でよく使われる言葉です。問いと比較すると発問は思考の過程を引き出しやすくする設計が特徴です。発問は教師やリーダーが生徒や部下に対して思考の道筋を可視化させる意図で投げかけます。例えば新しい概念を導入する際にはこの公式はどんな場面で使えますかといった発問を用意します。生徒は答えを急がされず、まず自分の理解の穴を認識し、次に説明のどこが難しいかを考えます。
このプロセスは対話の流れを作り出し、グループディスカッションの活性化にもつながります。
ただし発問が難しすぎると逆効果になることもあるため、適切な難易度の調整が必要です。
ポイントは発問を選ぶ際に授業の進度と生徒の反応を見極めることです。発問は答えの形を決めすぎず、思考を広げる導線として使うのが基本です。
実生活の中でも発問の考え方は役立ちます。会議やグループ作業で発問を使えば、参加者の視点が広がり、新しいアイデアが自然と生まれやすくなります。適切な発問は人と人の理解を深め、協力や創造性を高める力があります。
今日は発問について友だちと雑談風に深掘りしてみた。発問はただの質問ではなく、相手の考えの道筋をそっと照らすライトのようなものだ。最初に自分の考えを一言述べてみると、友だちはどこが引っかかったのかを具体的に返してくれる。すると自分の思考が整理され、次の発問へと自然に動く。発問の妙は答えそのものよりも、答えへ至る過程を共有できる点にある。だから勉強でも会話でも発問を大事にすると、相手の理解が深まると同時に自分も新しい発想を得やすくなる。





















