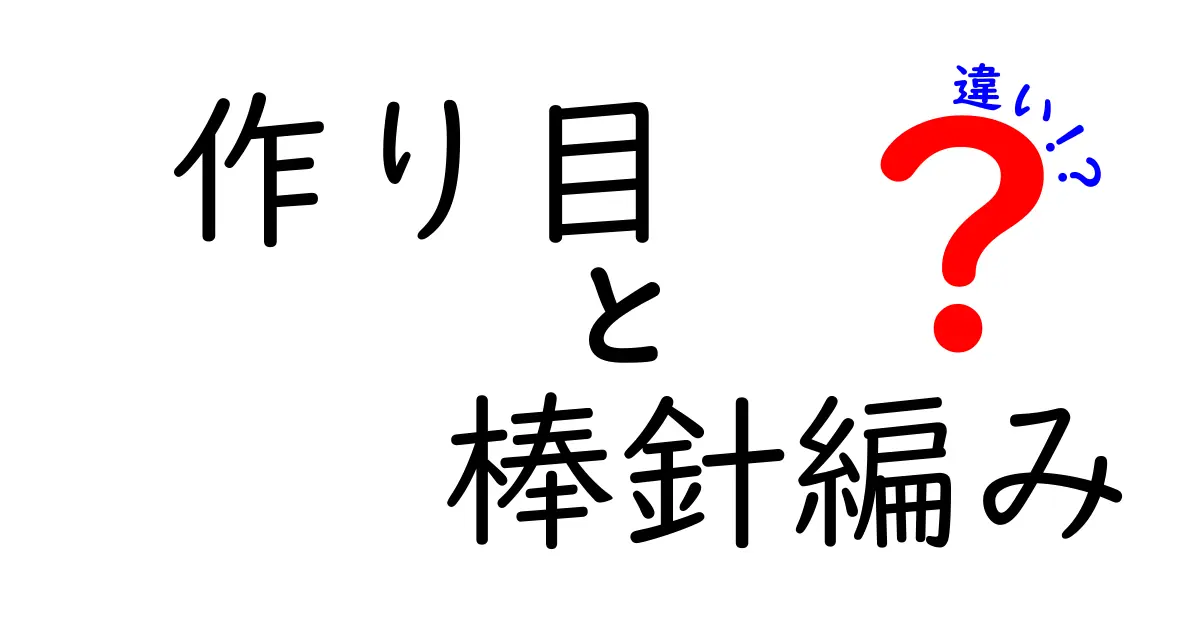

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
作り目と棒針編みの違いを徹底解説
作り目と棒針編みの違いは、手芸を始めるときに最初に出会う基本的な区別です。作り目は布の最初のループを作る作業で、棒針編みは糸を使って編み目を作っていく技法全体を指します。つまり、作り目は棒針編みを始めるための第一歩、布を作るための土台を作る行為です。作り目がなければ、編み地は落ちてしまい、作品は形を保つことが難しくなります。一方、棒針編みは糸の引っ張り方、針の動かし方、編み目の作り方、そして最終的な布の伸縮性を決める技術全体を含みます。作り目は練習用の小さなサンプルで試すことが多く、棒針編みはスカーフやセーターのような長さのある作品を作る際に実際に用いられます。
この二つは別々の概念ですが、相互に補完的であり、初心者がつまずきやすいポイントとしてよく混同されます。作り目の数量と棒針編みの目数を数える習慣は、作品のサイズを決めるうえで重要です。
作り目にはいくつかの方法がありますが、代表的な「長尾作り目」は糸の長さとテンションを自分で調整できるメリットがあり、輪針を使う場合でも同様の考え方が適用されます。ポイントは糸の始まりの結び目と最初のループの作り方、そしてそのループを次の段につなぐ際のテンションです。テンションが緩すぎたりきつすぎたりすると、縦方向の伸縮性が崩れ、作品の見た目が均一でなくなることがあります。さらに、作り目の方法にはそれぞれ利点と欠点があり、選択は作品の目的、糸の種類、針の太さ、そして自分の編み方の癖によって変わります。これからの章で作り目の基礎を具体的に見ていき、どうやって自分に合う方法を見つけるかを解説します。
作り目とは何か?基本のイメージと始め方
作り目は、針と糸で布の土台となるリングを作る最初の工程です。具体的には、まず糸を指で分け、結び目を作ってから、輪になった糸のループをひとつずつ引き上げて針にかける作業を繰り返します。長尾作り目と通常の作り目の違いには、糸の長さの取り方、手の動かし方、指の動きのコツなどがあり、初心者は最初の数十目で手首の負担や緊張感を感じさせますが、練習を重ねると自然になります。作り目は布全体の縦の伸縮性を左右する要素であり、最初の結び目がしっかりと締まっていると、作品の端がきれいになり、逆に緩すぎるとギャザー状になって見た目が崩れてしまいます。ここで重要なのは、作り目を作るときの糸のテンションと、最初のループを作った後の針の角度です。作り目を始める前に、糸の長さを決め、作業台の高さを調整し、鏡などで手の動きを確認すると良いでしょう。さらに、初心者には写真付きの手順を見ながら練習することをおすすめします。作り目の基本を身に付ければ、編み始めの最初の一歩でつまずくことは減り、以降の段の編み方を習得するのが格段に楽になります。
棒針編みの基本と道具選び
棒針編みは、糸を編み目として針の上でつなげていく技術の総称です。基本の動作は、針を持って糸を引き上げ、次の目を作る、という単純な反復作業の積み重ねの連続です。道具選びは作品の仕上がりに大きく影響します。まず針の太さは、糸の太さとテンションに合うものを選ぶことが大切です。細すぎる針は指に負担をかけ、太すぎると編み地が緩くなりすぎます。糸の種類には天然素材と合成素材があり、天然素材の糸は温かみがあり、混紡糸は耐久性と伸縮性のバランスをとってくれます。テンションを一定に保つコツは、針の持ち方と手首の動きを小さく保つこと、力を指先だけでこむことが多いのを意識することです。棒針編みの基本には、最初の作り目の目数を正確に揃え、次の段へと移るときの編み方を統一することが挙げられます。最初のうちは同じ目数でも、布の張りが違うと見た目の印象が変わるので、毎回編み地を触って確認する癖をつけると良いでしょう。もちろん、慣れてくると段の増減や模様編みに挑戦することができます。練習のコツは、一定のテンポを保ち、指の動きを覚えること、そして編み地の端を揃える意識を持つことです。これにより、作品全体の美しさや着心地が向上します。
実際の作品での使い分けと練習のコツ
作り目と棒針編みの違いを日常の作品に落とし込むには、練習計画を立てることが効果的です。最初の週は、作り目の練習と小さなサンプルを作ることに集中します。例えば、長尾作り目で十段程度のサンプルを作り、次に基本の編み方で十段ほど編んでみると、糸のテンションの変化が作品にどう現れるかを体感できます。完成を急がず、手の動きを体に染みつかせることが重要です。作り目は後で布の縁を揃える時にも役立つので、縁の美しさを意識して練習しましょう。棒針編みの基本は、作り目を終えた後の第一段で、鎖状の目が均一に揃っているかを確認することです。ここで不揃いがあれば、次の段にも影響を及ぼします。練習メニューとしては、同じ目数のサンプルを複数回編んで、糸の引っ張り方を一定に保つ訓練をすると良いです。作品を作るときには、作り目の数と編む目数を事前に計算しておくと、予定通りのサイズに仕上げやすくなります。設計図を読み解く力も大切で、寸法、ゆとり、伸縮性のバランスを頭の中で描くようにしましょう。
最後に、失敗しても気にしない心構えが大切です。初心者は必ずつまずく工程があり、そこで学ぶことが多いです。コツコツ続けていけば、作り目の美しさと棒針編みの技術が同時に成長します。
友だちと雑談していると、作り目と棒針編みの違いは“入口と進行の関係”のように感じられることが多いです。作り目は布の始まりの点、最初のループを作る瞬間の緊張感で、ここがうまくいくと次の段へ進む気持ちが自然と湧いてきます。棒針編みはその先の道のりであり、糸の動き、手首の角度、指の位置、針と糸の協調が問われます。雑談の中で私はよく「作り目は靴の前の紐通しみたいなもの」と比喩します。紐をきつすぎず緩すぎず結び目を安定させれば、履き心地が良くなる。棒針編みは紐を通した後に布を編んでいく作業で、練習を重ねるごとに手の動きが滑らかになります。もし友だちが最初の作り目で戸惑っていたら、私なら長尾作り目の動画を一緒に見て、糸の角度とテンションの感覚を体で覚えるまで一緒にやってみることを提案します。編み物は一人で完結する技術ではなく、同じ目標を共有する仲間がいると続けやすい趣味です。





















