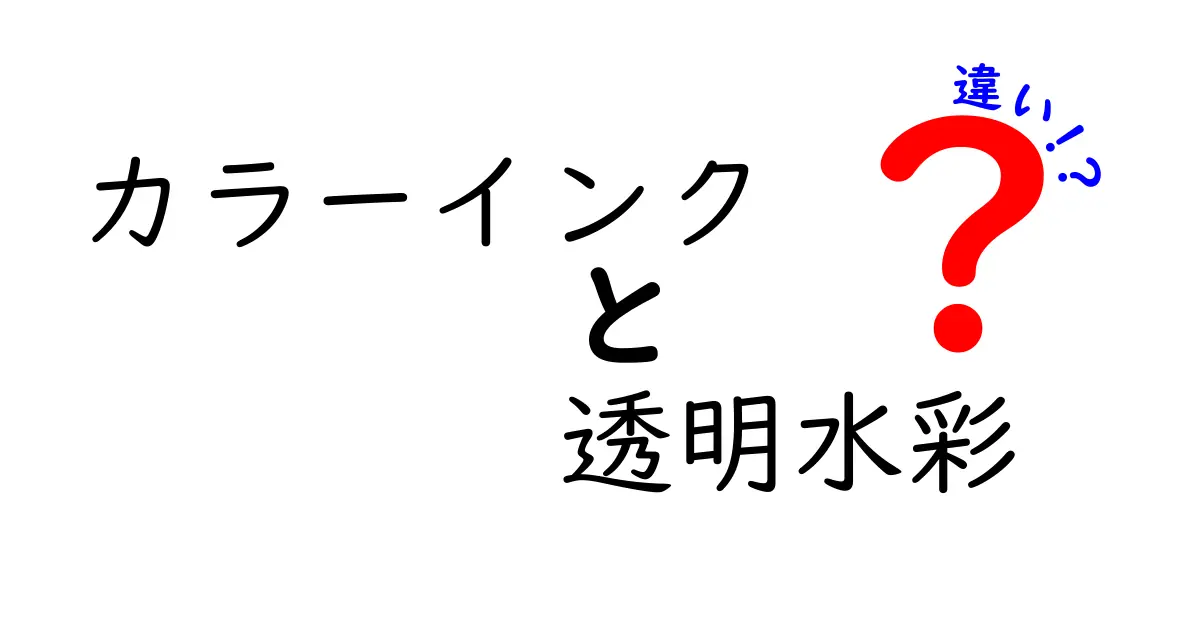

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
カラーインクと透明水彩の違いを知ろう
この二つの違いを知れば、絵を描くときの道具の選び方が格段に変わります。カラーインクは主に染料ベースの液体で、紙の上に描くと発色がとても鮮やかで、薄く重ねると色の深みが増します。しかしにじみや擦れ、紙の種類によって見え方が大きく変わるのも特徴です。透明水彩は水を使って色を薄く伸ばし、紙の白さを生かした透け感を表現するのが得意です。水の量を調整することで、同じ色でも透明感と影の濃さを自由に表現できます。発色はカラーインクほど刺さる感じではなく、柔らかく馴染む印象になることが多いです。カラーインクは光の当たり方によってキラリと目立つ色味を作り出しやすく、透明水彩は自然光の下で穏やかな表現を作るのに向いています。色を混ぜるときの挙動も違い、カラーインクは紙の表面で混ざり、透明水彩は紙の吸い込みと水分の動きによって混色の境界がぼかされます。これらの性質を把握することで、作品の雰囲気を狙いやすくなります。
初めて使うときは、色見本を作り、薄い色を何度も重ねて色の変化を観察すると良いでしょう。文字だけの説明よりも、実際に筆やペンを動かして体で覚える方法が、理解を深める近道です。
使い分けのポイントと描き方のコツ
次の段では、実際の使い分けの場面を想定して、どう選ぶか、どんな表現に向くかを具体的に見ていきます。風景画の広い空、城下町の石畳の陰影、人物の衣服の質感など、場面ごとに適した選択が変わります。風景には透明水彩の薄い層と自然な濃淡が活き、色の透明感が建物の質感を際立たせます。一方、日常のスケッチやポスター風の明るい表現にはカラーインクの強い発色とクリーンなラインが役立ちます。表現の強弱をつけるには、まずは2色だけで練習し、次に3色、4色へと段階的に増やしていくと頭の中での混色の組み立てが分かりやすくなります。さらに紙の種類(ホワイト、紙質のざらつき)によっても色の出方は変わるため、手元にある複数の紙で試すのが理想的です。カラーインクは黒や深い色を使うときに、紙の吸収率によってはにじみが強く出ることがあります。透明水彩は乾燥後に水を足して再度重ねづけをすると、色の深みを自然に増すことが可能です。この性質を活かして、時間をかけた階調表現を楽しむのもおすすめです。
具体的な練習法としては、同じ色を2段階の明度で塗り分け、境界をぼかす練習、そして30分程度の短い題材で色のにじみ方を観察する練習が有効です。練習の終わりには、作品の中で使った色を一覧にして、次回はどの色を濃く、どの色を薄く使うと雰囲気が変わるかをチェックすると良いでしょう。最終的には、自分の作品の意図に合わせて、カラーインクと透明水彩を組み合わせるハイブリッド表現にも挑戦してみてください。
友達と絵を描くときの雑談トークを再現する小ネタ記事です。
ねえ、カラーインクと透明水彩、同じ色を使ってもなんでこんなに印象が違うか知ってる?カラーインクは紙の上で色が“強く出る”感じがあるんだ。濃い緑を一 layer 置くだけで、すぐ目立つ。透明水彩は水を多く使えば薄く透けていくから、背景の空や遠景の霞み具合を自然に表現できる。だから同じ緑でも、森林の葉っぱを描くときには透明水彩を多用して透明感を出し、樹木の幹や影を強く描くときにはカラーインクの濃淡を使い分けるのがコツになる。最近はこの2つを組み合わせて、前景をカラーインクでシャープに、背景を透明水彩で柔らかく描く作品が流行りつつある。ちょっとしたコツとして、まず薄い色を何度も重ねる練習をし、次に濃い色を一点だけ強調してみると、全体のバランスが取りやすくなる。結局のところ、似た色でも塗り方ひとつで全く違う雰囲気になるから、いろいろ試して自分の“癖”を見つけるのが一番の近道だと思うよ。
前の記事: « 画用紙と色紙の違いを徹底解説!用途別の選び方と買い方ガイド
次の記事: 背景布と背景紙の違いを徹底解説!写真撮影の基本をマスターしよう »





















