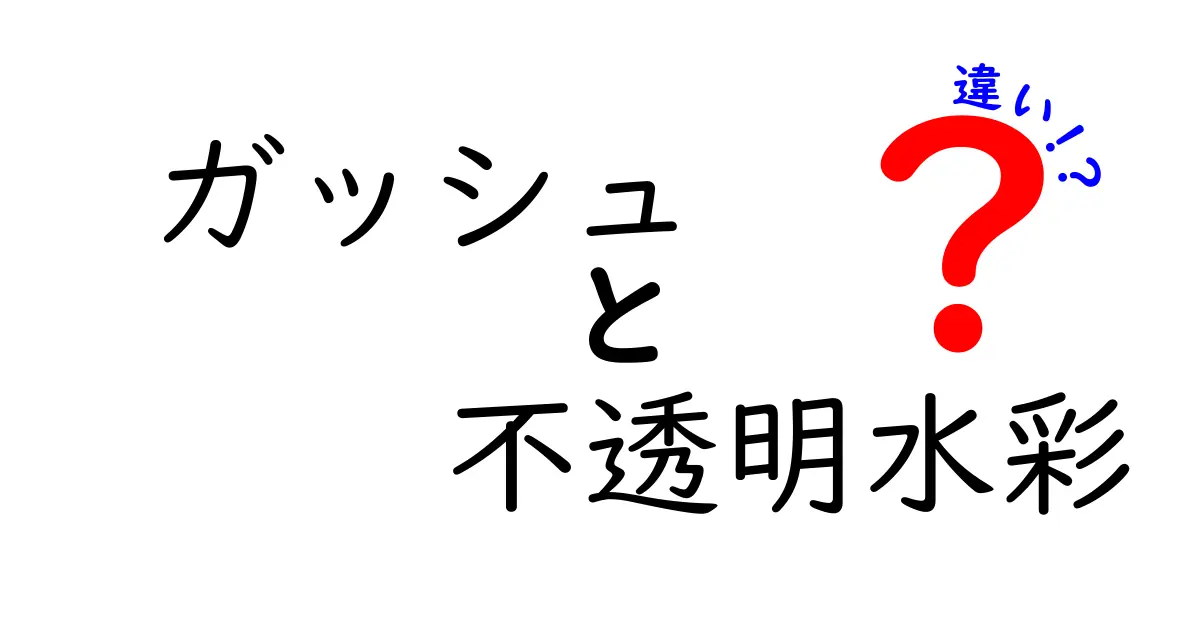

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ガッシュと不透明水彩の基本的な違い
ガッシュとは主に不透明水彩のことを指しますが、一般的には「gouache」と呼ばれ、絵具の中に白色の顔料が含まれていることが特徴です。白色の成分が紙の色を隠して作品全体を不透明にするため、一度塗った色をあとから上から重ねても下の色が透けにくくなります。
一方で不透明水彩ではなく普通の水彩は透明で、紙の白さを元の色として使うため、重ね塗りをすると下の白い紙が透けやすくなります。
この違いは実際の塗り方にも影響します。ガッシュは厚みのある筆致を出しやすく、筆跡を隠したい部分には強い塗りが必要です。紙の吸収を意識して、薄く塗らずに何度も乾かしながら塗ることが多いです。
また、ガッシュは「不透明さ」を出すためにチョーク状の白色顔料を含むことが多く、これが表現の幅を広げます。とはいえ注意点もあります。紙の種類や水分量によっては乾燥後に表面がざらつくことがあり、しっかりとした仕上げを求める場合は下地作りや紙選びが重要になります。
ガッシュの特徴と使い方のコツ
ガッシュの特性を理解すると、作品作りの幅が広がります。発色の濃さと不透明さを活かすには、まず紙の選択が大事です。水彩紙の中でも厚手で目の細かいものを選ぶと、白色顔料が均等に広がりやすく、乾燥後の白のコントラストがくっきりします。
次に道具の選び方です。ガッシュには粘度が高めの絵具と、柔らかい粒子感のものがあります。筆の種類は、広い面を塗る場合は大きめの筆を使い、細部を描くときは細い筆でコントロールします。筆圧を弱くすると色が薄く乗り、強く押すと濃い色になります。
表現のコツとして、先に暗い部分を塗るベースを作っておくと、後からの修正が効きやすいです。ガッシュは乾燥後でも水を含ませると再び柔らかくなる性質があり、ハイライトを後から追加する際に便利です。さらに、マットな仕上がりを好む人は仕上げに薄く全体を塗ると均一な質感になります。
実践例としては、風景画で空をガッシュで塗りつつ、木の枝などは水彩の透明感を残して重ねると、立体感と透明感のバランスが取れます。
不透明水彩の使い方と注意点
不透明水彩は紙の白を生かすのではなく、色そのものの不透明さで表現します。白を含む色の厚塗りが特徴で、色の塗り重ねが可能です。
水分量の管理が大切です。水を多く使いすぎると、色が薄まりすぎて不透明さが損なわれてしまうことがあります。適度な水分量を保ち、乾燥を待つことが基本です。紙は厚手の画用紙か水彩紙が適しています。
重ね塗りは、上から別の色を重ねても下の色が透けることもありますが、計画的に行えば劇的なコントラストを作れます。強調したい部分には白を直接混ぜず、明るい部分を残す工夫も有効です。
塗る順番としては、まず基本色を薄く敷き、徐々に暗い部分を追加します。白を活かしたい場合は別の白系の顔料を用意して、後からリフレッシュする感覚で整えると良いでしょう。
まとめと選び方のヒント
使い分けの基本は目的と仕上がりの好みにあります。繊細な透明感を活かしたいなら透明水彩、色の不透明さと強さを活かしたいならガッシュを選ぶのが近道です。
初心者は両方を少しずつ試して、紙の違いにも慣れることが大切です。例えば同じモチーフを紙に対して別々の材質で描くと、どんな雰囲気になるか比較できます。
作品のタイプが風景なら透明水彩の方が白の力を引き出しやすく、ポートレートならガッシュの不透明さが影を作るのに向いています。
色相の把握や色の混ぜ方の基本を身につけるには、カラーサークルを使って補色の効果を確かめると良いです。
最後に、道具の基本セットとして、品質の高い水彩紙と、適切な筆、そして練習用の小さなスケッチブックを用意すると、学習の効率がぐんと上がります。これらを揃えれば、描きたいモチーフを自由に表現できるようになるでしょう。
ねえ、ガッシュと不透明水彩の違いについて友達と雑談していた時の話なんだけど、私たちは最初、色が濃く出ればいいと思ってガッシュばかりを勧めていた。でも実際には透明感を大切にしたい場面も多い。そこで透明水彩の透明度と水分量の関係を実演してみると、同じ色を塗っても見える風景が違う。紙の白が生きるときは透明水彩、白を塗りつぶして色を際立たせたいときはガッシュ、という結論に落ち着いた。道具は使い分けが正解で、両方を持っておくと絵の幅がぐっと広がるんだ。
次の記事: 積み重ねると重ねるの違いを徹底解説|意味と使い方のポイント »





















