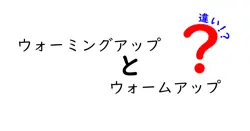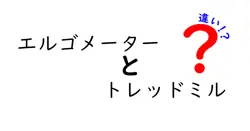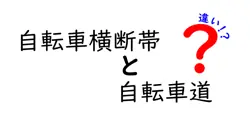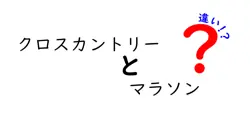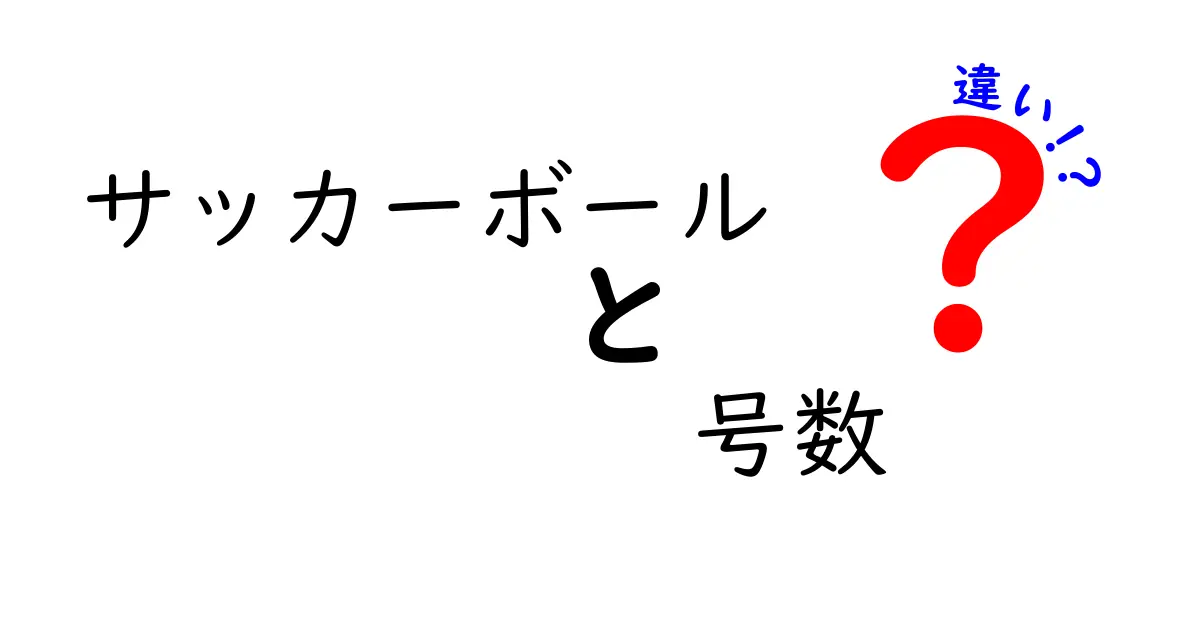

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
サッカーボールの号数違いを知ろう
サッカーボールの号数(サイズ)は、球の周囲の長さと重さで決まる規格のことです。いわゆる5号球、4号球、3号球といった呼び方は、プレーヤーの年齢や技術レベル、競技の場面に合わせて使われます。サイズが違うと、転がり方や蹴り心地、パンチの伝わり方が変わるため、練習の段階や試合の条件に合わせて選ぶことが大切です。
まず覚えておきたいのは、数字が大きいほどボールは大きく重くなるということです。一般的な規格として、サイズ5は周囲約68〜70センチ、重さは約410〜450グラム、サイズ4は周囲約63.5〜66センチ、重さ約350〜390グラム、サイズ3は周囲約58〜60センチ、重さ約300〜320グラムです。
この規格は公式戦にも適用される標準ですが、練習用には小さめのボールを使うことがあります。初心者の子どもには小さいサイズを使うと握る力や蹴るときの感覚がつかみやすく、成長に合わせて段階的に大きさを変えるのが効果的です。逆に、身長が高く技術がある人が小さなボールで練習しても、実際の試合での感覚とのズレが生じてしまうこともあるため、段階的な移行を意識しましょう。
なお、ボールを選ぶ際には「室内用」「室外用」「人工芝用」など、表面の材質や縫い方も重要です。室内用は通常サイズ5が多いですが、室内での蹴り心地や耐久性を考えて別の選択をすることもあります。
また、ボールは空気圧が大切です。あまり高く膨らみすぎると跳ねすぎてコントロールを失い、低すぎるとボールの転がりが悪くなるため、製品パッケージの推奨空気圧を守ることが重要です。
号数別の使い分けとポイント
次に、年齢別・目的別の使い分けのコツを見ていきましょう。幼児〜小学生低学年のうちはサイズ3もしくは4を選ぶことが多いです。理由は、手のひらの力でボールの反発を感じ取りやすく、蹴るときの面の使い方を身につけやすいからです。
小学生の中盤〜中学年になると、身長も伸び、蹴り足の正しいフォームを習得するためにサイズ4から5へ移行するタイミングを見極めます。
中学生以上で身長が高い人や競技経験がある人は、公式戦に合わせてサイズ5を基本に使うのが一般的です。公式戦でのボールの感触は、ドリブルの安定性、シュートの正確性、パスの距離感に直結します。練習では、サイズを段階的に切り替えながら、体の大きさとテクニックの成長に合わせて感覚を整えると良いでしょう。
また、シーン別の使い分けも覚えておくと便利です。屋外のタフな芝生や人工芝では耐久性が高いボールを選ぶ、室内の硬めの床では跳ねすぎないボールを選ぶなど、球質の差がプレーの安定性に影響します。ボールの選び方は道具の善し悪しだけでなく、練習の質にも直結します。
最後に、購入時のポイントとしては、ボールの縫い目の組み方(パンチングか合成皮革か)や縫い目の有無、耐久性、空気の保持力をチェックすることです。
表で見る「号数と仕様」
ここでは基本的な情報を表にまとめ、どのサイズを選ぶべきかを直感的に理解できるようにします。まずは、サイズ3・4・5の3つを比べ、年齢の目安、周囲、重さ、用途を比べてみましょう。さらに、ボールを選ぶときに大事なポイントとして、素材の耐久性、縫い方、空気圧の管理方法、室外と室内の使い分けなども解説します。表の数字は一般的な規格値であり、メーカーによって若干の差があります。ボールを実際に手に取るときは、周囲の寸法計測と手触り、蹴り心地を確かめるとよいです。
この表を見ながら、まずはお子さんの年齢と体格を基準にサイズを決め、プレーの感触を確かめてください。
公式戦を視野に入れる場合は、ほぼ確実にサイズ5を使用しますが、練習場面では同じサイズでの反復練習のほか、あえて別サイズを混ぜて使い、コントロールの幅を広げる方法もあります。
また、空気圧は季節や温度で変わるため、試合前に適正値に調整する習慣をつけてください。年齢が低いほど、ボールの感触を手足で体感する練習が重要になるため、無理のないサイズ選びが成長への近道になります。
スポーツショップでサイズ5を見て“公式戦は5号球”とすぐ決めがちですが、実はその場の状況で最適なサイズは変わります。例えば公園の人工芝で友だちと遊ぶなら、4号球のほうがコントロールしやすいことも。5号球は重さと大きさで強いシュートの感覚を作りやすい一方、まだ体が小さい子どもには扱いにくい面もあるのです。キーワードは「体格と練習内容を見ながら段階的に移行すること」。この発想を持っていれば、子どもの成長に合わせて自然と上達の幅が広がります。
次の記事: 仏像と大仏の違いを徹底解説!大きさだけじゃない仏像の魅力 »