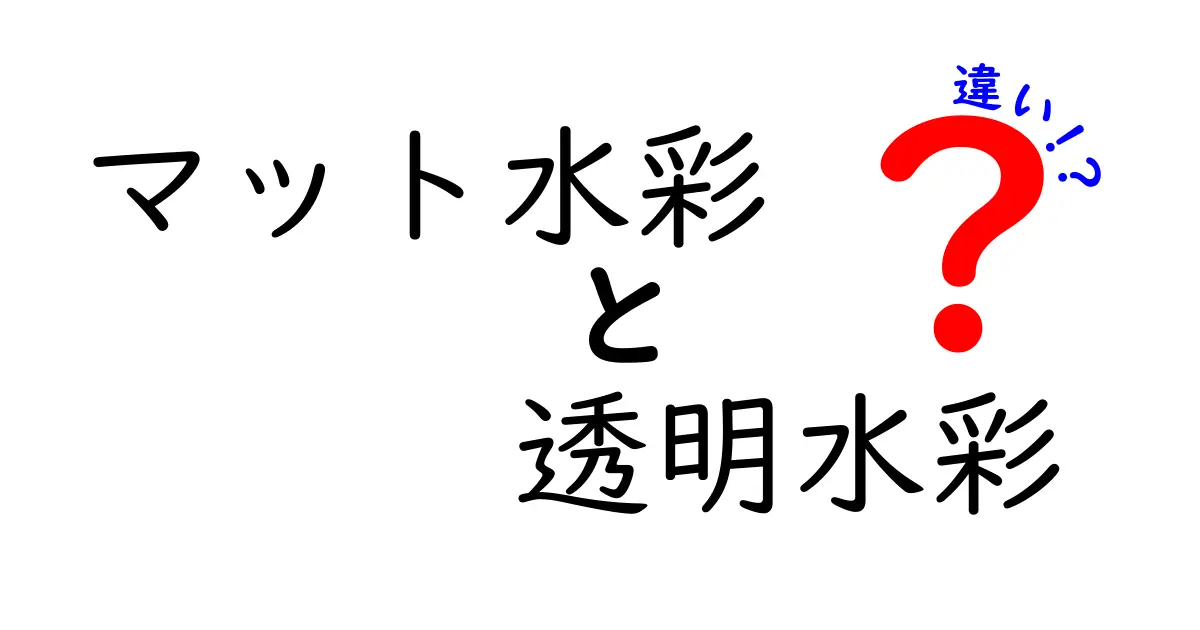

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに
このブログは『マット水彩と透明水彩の違い』をやさしく解説します。マット水彩は紙の表面をざらつかせ、光を反射しにくい質感が魅力で、塗膜がやや不透明になることが多いのが特徴です。一方、透明水彩は光を透過させ、下地の白を生かした透き通る色合いを作り出します。紙の繊維に色が染み込み、上に重ねるほど深みが増すことが多いのも透明水彩の魅力です。実際の画材選びは、描き方や仕上がりの好みによって変わります。この記事では、初心者の方が混乱しやすい点を整理し、どちらを選ぶべきか、どう使い分けるかを具体的な例とともに紹介します。
まず結論を先に伝えると、風景画や細い線を重ねたい場合は透明水彩、表現を柔らかくしたい場合やマットな質感を出したい場合はマット水彩が向いています。ポイントは“紙の表情をどう活かすか”と“水の使い方”です。読み進めるときは、あなたの描き方に近いケースを探してみてください。
この違いを知ると、絵の道具選びが楽しくなります。
マット水彩と透明水彩の基本的な違い
ここからは、実際の描き方に直結する基本の違いを整理します。色の透明度、乾燥の仕方、紙への定着といった点を、写真や絵の例を想定して具体的にイメージできるように説明します。
まず大切なのは、色が「どれだけ隠れるか」ではなく「どのように透けるか」という考え方です。マット水彩は紙の白さを守りつつ、不透明色を使って重ね塗りを楽しむことが得意です。透明水彩は下地を活かして、薄い色を何度も重ねることで深みを作るのが得意です。
この違いを把握するだけで、描き始めの作業がぐっとスムーズになります。
性質の違い
マット水彩の性質は、色が紙の表面に沈み込みやすく、表面の光沢が抑えられることです。筆で塗ったあとの紙の質感が見えやすく、絵全体に「ざらつき感」が出やすいです。これにより、風景の木の葉や草の繊細な陰影をのりの良さと組み合わせて表現するのに向いています。
また、不透明寄りの発色になることが多く、下地の色を覆い隠す力が強い場面があります。乾燥後は色が落ち着きやすく、強いコントラストを作るのにも向いています。紙の吸い込み方は紙の材質や目の細かさに左右されるため、同じマットでも作品ごとに印象が変わる点も楽しみのひとつです。
透明水彩の性質は、色の透明度が高く、下地の白色を透かして見せる表現が特徴です。乾燥中の水分が紙の上でゆっくり動くため、にじみやぼかしを活かした柔らかな描画が得意です。重ね塗りをする際には、上の色が下の色を透過して混ざるため、色の組み合わせによって意図する観感が得やすいという利点があります。
ただし、薄い色を多く重ねると紙の白が透けすぎて淡く見えることがあるので、適度な濃度管理が必要です。
描き方によっては水の動きを味方につけられる点が魅力で、グラデーションや空の表現、透明感のある水辺の描写などに向いています。
発色と乾燥
発色の差は大きく、マット水彩は「濃く塗ると不透明寄りの色味になる」ことが多いです。透明水彩は水の量を変えることで色の濃さを自在に調整でき、紙の白を背景にして透明感を生かします。
乾燥の挙動にも違いがあり、マット水彩は乾燥後に紙の繊維が色を引き止めるような印象を与え、エッジがやや崩れにくい傾向があります。透明水彩は乾燥の前後で色の境界が柔らかくなることが多く、にじみを活かした表現がしやすいです。
この二つの特性を把握することで、同じ絵でも「どう見せたいか」に合わせて選択肢を増やせます。
使い分けのコツと描き方のヒント
実際の描き方では、道具の選択だけでなく「水の扱い方」が大きな鍵を握ります。水の量と筆圧のコントロールを意識することで、マット水彩は紙の質感を活かした質感表現、透明水彩は透明感と深さを引き出す表現が生まれます。
以下のコツを参考にしてください。まず紙は、目の細かい水彩紙を選ぶと両者の表現が安定します。水を多く使うときは筆を大きく、控えめに塗るときは筆を小さくすることで、塗り重ねのニュアンスが出やすくなります。
次に塗り方の基本として、下地の色を薄く作り、上から厚みを足すのが定番です。マット水彩の場合は、下地の影の輪郭を強めに出すと立体感が出やすいです。透明水彩の場合は、淡いグラデーションを作るときに水を左右対称に動かすと美しい空や水面の表現が作れます。
道具選びとしては、紙の質感を活かしたい場合は表面が粗目の紙、細かい線やシャープな描写を求める場合は滑らかな紙を選ぶと良いでしょう。
実践のための簡易手順を以下にまとめます。最初に薄い色を全体に薄く塗り、乾かします。次に深い色を部分的に重ね、境界をぼかす場合は水を多めに使います。最後に細部を描き込み、必要に応じて再度薄く塗り重ねます。これらの基本を覚えると、透明水彩とマット水彩の双方で自然なグラデーションや質感を表現しやすくなります。
道具と描き方の実践ヒント
最適な道具選びは作品の印象を大きく左右します。紙の質感と塗り方の相性を考慮して選ぶと、失敗が少なくなります。例えば風景画や自然のモチーフには、紙の目が細かいものを選ぶと水が均一に流れやすく、ぼかしが美しく決まります。人物画には、肌の透明感を出すために透明水彩の薄い層を何度も重ねる方法が有効です。道具の基本セットとしては、丸筆と平筆を一本ずつ、濃淡を作るための色数を3~6色程度から始めると迷いが減ります。
また、作品のイメージに合わせてマットと透明のバランスを試す「混色テスト」を事前に行うことをおすすめします。ここで失敗を恐れず、いろいろ試すことが成長につながります。
表で比較
この表を参考に、あなたの作品に最適な材料を選んでください。
最後に、両方の特徴を組み合わせて使うと、より自由な表現が可能になります。
紙と水の関係性を理解することが、絵を上達させる近道です。
まとめと次のステップ
マット水彩と透明水彩には、それぞれ独自の魅力とコツがあります。紙の表情を大切にすること、水の量と筆圧をコントロールすること、そして作品ごとに最適な組み合わせを見つけ出すことが、上手になる近道です。この記事をきっかけに、あなたが描きたいモチーフに合わせて二つの材を使い分ける練習を始めてください。きっと、思い描く色の世界が確実に広がります。
透明水彩を深掘りする小ネタです。友達とカフェで話しているとき、彼は『透明水彩って下地の白をそのまま生かせるから、空の表現が自然で好きだな』と言いました。私は彼に、濃い色を薄く重ねるときの水の動きが重要だと教えました。透明水彩の魅力は“水が絵の筆運びになる”瞬間にあり、薄く塗った青の層が乾くとき、下の色が透けて微妙な暖かさを生むのです。彼は「なるほど、透明感を出すには水の管理が命なんだね」と感心していました。こうした日常のひとコマからも、透明水彩の深さは感じられます。





















