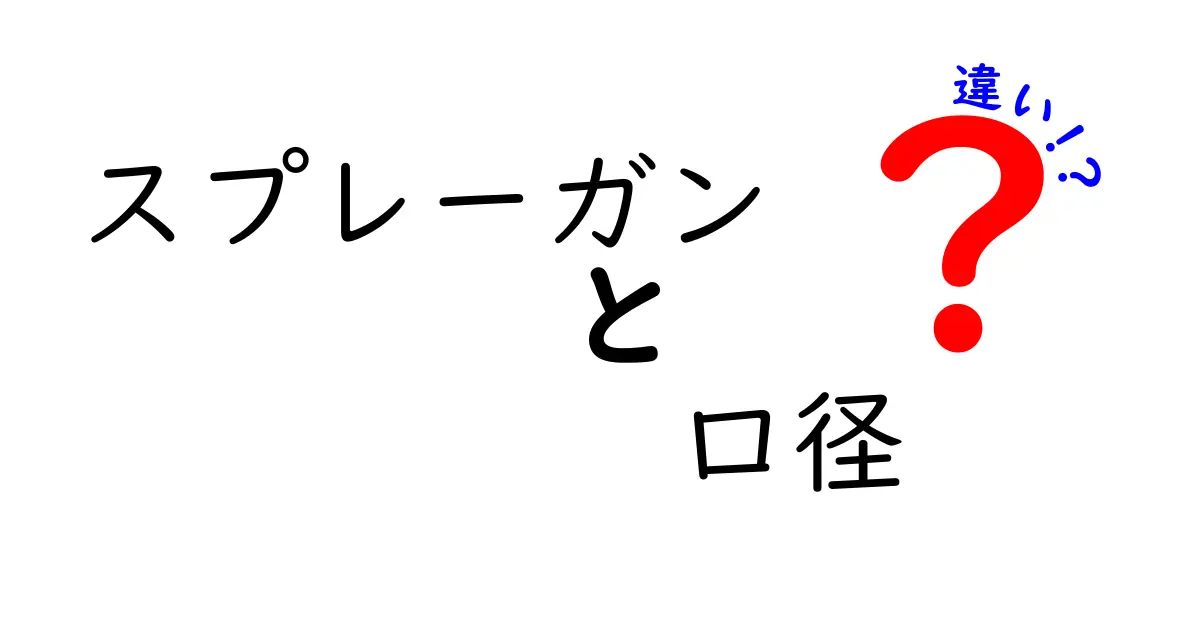

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
スプレーガンの口径の違いと基本ポイント
スプレーガンの口径とはノズルの開口サイズのことを指します。この口径が小さいほど粒子が細かく、広がりは狭くなるのが基本的な特徴です。反対に口径が大きいと粒子は太くなり、広い範囲を一度に塗布できますが、粒子のばらつきや無駄な飛散が増えやすくなります。塗装現場ではこの差を理解して作業を選択することが、見た目の仕上がりや作業効率に大きく影響します。
一般的には口径は0.8mm〜2.0mm程度で表示されることが多く、プリマー用には0.8〜1.2mm、ベースコートには1.0〜1.4mm、クリアコートには1.3〜1.8mmといった目安がよく使われます。ただし車種や塗料の粘度、エア圧の設定、塗装距離によって最適値は変わるため、初めての材料を使う時は必ず小さめから試して徐々に調整していくのが安全です。
口径だけでなく、エア圧( psi など)、距離、粘度、塗装速度などの要素が組み合わさって、理想的な粒子分布とムラの少ない塗膜が生まれます。塗装前には材料データシートを確認し、テストパッチを作って確認する習慣をつけましょう。
口径は通常のスプレーガンだけでなく、HVLP(空気量を抑えて低揚力で塗布する方式)の機材でも重要な要素です。HVLPは低圧で安定した霧を作りやすい反面、口径が合っていないと塗料の供給不足や詰まりの原因になることもあります。ですから、機材の種類に応じた適切な口径の組み合わせを選ぶことが、初動で最も大事なポイントです。
この項目の要点をまとめると、 口径が小さいほど塗膜は細かく均一になりやすいが、広い面積には適さない、口径が大きいほど塗布量は増えるが、ムラやパスが出やすい、塗料の粘度と機材の組み合わせで最適値は変わる、という3つの基本を覚えておくと現場での判断が楽になります。
口径の基本の用語とどう違うか
口径はミリメートルで表記され、1.0mm、1.4mmのように数値が大きくなるほど開口が広くなります。同じ機材でもノズルの交換により適用範囲が変わるため、作業する材料ごとに複数の口径を用意しておくと良いでしょう。塗装の現場では、まず小さめの口径で塗布を始めてから、必要に応じて徐々に大きい口径へ移行する“段階的な適用”を取ることが多いです。これにより、ムラ・流れ・オーバーコートのリスクを抑えながら、表面の仕上がりを安定させることができます。
また、口径だけでなくノズルの形状、塗料の粘度、エア圧の設定、距離の管理も同時に調整する必要があります。これらの要素が上手く噛み合うと、短時間で均一な塗膜を得ることができ、仕上がりの美観にもつながります。
実践での使い分けと注意点
実務での使い分けは、作業の対象材料と面積、そして仕上がりの美観レベルによって決まります。 小口径は細部の表現やライン作業、狭い箇所の塗布に向く一方で、広い面積を均一に塗るには大口径が効率的です。ただし大口径を用いると粒子が太くなるため、滑らかなグラデーションやオーバーコートの抑制を意識する必要があります。塗装の初期段階では、まずテストパッチで最適な口径を探し、次に実際の面で調整していくのが基本の流れです。
具体的な注意点としては、塗料の粘度が高い場合は口径を大きくする前に薄めすぎない、エア圧が低すぎるとムラが出ることがある、距離が近すぎると粒子が崩れて表面がざらつくといった現象が起こりやすい点です。これらの点を避けるには、初動は低速で慣らし、徐々に速度と距離を調整していくと良いでしょう。
さらに現場では、塗装後の仕上がりを長く保つための養生や温度管理、乾燥時間の確保も忘れずに行います。温度が高すぎたり湿度が高い環境では、塗膜が縮んだりひび割れたりすることがあります。適切な養生と換気、適正な乾燥条件を整えることが美しい仕上がりを長持ちさせるコツです。
最後に、道具の定期点検も重要です。ノズルの傷や擦り傷、シール類のゆるみ、エアホースの圧力損失などは、仕上がりに直接影響します。異音やスプレーの均一性が気になる場合は、即座に点検・清掃・部品交換を行い、常にベストな状態で作業できるようにしておきましょう。以上を守れば、口径の違いを理解した上で効率的かつ美しい塗装が実現します。
小ネタ記事の前置き
友人とDIYの話をしているとき、口径の話題で盛り上がりました。友人は“口径は大きいほど良い”と信じていて、思い切って2.0mmのノズルを購入したのですが、一度の塗布で厚すぎて艶が底までのびず、ムラが多発。私は反対に0.8mm前後のノズルをすすめ、薄め具合と距離を調整して徐々に厚さを作る方法を提案しました。結果、同じ材料でも口径と塗り方の組み合わせで仕上がりは大きく変わることを実感。実践では、最初は小口径でテスト、慣れてきたら用途に合わせて口径の幅を広げるのが安全で効率的だと結論づけました。こんな雑談は、道具と作業の理解を深める良い機会になります。口径の選択は経験と実験の積み重ね。失敗を恐れず、テストパッチを重ねて自分の作業スタイルを確立していきましょう。





















