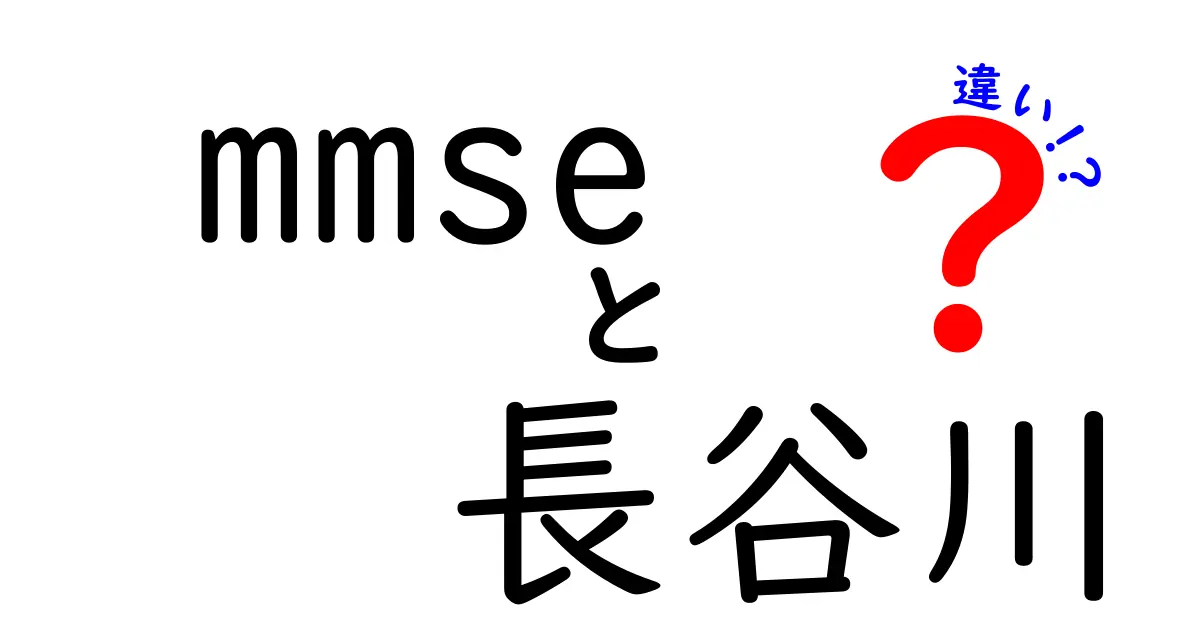

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに: MMSEと長谷川式検査の違いを知る理由
MMSEと長谷川式認知機能検査(以下HDS-Rと呼ぶことが多い)は、認知機能を評価する代表的な検査です。学校の成績のように点数だけを見てはいけません。どの分野を test しているのか、どういう人に強く影響されやすいのかを理解することが大事です。この章では前提となる基本を整理します。MMSEは英語圏で長く使われてきた30点満点の検査で、所要時間はおおむね5〜10分程度です。一方、長谷川式は日本で生まれた検査で、日本語の言い回しや日常生活の記憶・計算の要素が強調され、こちらも30点満点です。どちらも「認知機能の総合的な状態を把握するための道具」であり、診断を一発で決定するものではありません。適切な場面で使うことが重要です。
MMSEとは何か
MMSE(Mini-Mental State Examination)は、歴史的にも広く使われてきた認知機能検査の標準的な形式のひとつです。設問は大きく分けて6つの領域に分かれます。1つ目は時間・場所・人の認識を問う「方向性」。2つ目は記憶の「登録」と短期記憶の確認、3つ目は注意と計算(つぎの数字を引く、数を順番に数えるなど)、4つ目は短期的な記憶の「保持・呼び出し」、5つ目は言語機能(命名・理解・文章の復唱・会話の流暢さ)、6つ目は作業的な能力である「模写」や図形の描写を含みます。
この構成の特徴は、日常的な語学理解や抽象的思考の要素を含み、教育歴や語学レベルの差を受けやすい点です。つまり、教育歴が高い人は点数が高く出やすい一方、低い人は点数が低めに出ることがあります。したがって臨床現場では、検査の結果だけでなく、受検者の背景情報を合わせて解釈することが重要です。
またMMSEは英語圏で開発された基準であるため、日本語話者に適用する際には日本語版の配慮項目が設けられており、日常語彙の多さや表現の難易度が影響します。これにより、認知機能の変化を検出する敏感さは高く保たれますが、教育水準が大きく影響する点は忘れてはいけません。臨床現場では、検査の目的を明確にし、評価の一部として他の臨床情報と組み合わせて解釈します。
長谷川式認知機能検査(HDS-R)とは何か
長谷川式認知機能検査(HDS-R)は、日本で開発された認知機能検査の代表的なひとつです。30点満点で、主な構成は日常生活に関連する記憶・注意・計算・言語の要素を含んだ設問です。日本語の語彙と日常的な場面設定が多く、受検者の生活背景に馴染みやすい設計になっています。難易度はMMSEと比較するとやや低めに感じられることがあり、検査時間も短縮される傾向があります。教育歴の影響を受けにくい設計を意図している点が特徴で、地域の高齢者を対象にしたスクリーニングで使われることが多いです。HDS-Rは日常の記憶と実生活での判断力を見やすくする工夫があり、病院だけでなく地域の介護現場や訪問診療の場でも活用されます。こうした背景から、教育歴が異なる人々間での比較や、長期的な認知機能の変化を追いやすい点がメリットとして挙げられます。
違いを項目別に見る
以下の項目は、実務でよく比較されるポイントです。検査時間、対象者の背景の影響、日語・日常語の適合性、点数の解釈と臨床的意味、そして臨床での適用分野です。
1つずつ見ていくと、MMSEは総合的な認知機能を一枚の点数として示すため、総合評価には向いていますが、教育歴の差を補正する工夫が必要です。HDS-Rは日本語環境に最適化され、日常場面の記憶・認知タスクに重心が置かれるため、地域高齢者のスクリーニングには強い適性を持ちます。両者を併用することで、教育歴が高い人と低い人の差異を減らし、認知機能の変化をより正確に見抜くことが可能になるのです。
強調したいのは、どちらの検査も「単独で診断を決定づけるものではない」という点です。状況に応じて、補足的な検査や医師の総合判断と組み合わせて総合評価を行うべきです。
臨床での使い分けと実務のコツ
現場では、検査目的に応じて使い分けをします。教育歴が高い人にはMMSEの補正が有効な場合がある一方、地域の高齢者や日常生活の場面を重視する場面にはHDS-Rが適していることが多いです。また、検査を受ける人の言語能力や聴覚・視覚機能にも留意する必要があります。結果の解釈では、点数だけを見るのではなく、受検者の背景、回答の文脈、反応のスピード、エラーの型などを総合的に評価することが大切です。検査の前には、受検者に対して目的と所要時間を説明し、安心した状態で受検してもらうことが信頼性を高めるコツです。最後に、結果を家族や介護者と共有する際には、複数の視点からの解釈を丁寧に伝えることが重要です。これにより、認知機能の変化を早期に発見し、適切な支援や計画を立てやすくなります。
カフェで友人とMMSEと長谷川式の話をしていたとき、私は一つの例え話を使って深掘りしました。二つの検査は、同じ目的=認知機能を測るという点では共通しています。でも現場では、MMSEが“広く使われる標準尺”のように見える一方で、HDS-Rは日本語に馴染みやすく、日常生活の文脈を大事にする道具として重宝します。僕が思うのは、結局、検査は道具であり、人と文脈を読み解くための手がかり。だからこそ、検査の結果だけでなく、受検者の背景や回答の意味を一緒に見ることが大切だと感じました。もし誰かが「どちらを選ぶべきか」と迷ったら、教育歴や日常生活の場面を想定して、両方の良さを組み合わせるのが最適解になると思います。





















