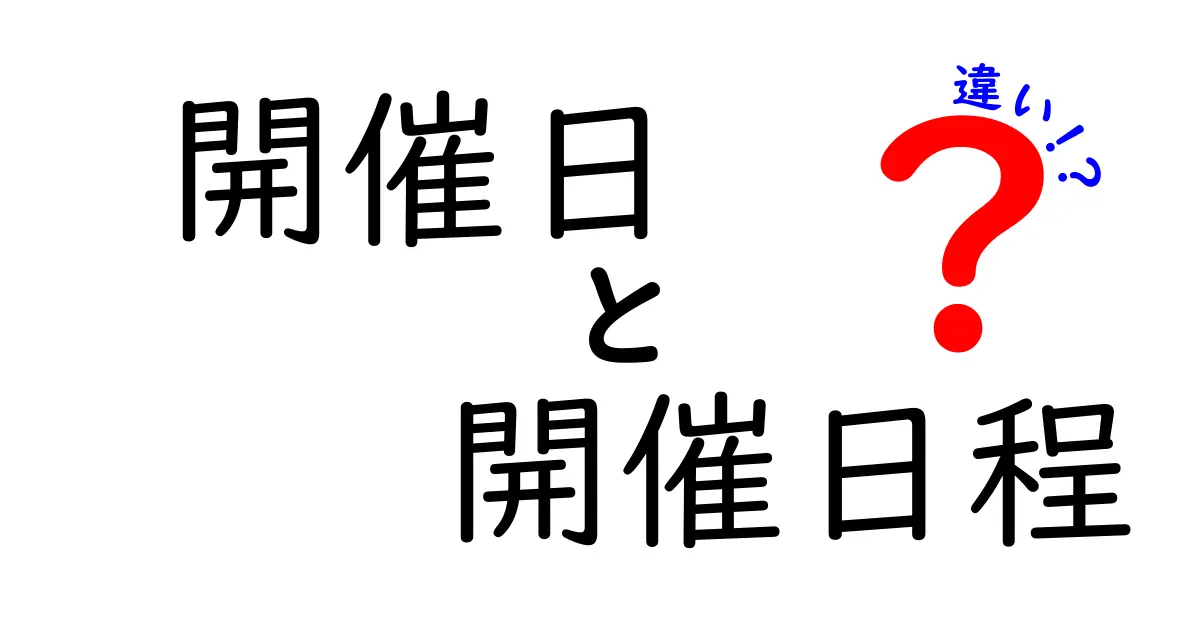

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
開催日と開催日程の違いを徹底解説:意味・使い方・混同を防ぐコツ
開催日と開催日程は、イベントの告知や計画を書くときに混同しやすい用語です。開催日はそのイベントが実際に行われる日付そのものを指します。開催日程は日付だけでなく、開始時刻、終了時刻、複数日間の日程、場所の割り当て、各日ごとのプログラムなどを含む予定全体を意味します。例えば学校の文化祭を例にとると、開催日は2025年10月15日です。一方、開催日程は2025年10月15日〜16日、9:00〜18:00、体育館と講義室でのプログラム構成というように、日付と時間・場所・内容をまとめたものになります。
この二つの語を正しく使い分けると、読者にとって情報が見やすくなります。特に公式発表やチラシ・ウェブ告知では、開催日と開催日程を分けて表示するのが一般的です。混乱を避けるコツとしては、まず「いつが実施日か」を明記してから、「どのくらいの期間・どの内容か」を続けて書くこと、または日程の表現を箇条書きで整理することなどがあります。正確さと分かりやすさを両立させるために、日付だけでなく開始時刻・終了時刻の記載、場所、参加方法、参加費の有無などの補足情報を添えると良いでしょう。
さらに、オンラインイベントではタイムゾーンの表記も忘れずに入れると、国内外の読者に対して配慮できる点です。
日程の例外や注意点として、日程が変更になる場合がある点を読者に周知することが大切です。日程が確定しているときは「確定」と明示し、変更時には通知の方法と新しい日付を迅速に伝えることが求められます。日程が未確定の場合には「日程は後日お知らせします」といった表現を使い、読者の混乱を避けましょう。
日常の会話でも、開催日と開催日程の使い分けを意識して話すだけで、話の伝わり方が格段に良くなります。
日常での使い分けのコツと注意点
日常の会話・告知文での使い分けのコツを紹介します。
1) まずは「いつ」。その後に「どのくらいの期間か」。
2) 期間が複数日か1日だけかで分ける。
3) 表現は短く明確に。
4) 予定が複雑なときは箇条書きで整理すると伝わりやすい。
このコツを実践すると、同僚や友人との予定調整の際に、相手の混乱を減らすことができ、約束の時間が守られやすくなります。
また、告知文を書くときには、見出しで「開催日」と「開催日程」を分け、本文でそれぞれの意味を再度確認するのがオススメです。正確な日付情報と詳細な日程情報を並べることで、読者は迷わず必要な情報を拾えます。さらに、オンラインとオフラインの混在イベントでは、タイムゾーンやアクセス方法の違いにも注意を払うとよいでしょう。
友達と日程の話をしていて、日程の決め方について深掘りしてみた。日程は単なる日付の並びではなく、誰が参加可能かを前提に調整する作業だと気づいた瞬間、場の雰囲気が変わる。人と人の都合を合わせるのは難しいが、候補日を3つ程度用意しておくと、誰かの予定が入っていても別の日を選びやすい。私はまず最優先の人の都合を聞き、次に全体の候補日を絞っていく方法を実践している。
前の記事: « 学会と学術会議の違いを完全解説!誰でも分かる使い分けのコツ





















