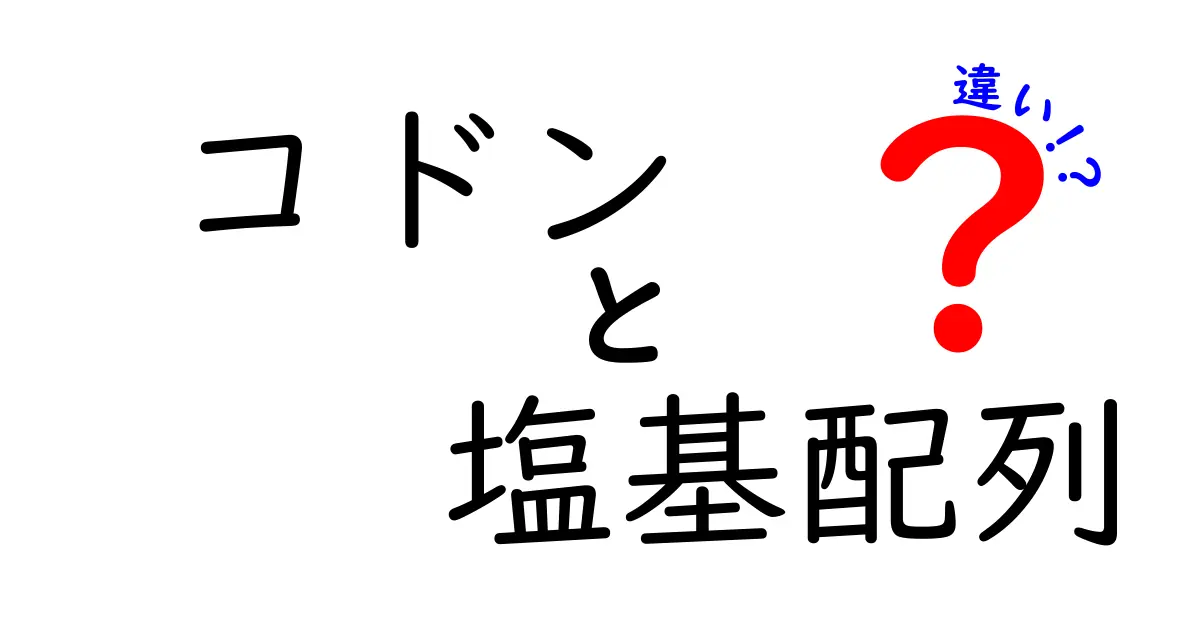

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
コドンと塩基配列の違いを徹底解説!クリックしたくなる図解つきガイド
コドンと塩基配列は、遺伝情報を読み解くときの“基本用語”です。難しく考えがちですが、実は私たちの体を作る仕組みを理解するためのとても大事なヒモです。ここでは、コドンが何を指すのか、塩基配列がどんな役割を持つのかを、日常の身近な例にも例えながら丁寧に説明します。まずは結論から言うと、コドンはRNAの“三文字コード”であり、塩基配列はDNAやRNAの“文字列全体”のことです。この二つは同じ情報を指すときにも別の視点を提供してくれます。
遺伝子の話をするとき、よく出てくる言葉に“読み枠”や“翻訳”があります。読み枠とは、どこから3文字を読み始めるかを決める目安のことで、これがずれると同じDNAの並びでも作られるアミノ酸が変わってしまいます。コドンは、リボソームと呼ばれる工場で実際にアミノ酸へと変換される基本的な設計単位です。塩基配列はその設計書の長さを決める総意であり、どのアミノ酸を作るかは、三文字ずつの並び方(コドン)によって決まります。
この違いを理解すると、なぜDNAの配列がわずか1つ変わるだけで体の機能が変わることがあるのか、またどうして同じコドンが複数のコドンと同じアミノ酸を作ることがあるのかがわかります。実際の学習では、DNAの塩基配列を読んでRNAへ転写し、RNAのコドンを翻訳してタンパク質が作られる一連の流れを見ていきます。以下の図と表を使うと、違いのイメージがつかみやすくなるでしょう。
コドンのしくみと塩基配列の関係
コドンは常にRNAの三文字で1つのアミノ酸を指示します。AUGはメチオニンを意味し、ここから翻訳が始まります。塩基配列全体の中で、コドンがどのように並ぶかで作られるタンパク質が決まるのです。面白い事実として、同じアミノ酸を作るコドンは複数存在することがあり、これを“退化コード”と呼びます。たとえば、GCU、GCC、GCA、GCGはいずれもアラニンを表します。この冗長性は、DNAのエラーに強くなるように進化した工夫の一つです。
実生活での例えを使えば、塩基配列は作業日誌のようなもの。毎日書く内容が違っても、コドンという“小さな単位”を組み合わせて大きな仕事(タンパク質作成)を完成させます。読み始める場所がずれれば作るべきタンパク質も変わってしまうので、細胞は厳密な制御をします。ここで覚えておくべきポイントは、コドンは3文字の単位、塩基配列は全体の文字列、翻訳はその文字列を具体的な分子に変換するプロセスということです。
ねえ、今日はコドンのおしゃべりを一問一答風に雑談してみよう。コドンは3文字で1つのアミノ酸を指示する“三文字コード”です。DNAをコピーして作られるRNAの読み枠の中で、AUGから読み始めると必ずメチオニンを作る最初のコドンになります。ところが、同じアミノ酸を作るコドンは複数あるため、実は同じ目的地に行く道がいくつも存在します。これを退化コードと言います。もし読み始めの場所を横から少しずらしたら、違う物質ができてしまうので、細胞は正確さを保つために厳密な制御をしているのです。こうした雑談的な見方をすると、難しい用語も身近な話として理解しやすくなります。





















