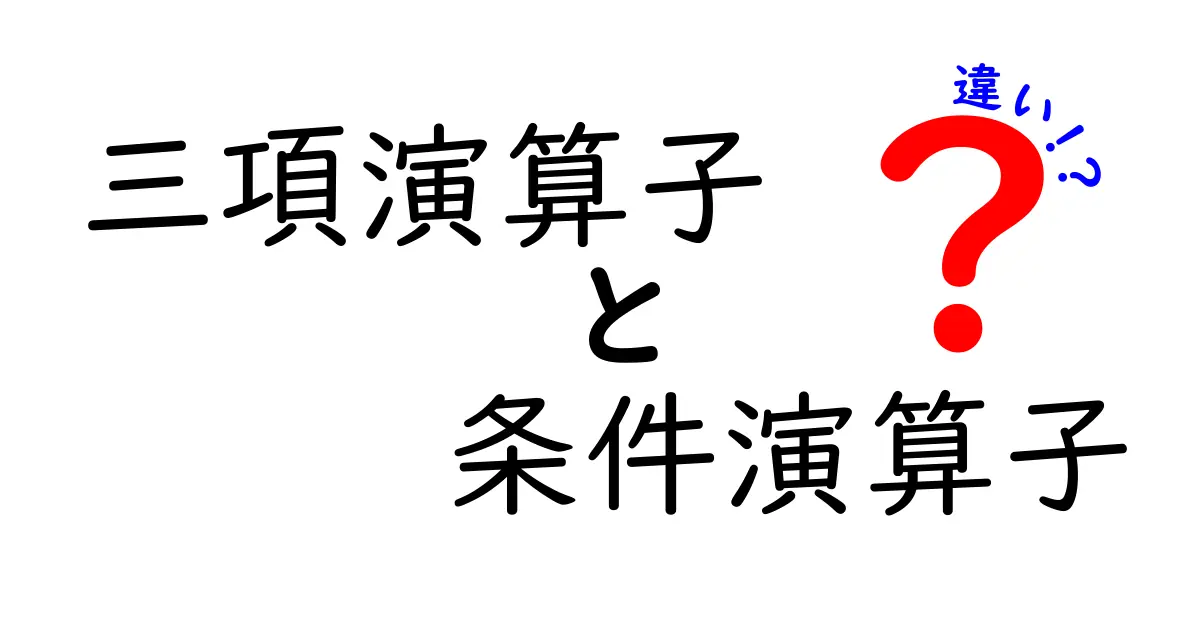

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
三項演算子と条件演算子の基本を理解する
三項演算子と条件演算子は、日常の日本語で言うと「ある条件が成り立つ場合とそうでない場合のどちらかを選ぶ仕組み」です。プログラミング言語ではこの仕組みを一つの表現として用意しています。三項演算子は名前の通り「三つの要素を持つ演算子」で、通常は「条件 ? 値A : 値B」という形で書き、条件が真のときは値A、偽のときは値Bを返します。このように、1文の中で条件判定と選択が一度に完結するのが特徴です。
一方の条件演算子は、機能の説明寄りの用語であり、どんな場面で使われるか、どんな値を返すのかといった“機能の意味”を強調します。
どちらも「条件に基づいて別の値を返す」という共通点がありますが、呼び方のニュアンスが異なるだけで、実際の動作は多くの言語で同じように動作することが多いです。
このとき重要なのは、使い分けの指針を持っておくことです。短くてシンプルな場合には三項演算子を用いてコードをすっきりさせるのがよい場合が多いですが、条件が複雑になったりネストが深くなると、読みやすさを優先して通常のif文を使うほうが良い結果を生みます。
実践的な使い方と表での比較
基本形は「条件 ? 真の場合の値 : 偽の場合の値」です。条件が真であれば左側の値、偽であれば右側の値が返ります。
この仕組みを理解しておくと、値を選ぶときの表現力がぐっと上がります。
ただし、入れ子になったり長い式になると、可読性が低下する危険があります。そういうときには、if文へ切り替える判断を持っておくと安全です。
以下は、具体的な比較表です。
最後に、例を二つ挙げます。
例1: 簡単な値の選択
let result = condition ? 'A' : 'B';
例2: ネストの注意点
let value = flag ? (type ? 'X' : 'Y') : 'Z';
今日は友達と雑談風に進めます。三項演算子と条件演算子の違いは、実は“形と機能”の違いだけ。話をしながら思ったのは、コードを書くときはまず“何を選ぶか”を決めること。そのうえで式を短くまとめると読みやすさが生まれる。例えば、天気が良い日には外に出るかどうかを判断する設問と同じ。条件がtrueなら外に出る、そうでなければ室内にとどまる。三項演算子はその選択を一行で表すための道具だ。深掘りすると、言語ごとに役割の解釈が少し違うことにも気づく。つまり、場面に応じて使い分けるのが大事。だから仲間と話す時も「この場合は三項演算子を使って短く書く方が伝わりやすいね」とか、「ここの条件は複雑なのでif文にした方が安全だよ」と雑談ベースで共有すると、学ぶスピードが上がるんだ。
前の記事: « モニターの発色の違いを徹底解説|色味が変わる理由と選び方のコツ





















