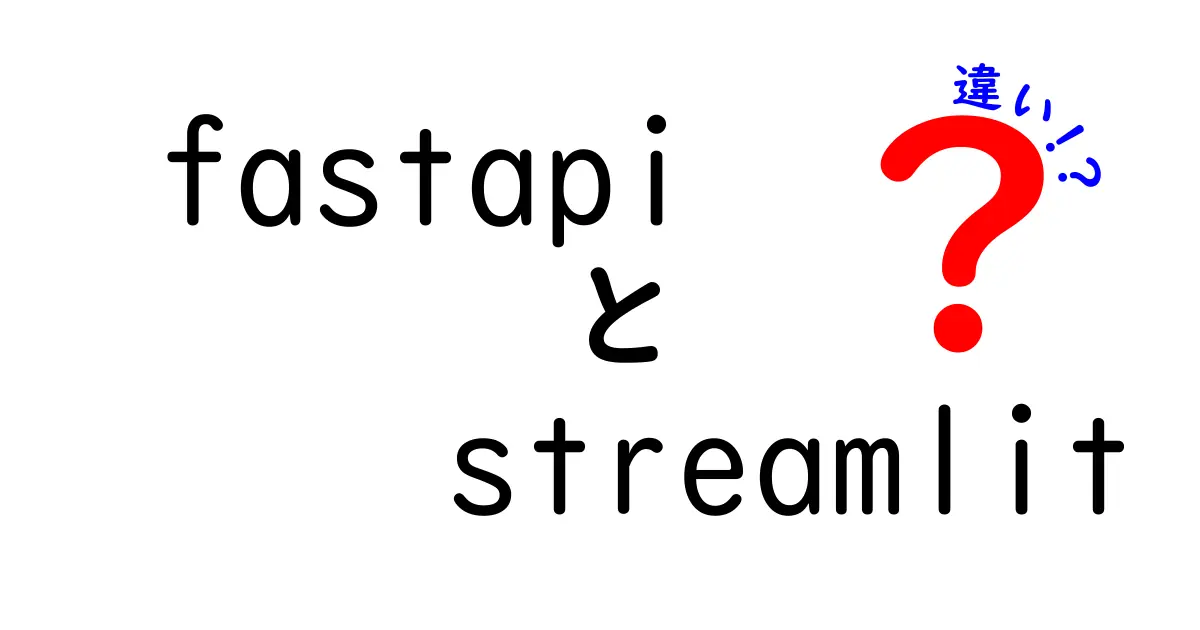

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
fastapiとstreamlitの違いを徹底解説する理由と全体像を長文で語る見出し: この記事は、Webアプリ開発の現場で二つの人気ツールがどう役割分担しているのかを初心者にも理解できるよう丁寧に整理したものです。fastapiはAPI設計とサーバーサイドの高速性を追求するフレームワークであり、型安全性と自動ドキュメント生成、非同期処理の強力さが特徴です。一方でstreamlitはデータ可視化やダッシュボード作成をとても簡単にするためのツールで、コードの量を大幅に減らしてUIをすばやく組み立てられる点が魅力です。
この両者は同じPythonエコシステムに属しますが、用途が異なるため使い方も考え方も変わります。初心者が混同しやすいポイントを整理して、どの場面でどちらを選ぶべきかを具体的なケースとともに解説します。
FastAPIは最新のPythonを活かした高性能なAPIサーバーを作るためのフレームワークです。HTTPリクエストのバリデーションをPydanticで自動化し、型情報を使って開発者が間違いを早期に見つけられるようにします。ASGIという非同期仕様を使うことで同時接続の処理能力を高め、デプロイ後の応答性を安定させます。さらにSwagger/OpenAPIの自動ドキュメント生成機能があり、APIの使い方をクライアント側が理解しやすくなります。一方のStreamlitは、データを表示するUIを最小限のコードで作れる点が魅力です。データ分析や機械学習の結果を直感的に可視化するダッシュボードを、Pythonのスクリプトだけで手早く作成でき、開発初期のプロトタイプ作成に強い武器になります。
ただし、Streamlitは「APIを自分で作る」ことよりも「データを見せるUIを作る」ことに焦点が当たっているため、認証や複雑なルーティング、長期運用の観点ではFastAPIほどの自由度や拡張性はありません。これを理解することが、正しいツール選択の第一歩です。
このように、どちらを選ぶかは“何を作りたいか”という目的と、“利用可能な時間とリソース”という制約に左右されます。
このセクションの補足として、実務での使い分けのポイントをいくつか挙げます。まずAPI中心のバックエンドを作るならFastAPIが適しています。次にデータの可視化や素早いプロトタイピングを重視するならStreamlitが向いています。両者を組み合わせるケースも多く、FastAPIでAPIを提供しStreamlitでそのAPIを利用してUIを作る構成は現場でよく見られます。デプロイの観点ではFastAPIは一般的なウェブサーバーとして動作しますが、Streamlitはアプリとして独立して動くため別のデプロイ手順が必要になる場合があります。
- 適したケースの例: API中心のバックエンド開発にはFastAPI
- データ可視化やダッシュボード作成にはStreamlit
- 両者を組み合わせて、FastAPIでAPIを提供しUIをStreamlitで作るパターンが一般的
結論としての使い分けは、作りたいものの性質と開発リソースのバランスを考えることです。APIの設計と運用の安定性を重視するならFastAPI、データの可視化やプロトタイピングの速度を優先するならStreamlitを選ぶのが妥当です。さらに将来的に拡張する可能性が高い場合は、両方を組み合わせた設計を前提に計画しておくと、後々の保守性が向上します。
このガイドを通じて、読者の皆さんが自分のプロジェクトに本当に必要なツールを見つけ、学習の順序を明確にし、効率的に開発を進められるようになることを目指します。
すぐに手を動かして試せる小さなサンプルから始め、段階的に機能を追加していくと理解が深まります。
最近の話題を雑談風にまとめると、FastAPIはAPIの骨格を作る設計図のような存在で、型とルーティングの組み合わせを理解すると自然と動くコードが見えてきます。対して Streamlit はデータの結果を美しく表示するUIを瞬時に作る道具で、分析結果を友達にも共有しやすい形に整える助っ人です。私自身はまず FastAPI でAPIの骨格を作り、そのAPIを Streamlit のUIから呼ぶ流れを練習しています。そうすると両方の強みを活かしたアプリが作れると気づきました。FastAPIは学習初期に型とデコレーターの感覚をつかむのがポイントで、Streamlitはウィジェットの配置と反応を試すことでUI作りの楽しさを実感できます。両者を組み合わせると、バックエンドとフロントエンドの連携が自然とスムーズになり、開発の効率がぐんと上がるのを実感します。





















