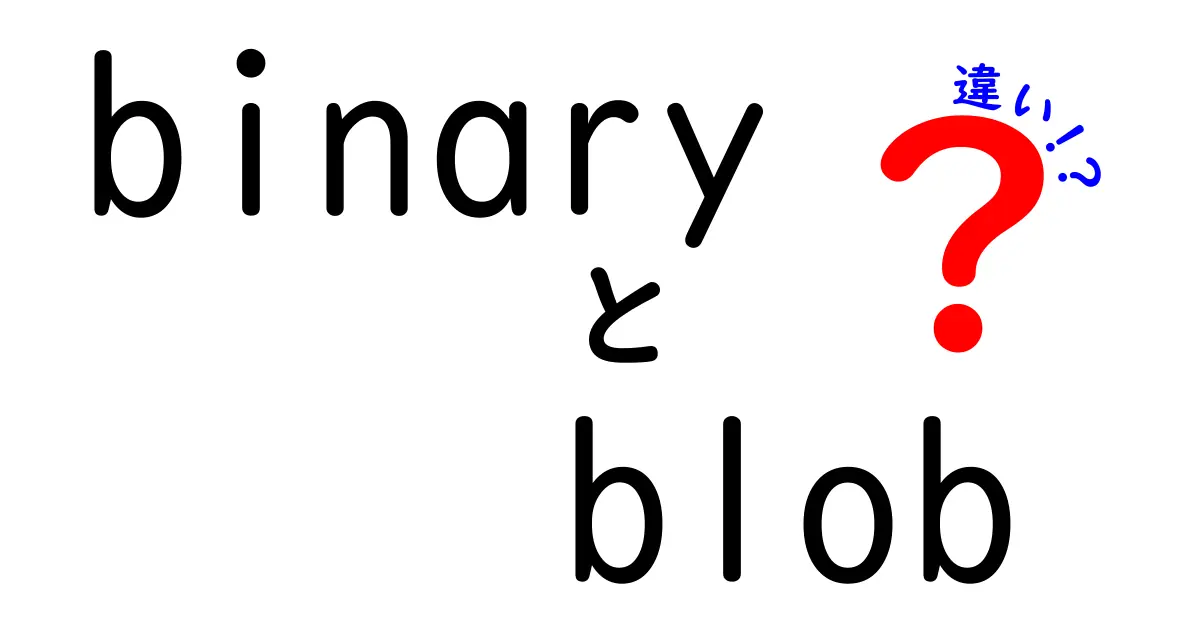

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
結論から知る「binary」と「blob」の違い
この二つの言葉は、日常のIT用語の中で混同されがちですが、現場での意味はっきりと区別されます。binaryは「2進数で表現されたデータ全般」という抽象的な概念を指す言葉で、ファイルの内容そのものやデータの伝達形式を説明する際に使われます。対してBlobはデータベースや特定のAPIが「Binary Large Object」という型名で提供する、巨大な2進データを格納するための専用のデータ型を指します。つまり、binaryはデータの種類を示す概念、Blobはそのデータをどう格納・扱うかを決める機能・型の名前、という違いが基本になります。
日常のプログラミングでは、binaryという言葉はファイルのフォーマットやデータのエンコード方法を表す際に登場します。例えば「このファイルは binary 形式で保存されている」などと言います。一方でデータベースの話になると、Blobという語が頻繁に出てきます。Blobは2進データをそのまま入れておく箱のような意味合いで使われ、サイズ制限や取り出し方はDBの仕様に従います。つまり、同じ“データ”を指していても、文脈が違えば「どんなデータか」という意味と「どう扱うか」という機能が変わるのです。
表現の違いを具体的に整理する
以下の表は、binaryとBlobの基本的な違いを視覚的に整理するためのものです。
実務では、こうした差を意識して設計書を作成したり、コードのコメントを分けたりします。
表を見れば、どちらがデータの性質を表す語なのか、どちらが格納や取り扱いの仕組みを指す語なのかが一目で分かります。
1. 基本の定義と使い分けの感覚を養う
まず抑えておきたいのは、binaryは「データの性質」を表す抽象的な語であり、Blobは「格納先・格納方法を決めるデータ型名」という具体的な機能を指す点です。
この2語を混同すると、コードでの型名やコメントで混乱が生まれ、後から見たときに「このデータはどう扱うべきか」がわかりづらくなります。
中学生の頃に言葉の意味を分けて覚えるコツとしては、binaryを“データそのものの性質”と捉え、Blobを“保存や取り扱いの箱”と考えると理解しやすいです。
この感覚を養うには、日常の身の回りのデータを例にすると良いです。例えばスマホで撮影した写真は“binaryデータ”として存在し、それをクラウドのデータベースに保存する場合にはBlob型の格納仕様が適用されます。こうした具体例をイメージすることで、言葉の意味のズレを防ぐことができます。
2. 実務での使い分けを理解する
実務では、binaryとBlobをうまく使い分けることが重要です。
例えば、通信プロトコルの説明ではbinaryがデータの性質を示す語として使われ、DBの定義ではBlobが格納対象を示す語として使われます。
この区別を意識しないと、コードのコメントや設計書が混乱を招く原因になります。
この違いを学ぶには、身近な例で考えると理解が進みます。
例えば、スマホで撮った写真をクラウドに送るとき、写真データはbinaryデータとして送られます。クラウド側のデータベースにはBlobのような型で保存されることが多く、アプリはそのデータを取り出して表示します。このとき「データそのものの性質」と「格納の仕方」が別物として扱われている点がポイントです。
また、プログラムでファイルを扱うときには、binaryと表現されるデータを読み込み、BlobとしてDBに登録する処理を別々に設計します。これにより、データの転送量の管理、エンコードの注意点、アクセス権の設定など、実務的な問題を個別に解決できます。
この設計の分離は、パフォーマンスとセキュリティの両方を高める基本テクニックです。
まとめとしてのポイント
本文の要点をもう一度整理します。
・binaryはデータの性質を表す概念、Blobはデータを格納・取り扱うための型の名前。
・実務ではこの区別を明確にすることで、設計・実装・保守のミスを減らせる。
・表のような視覚的整理と、日常の具体例をセットで学ぶと理解が深まる。
・MySQLのLONGBLOBやPostgreSQLのbyteaなど、DBごとのBlob型の仕様にも注意が必要。
この3つのポイントを押さえれば、binaryとBlobの違いを日常の開発で正しく使い分けられるようになります。
ねえ、さっきの話だけど、Blobが“データを格納する箱”みたいなものだと理解するといいよ。写真や動画のような大きなデータをDBに入れる時、その“箱”としてBlob型を使う。いっぽうでbinaryはその箱に入る中身、つまりデータ自体の性質を表す言葉。コードを書くときには、変数名を binaryData、データ格納の型を Blob にすると、意味が分かりやすくなる。こうして言葉の役割を分けておくと、後で見直すときに理解がぐっと楽になるんだ。





















