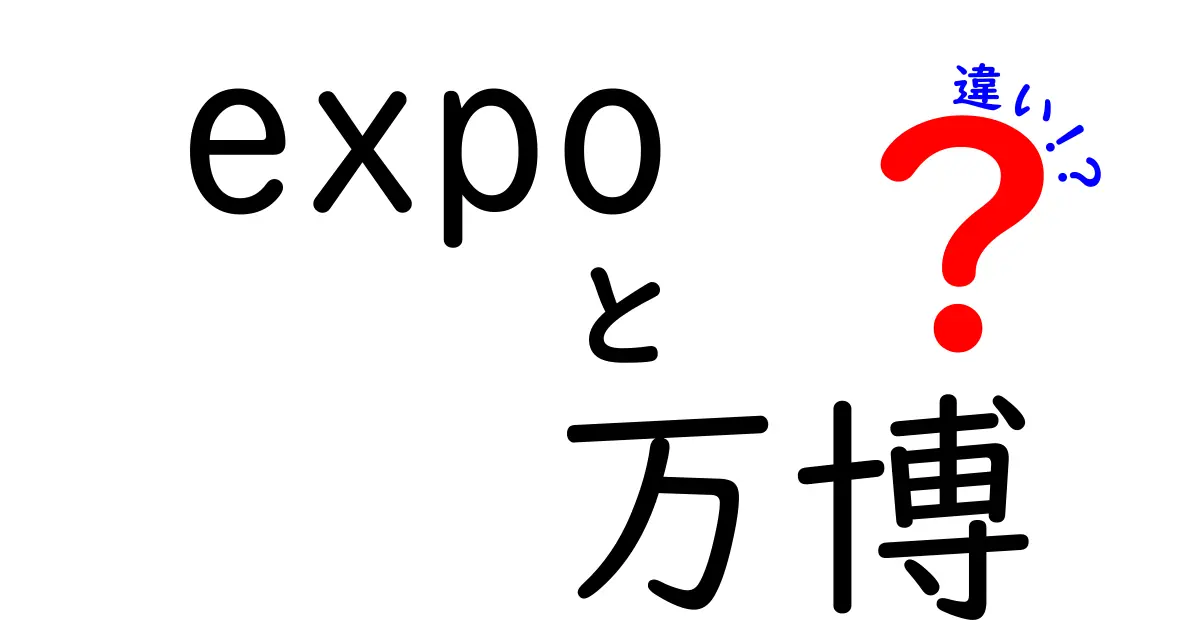

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
expoと万博の違いを理解する基本ポイント
まず最初に知っておきたいのは、expoと万博は指す対象が似ているが呼び方が違うという点です。expo は英語圏を中心に使われる略語で、exposition という長い語の頭文字を取ったものです。世界中で開かれる国際的な展示会や技術・文化の発表イベントを指す名称として、多くの公式資料・ニュース・学術討論で登場します。対して万博は日本語の通称で、1980年代以前から教育現場でも普通に使われ、日本のメディアでも広く認知されています。身近な例として、国際的な博覧会が日本で話題になるときには「万博が行われる」「万博に行った」といった言い回しが自然で、英語表記の公式名称と混同することは少なくありません。つまり、意味はほぼ同じでも、使われ方が言語と場面によって変わるという点が大きな違いです。
この違いを理解するには、学習や日常的な会話の場面を思い浮かべると分かりやすいです。ニュース記事や公式サイトでは Expo 2025 Osaka など英語表記が用いられることが多く、ブランド性や国際性を強調します。一方、授業の資料や日本のテレビ番組では 万博 という表現が中心となり、歴史性・教育的価値を前面に出す傾向があります。英語の名前を知っておくと国際的な情報を正しく理解しやすく、日本語の名前を使えば身近さと理解の容易さが増します。これらの使い分けは、情報源の出どころを判断する手がかりにもなります。
使い分けと実例・覚えておくべきポイント
使い分けのコツは、話す相手と場面を想像することです。日常会話では万博と呼ぶのが自然ですが、英語圏の文献や公式情報をそのまま引用する場面では expo の方が適しています。ニュースサイトや公式サイトの見出しには Expo や EXPO という語が使われ、イベント名が固有名詞として扱われる点が重要です。教育現場では、万博の歴史的背景や社会的影響を説明する際に、この語のブランディングと意味を分けて説明すると理解が深まります。
さらに、名称の実例で整理しておくと混乱を避けやすいです。以下の表を見れば、 expo と万博 の使い分けのヒントがつかめます。表は見出しの下に配置して、文字だけでなく視覚的にも理解を助ける役割を果たします。
結局のところ、ex poと万博は言語の違いと文脈の違いだけであり、意味は同じ大規模な国際展示イベントを指しています。日本語と英語の両方の表現を知っておくと、世界のニュースや資料を正しく読み解く力がつき、海外の人とコミュニケーションをとる際にも便利です。
友人と雑談していて、万博という言葉の奥にあるちょっとしたズレに気づいた話をしたい。expoと万博は同じ意味の異なる呼び方のように思えるけれど、日本語では万博が一般名として長い歴史を持ち、英語では Expo という国際的表記になる。この二つの語を使い分ける場面は、海外のニュースを読むときや海外のイベント名をそのまま紹介するとき、そして日本の教育文脈で説明するときなど、文脈によって変わる。私は友達に、"万博"は日本の学校の歴史の教科書で学ぶ伝統的な語感、"expo"は国際ニュースや公式サイトで見かける最新のブランド扱いだと話してみた。すると友達も頷き、話は自然と大阪万博の話題へと進んだ。結局、二つの語は互いを補完する関係で、混同せず使い分けることが大人になる第一歩だと気づいた。





















