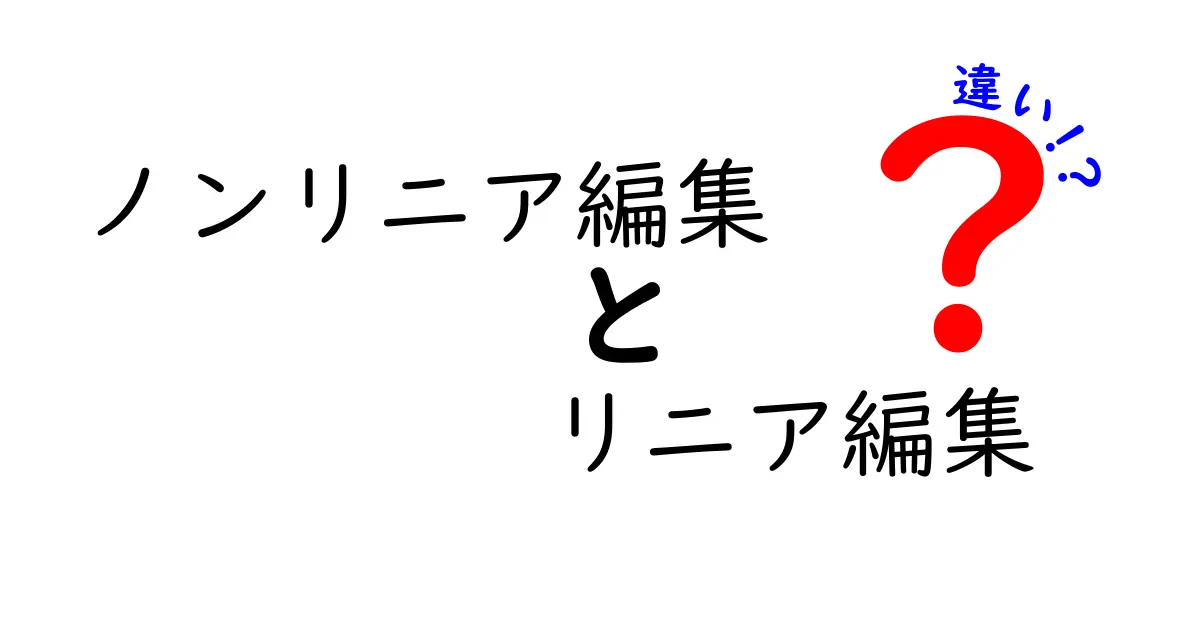

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ノンリニア編集とリニア編集の基本を知る
現代の映像制作ではよく耳にする言葉が二つあります。ノンリニア編集とリニア編集です。これらは同じ“編集”を指す言葉のはずなのに、作業の流れや考え方、使われる機材が大きく異なります。まずは用語の意味をしっかり整理しましょう。
ノンリニア編集とは、素材を並べ替えたり修正したりする際に、元の映像を壊さずに別ファイルとして扱える編集方法のことです。非破壊編集とも呼ばれ、編集の過程で何度でもやり直せる自由度が特徴です。これにより、最初の構想と完成形が違っていても、順序を入れ替えたり、不要な場面を削除したり、エフェクトを追加したりといった作業を何度でも繰り返すことができます。
一方、リニア編集は、素材を物理的に連続した順序で処理していく従来の手法です。撮影した素材を順番に並べ、最終的な映像を一本の流れとして完成させるイメージです。デジタル化が進んでもこの考え方は残りますが、後からの変更は難しく、初期の計画と素材選びがとても重要になります。
この二つは“編集の哲学”の違いとも言え、どちらを選ぶかは作品の性質によって決まります。
ノンリニア編集の魅力は自由度の高さと複数人での同時作業、バージョン管理のしやすさにあります。長尺作品や複雑な展開、複数カメラの素材を扱う場合には特に有利です。編集ソフトはPremiere Pro、Final Cut Pro、DaVinci Resolve など多様で、どれも非破壊編集を前提に設計されています。ここでは、作業の流れを崩さずに前向きに進められる点が現代の映像制作で大きな強みになる理由を詳しく見ていきます。
また、ノンリニア編集はプレビュー作業やカラーグレーディング、音声微調整などの後工程を同じソフトウェア内で完結させやすい点も利点です。初学者にも扱いやすいツールが多く、学習曲線を緩やかにしてくれる点も魅力の一つです。
実務での違いと選択のポイント
現場の判断として、プロジェクトの要件・チーム体制・納期・予算・設備条件などが編集手法を決める大きな要因になります。ノンリニア編集は、複数の素材やアングル、そして複数人の編集者が関与する大型案件で真価を発揮します。素材ごとに保存・管理を行い、誰がどの段階で何を変更したかを追跡できるため、クライアントの変更依頼にも迅速に対応できます。高解像度素材や長尺作品では、非破壊編集と柔軟なタイムラインが作業効率を大きく向上させます。
さらに、バックアップ機能とバージョン管理の重要性は、納品後の修正や差し替えにも強い味方となります。
一方、リニア編集は、放送現場の即時性を重視する場面や短時間での編集、現場の確認用など、特定の条件下で有利です。長尺素材を一連の流れとして処理することで、頭の中で完成像を組み立てやすく、ミスを減らす設計思想があります。ただし現代のデジタル環境では、主流はノンリニア編集へ移行しており、リニア編集は教育現場や予算が限られた小規模プロジェクトで生きることが多いです。
以下の表は、実務でよくあるケースを簡潔に比較したものです。表を見れば、いま自分たちの現場で何を最優先すべきかが分かります。
実務で使われるソフトの選択肢として、ノンリニア編集ソフトにはPremiere Pro、Final Cut Pro、DaVinci Resolveなどがあり、OSやチームの習熟度に合わせて選ぶのが基本です。これらは非破壊編集を前提に設計されており、多くの現場で標準的なツールとなっています。
一方、リニア編集は現在の主流ではありませんが、放送現場の特定のニーズや教育用途でstill活躍する場面があります。編集の世界は日々進化しており、基礎を押さえた上で柔軟に組み合わせることが、良い作品を作る近道です。
友達のミカンと私は、ノンリニア編集とリニア編集の話題で盛り上がりました。ノンリニア編集は素材を自由な順番で並べ替えられるのが魅力で、途中で戻したり別のアングルを重ねたりするのが普通だと知って驚きました。リニア編集は直線的に進む古い方法ですが、現場の即時性が必要なときにはまだ役立つ場面があるそうです。結局、正解は一つではなく、作品の性質に合わせて選ぶこと。私たちは編集の自由度と現場の要件を天秤にかけ、最適な方法を組み合わせることが大事だと話し合いました。これから映像を学ぶ仲間にも伝えたい、そんな気づきです。
前の記事: « よもぎ蒸しと半身浴の違いを徹底解説!自分に合う入り方を選ぶコツ





















