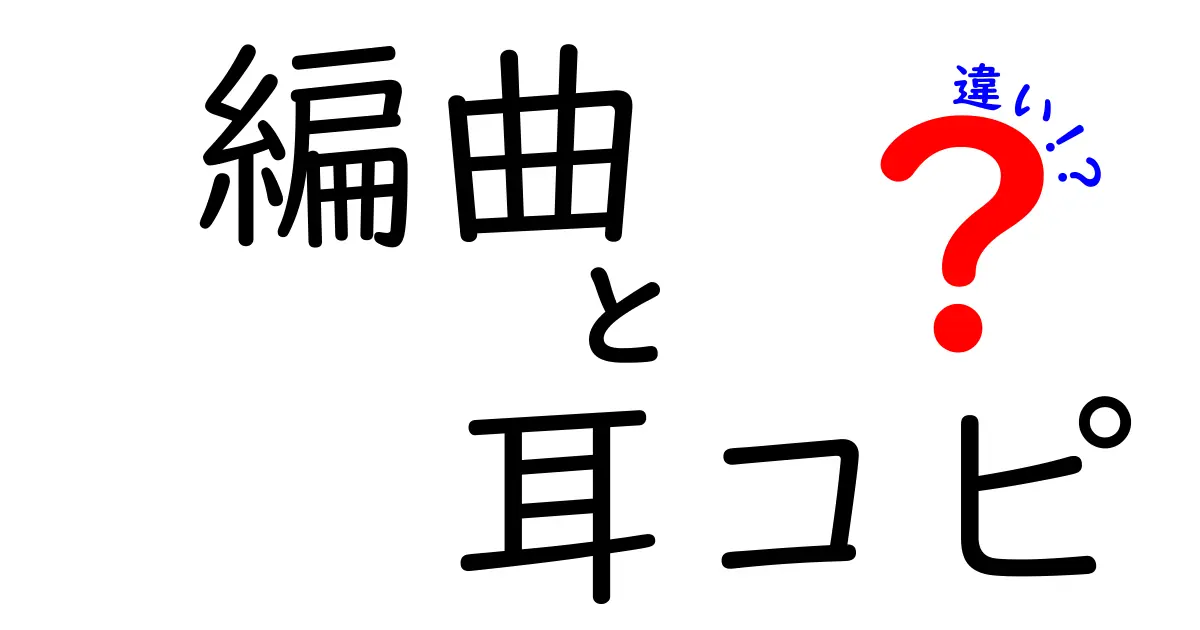

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:編曲と耳コピの違いを知ろう
音楽にはさまざまな作業があります。特に編曲と耳コピは似ているようで、目的や作業の仕方が大きく異なります。結論を先に言うと、編曲は楽曲を新しい形へと再構築する創作の工程であり、耳コピは音源を聴き取り正確な音符を写し取る再現作業です。どちらも学ぶ価値が高いのですが、狙いが違うため、取り組む順序や使い方が変わってきます。
この違いを理解すると、曲をどう扱うべきかが見えてきます。例えば、学校の音楽部で原曲をそのまま再現したいときは耳コピが役立ちます。一方で、映画のサウンドトラック風にアレンジしたい場合は編曲スキルが必要になります。
以降では、まずそれぞれの意味を整理し、現場での実践的な流れや注意点、そして使い分けのコツを詳しく解説します。なお著作権には十分気をつけ、学習と趣味の範囲で楽しみながら理解を深めていきましょう。
編曲とは何か?作業の流れと具体例
編曲とは、元の曲の素材を活かしつつ新しい形へと組み立て直す創作活動です。具体的にはメロディの扱い、ハーモニー(和音)の変更、楽器編成の変更、リズムやテンポの調整、曲構成の再配置などを行います。例えばポップスの原曲をギターとピアノ中心のアレンジに変え、ストリングスを追加して壮大な雰囲気にする、あるいは同じメロディを別のリズムで演奏できるように編成を組み替える、などが典型です。
編曲の作業フローは、まず曲の「核」を理解することから始まります。メロディがどれだけ強いか、どの部分に感情のピークがあるか、現在のコード進行はどう機能しているかを読み解きます。次に、目的に合う音色や楽器編成を決め、和音進行を調整したりリズムセクションを置き換えたりします。最終的には、演奏する人や聴衆のイメージに合わせてテンポやダイナミクスを整え、曲の個性を新しい形で表現します。
ここで重要なのは創造と再現のバランスです。原曲の雰囲気を残しつつ、アレンジならではの新鮮さを足すことが求められます。学校の合唱や吹奏楽部のための編曲練習では、楽譜の読みやすさと演奏のしやすさの両立を意識することが大切です。
耳コピとは何か?実践のポイントと注意点
耳コピは音源を聴いて音符を再現する技術です。ここで大切なのは、聴く力を段階的に鍛えることと、正確さと再現性の両立を意識することです。実践の流れとしては、まず全体のリズム感とメロディの大枠をつかみます。次に細部の長さ(音の長さ)と高さ(音階)を正確に書き起こします。テンポが速い場合は、最初は拍子感を崩さず、後から細かいニュアンスを足していくと安定します。
耳コピの難しさの一つは「音の微妙なニュアンス」、例えばレガートの長さや強拍のニュアンス、アタックの鋭さなどです。これらは機械的に再現するよりも、何度も聴き直して聴覚でフィット感を確かめる作業が欠かせません。
実践のコツとしては、最初は簡単なフレーズから始める、拍子を守りつつメロディを書き起こす、リファレンスとして原曲の別バージョンを比較する、そして録音データの速度を変えて聴くなどが有効です。もちろん著作権を尊重し、私的利用の範囲で練習を進めることが前提です。
実際の作業で使い分けるコツ
日常の学習や制作現場では、編曲と耳コピをどう使い分けるかが上達のカギになります。まずは耳コピで曲の核となるメロディと基本のコード感を掴み、曲の要素を「どういう形に変えるとどう響くか」を考えるのが良い順序です。例を挙げると、原曲のメロディを崩さずに和声を変えるだけで曲の印象は大きく変わります。次に編曲として実際の楽器編成を決め、アレンジの全体像を描きます。ここで大切なのは聴こえ方の想像力と演奏者の技量を合わせることです。演奏の難易度が高い箇所は、音域を下げたりリズムを単純化したりして現実的な演奏に落とし込みます。
また、表現意図を明確にするためにセクションごとに雰囲気を変えるのも有効です。例えばイントロは静かに始め、サビで盛り上げるといった「起承転結」を意識すると、聴衆に伝わりやすい作品になります。
表現の幅を広げたいときは、耳コピで得た正確さをベースに、編曲で新しい音色やリズムを追加すると、両方の技術が相乗効果を生みます。今後の練習では、短いフレーズを何度も反復して完全再現を目指すことと、機材やソフトの機能を使いこなすことを並行して進めると良いでしょう。
まとめとポイント
この記事の要点をまとめます。まず、編曲は創作的な再構築、耳コピは正確な再現という違いを理解することが第一歩です。次に、実践では耳コピで原曲の核を掴み、編曲で新しい表現を作るという順序を意識しましょう。現場では目的に合わせてテンポや音色を調整し、演奏者の難易度にも配慮します。最後に、権利や倫理にも留意しつつ、学習と創作の両方を楽しむことが大切です。音楽は技術と感性の両方を磨く旅です。これからの練習で、耳コピと編曲の両方をバランスよく身につけていきましょう。
友達と音楽部の話をしていたときのこと。私が耳コピの練習を進めると言うと、友達はすぐに『それって元の曲をそのまま再現するってこと?』と聞いてきました。私はうなずきつつも、耳コピと編曲の違いを丁寧に説明しました。耳コピは細部まで正確に写す作業で、テンポが速い曲では何度も聴き直す忍耐力が要ります。一方で編曲は、同じメロディを別の楽器で響かせたり、和声を変えて違う感情を引き出したりする創作の過程です。私は耳コピで基礎を固めた後、編曲に挑戦するつもりです。そうすると、原曲の良さを保ちつつ自分らしい表現が加わり、音楽を見る目がぐっと広がると感じています。これからも練習を続けて、いつか友達と一緒に新しい編曲を発表できたらいいなと夢を膨らませています。
次の記事: コード 音階 違いを徹底解説!中学生にも分かる丁寧ガイド »





















