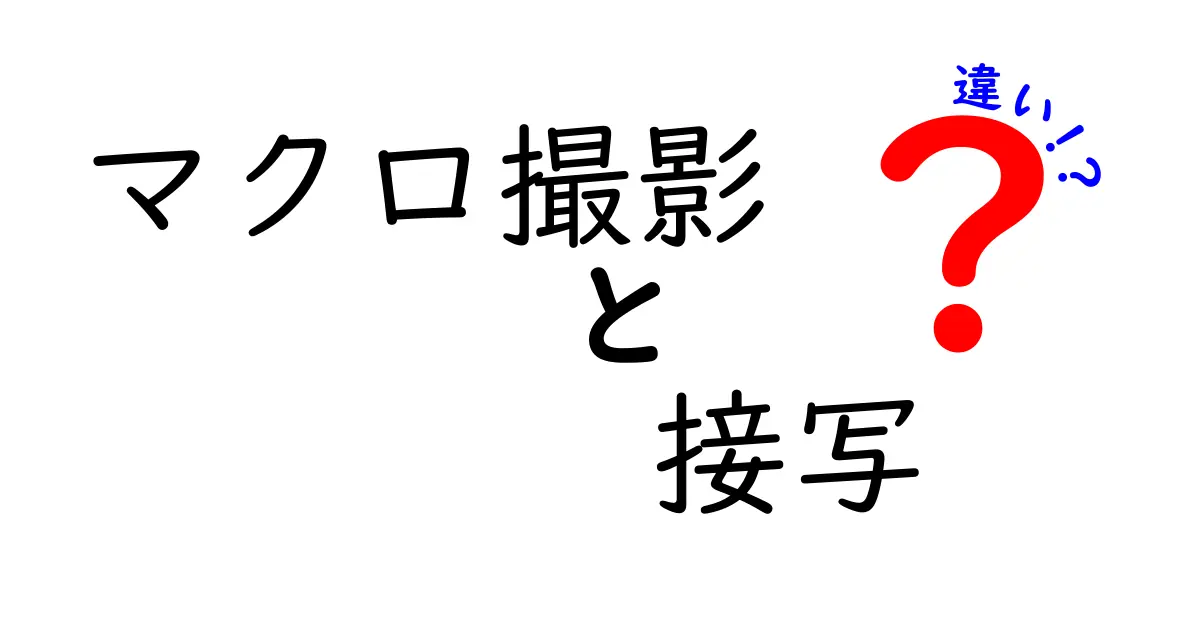

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
マクロ撮影と接写の違いを理解するための基本
まず最初のポイントは用語の捉え方です。通常、写真の世界でマクロ撮影とは、被写体を1:1以上の倍率で写し出すことを指しますが、現場では実務上1:1だけでなく1:2や1:1.5程度の近接撮影も含めて語られることが多いです。ここで重要なのは倍率と被写界深度、そして撮影距離の3つの要素です。倍率が高くなるほど小さな生物や細かな表面が画面に大きく映りますが、同時に被写界深度が薄くなるためフォーカスの一点を長く追い続ける技術が求められます。接写は“近くを撮ること”全般を意味する言葉であり、被写体との距離感を詰めて撮る行為を指します。接写は必ずしも高倍率を意味するわけではなく、日常的な虫の接近や身近な物の細部を観察する遊び心のある撮影も含みます。現代のカメラとレンズの組み合わせでは、近接距離に入るだけでマクロ的な描写が可能になる場面も多く、境界線は機材と撮影意図で決まります。
つまり、マクロ撮影は撮影の技法の名前、接写は距離感を指す表現と理解すると混同を減らせます。次の要点を押さえれば、作品作りの計画が立てやすくなります。倍率、被写界深度、距離感という順序で整理すると、何を写したいのかが自然と見えてきます。
この考え方を持つと、花の細胞構造のような微細な模様から、日用品の表面の質感まで、被写体の魅力を的確に切り取る練習が楽になります。
マクロ撮影の特徴と機材選び
マクロ撮影の最大の特徴は高倍率時の被写界深度の薄さと、距離が画質に大きく影響する点です。小さな生き物や花粉、繊維のような細部を大きく写すと、背景が非常にぼけて美しいボケ味が生まれます。これを狙うには専用レンズが役立ちます。代表的な機材にはマクロレンズと呼ばれる専用の長い焦点距離と近距離でピントを合わせる設計のレンズがあります。
さらに拡張アイテムとして、延長筒(Extension Tube)やベルボーンズ(Bellows)、リバースレンズ(Reverse Lens)などの工夫を使い倍率を稼ぐ方法もあります。これらは一眼カメラに直接取り付けて、通常のレンズでは難しい近接撮影を可能にします。
ただし、高倍率ほど撮影距離が短くなる点と、光量が不足しやすい問題を克服する工夫が必要です。照明はできるだけ均一に、自然光だけでなく小型の LED ライトやリングライトを使い分けるとよいでしょう。三脚を使って安定させ、マニュアルフォーカスで微調整すると、ピントのズレを防ぎやすくなります。練習のコツは、被写体を静止させることと、背景を整理して主題を強調することです。
機材選びのポイントは、初心者の場合は標準クラスのマクロレンズか、多様な焦点距離を持つセットを選ぶと扱いやすい点です。コストを抑えつつ画質を確保するには、照明と安定性を強化することが、撮影の満足度を大きく高めます。
接写の実践的なシーンとポイント
接写はマクロ撮影ほどの倍率を狙わずとも、身の回りの小さな物事をクローズアップして楽しむ撮影です。身近な素材、例えば布の繊維、紙の質感、果物の表面のつぶつぶ、昆虫の脚の微細な毛など、日常の中の細部を発見する楽しさが魅力です。実践時には、焦点距離を短くしすぎると手ブレが起きやすくなるため、シャッタースピードを速く設定したり、照明を安定させたりする工夫が必要です。
カメラのオートフォーカスを使いながらも、近距離になると微妙に前後することがあるため、マニュアルフォーカスでの微調整を習慣化すると失敗が減ります。被写体が動く場合には背景を暗くして被写体を浮き立たせると、雰囲気がぐっと良くなります。また、被写体の表面を水滴で濡らす“レジン効果”のような演出も、作品を引き立てるテクニックとして覚えておくと良いでしょう。
接写は観察力を鍛えるのに最適で、写真だけでなく美術や科学の学習にも役立つ門口です。光源の使い方、ピントの合わせ方、被写体の選び方を少しずつ学んでいけば、自然と写真の表現力は高まります。
以上を繰り返し練習することで、両方の撮影スタイルが自然と使い分けられるようになります。
最初は1つのテーマを選んで、背景の整理と光を意識しながら段階的にステップアップしてください。
写真は観察力と表現力の両方を育てる遊びです。
コツは焦らず、失敗を記録して次の撮影に活かすことです。
koneta: 友達と話していて、マクロ撮影の話題になると私は花の中心にある小さな蜜の粒を見せる瞬間が好きだと伝える。近づき方一つで普段は見えない模様が現れ、倍率を上げるほど背景がぼけて主題が浮き上がる。この感覚を共有すると、説明が技術の話だけでなく観察力と好奇心の表現だと理解してもらえる。最初は失敗して当然だと笑い合い、光と角度を少しずつ変えていくうちに、写真が“発見の道具”になるのを実感できる。





















