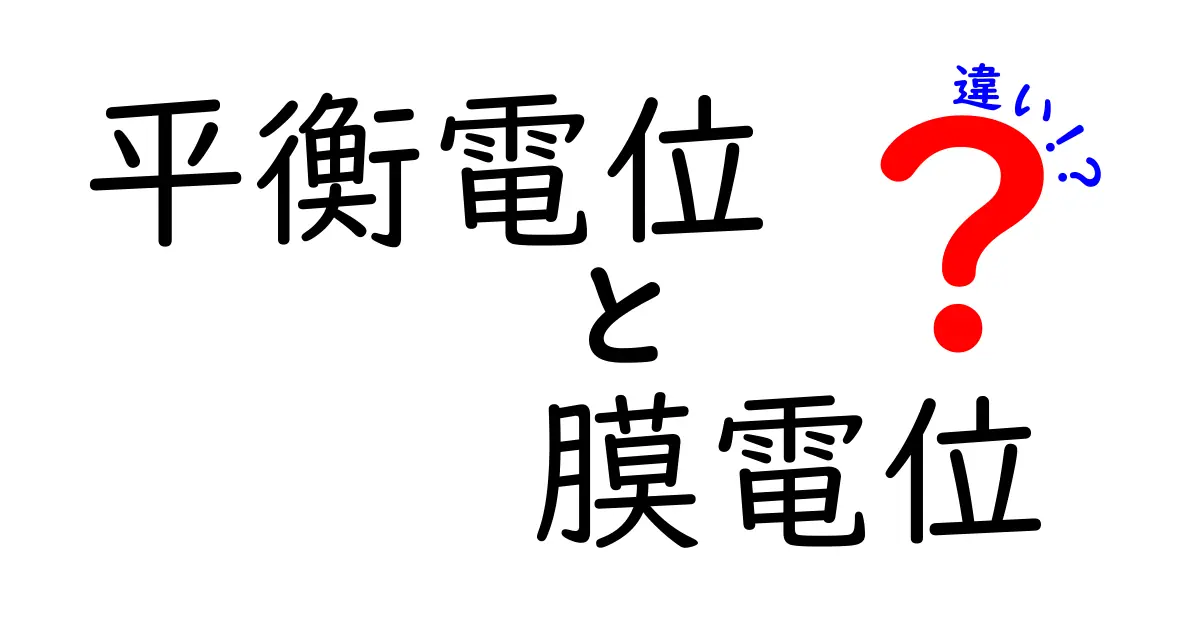

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
平衡電位とは何か?基本の考え方をやさしく解説
平衡電位は、ある特定のイオンだけが膜を自由に通れると仮定したとき、膜の内側と外側の濃度差と電荷の引力・斥力がちょうどつり合い、ネットの電流が0になる電位のことを指します。つまり外側と内側のイオン濃度勾配と電気的な力が等しくなる値です。
この考え方を支えるのがNernst方程式と呼ばれる式で、代表的には E_ion = (RT/zF) ln(外/内) という形で表されます。温度が違えば係数が変わるため数値も変動しますが、要点は「ある1種類のイオンだけが通れると仮定したときに得られる理論上の膜電位」という点です。
日常の例えで言うと、川の流れをただ1つの魚しか通さない網で表すようなものです。網を通れる魚(イオン)の種類が1つなら、網の端で生じる電位がその魚の平衡電位になります。
この平衡電位は単一イオンの濃度差をもとに決まる理論値であり、実際の膜電位をそのまま示すわけではありません。実験室の細胞でも、膜には多くのイオンが出入りしており、それぞれの透過性の影響を受けて結果としての膜電位が決まります。
つまり、平衡電位は“イオンごとの個別の目安”であり、膜電位は“複数のイオンの動きの総合結果”なのです。これを理解する鍵は、濃度差だけでなく「透過性」が大きく関わるという点です。
膜電位とは:実際の細胞で何が起きているのかを知ろう
膜電位は、膜の内側と外側の電位差を指します。これは1つのイオンだけで決まるものではなく、複数のイオンの透過性(どのイオンがどれだけ通りやすいか)の組み合わせで決まります。安静時には通常、カリウム(K+)の通り道が最も開いており、ナトリウム(Na+)や塩素(Cl-)の通り道は相対的に小さいため、膜電位は-70 mV前後となることが多いです。刺激を受けるとNa+の流れが増え、膜電位は一時的に正の方向へ動くことがあります。これは神経細胞が興奮する基本的な仕組みの核です。
この動きを理解するには、Goldman-Hodgkin-Katzの原理という考え方を使います。つまり膜電位は、P_K、P_Na、P_Clといった透過性の比率と、それぞれのイオンの内外濃度の組み合わせで決まるのです。透過性の変化が起きると、膜電位は新しいバランスへと移動します。
実際の数値としては、K+の平衡電位はおおむね-90 mV、Na+は約+60 mV、Cl-は約-70 mV程度とされますが、膜の透過性の比率がこれらの値の重みづけを決めるため、実際の膜電位はこれらの値の単純な平均ではなく、状況によって変わります。安静時にはK+が大きく影響し、興奮時にはNa+の影響が強まることで膜電位は大きく動くのです。
このしくみを表で整理すると理解が深まります。下の表は、代表的なイオンとそれぞれの平衡電位、および膜電位の出し方のイメージを示しています。
表を見ながら、膜電位がどう変化するかを考えると、数学的な公式がなくても現象の意味がつかみやすくなります。
まとめとして、平衡電位は“1つのイオンだけを考えた理論値”、膜電位は“複数のイオンの透過性と濃度の組み合わせによって決まる現実の値”という点を覚えておくと、次に学ぶときにも混乱しにくくなります。表や例を活用して、どのイオンがどの場面で影響を及ぼすのかを意識すると、神経科学の基本がぐっと理解しやすくなります。
友達と理科の話をしていて、膜電位と平衡電位の違いの話題が出ました。私は「平衡電位は1つのイオンだけが動くときの理論上の値で、膜電位は実際に細胞膜をいろいろなイオンが動く総合結果だよ」と説明しました。友達は「つまり、膜電位は複数のイオンの得失点の合計みたいなものか」と納得。話を深めるうちに、Na+が通りやすくなると膜電位が一気に正の方向へ動く、K+が dominantなときは逆に負の方向へ近づく、という現象のキャラクター性を実感しました。実験的な現場では、P_NaとP_Kの変化を敏感に捉えることが重要だと気づき、教科書上の数値だけではなく“動的な変化”を感じ取る大切さを再認識しました。
次の記事: 反応速度と酵素活性の違いを徹底解説!中学生にも伝わる科学の基本 »





















