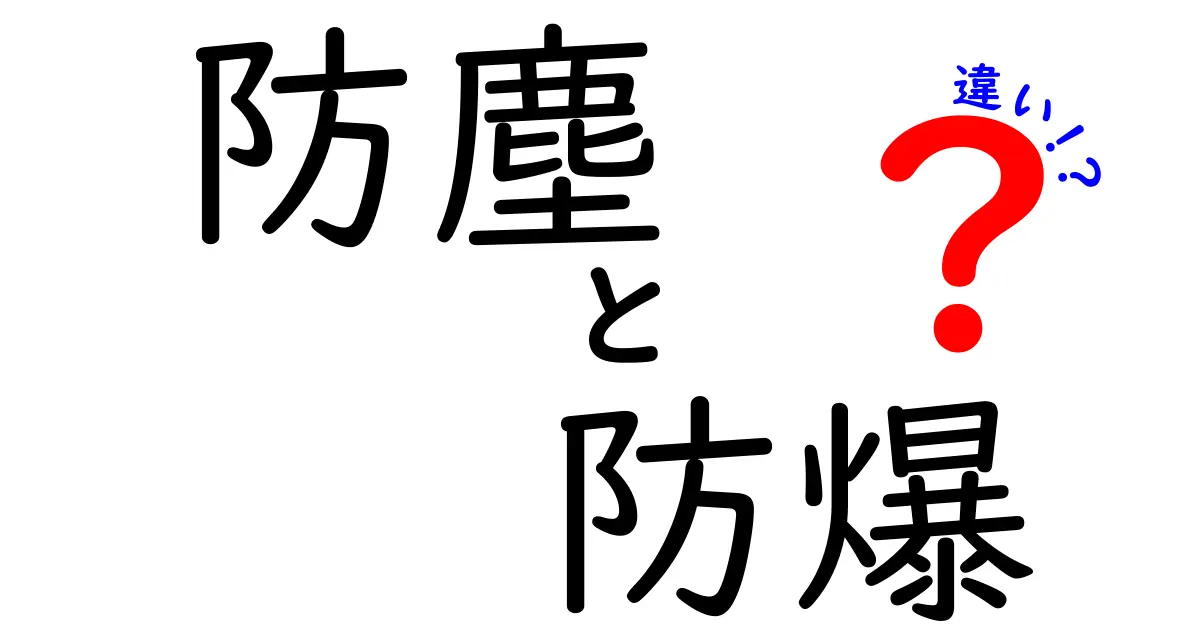

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
防塵と防爆の違いを徹底解説:現場を守る基本ルールと見極めのコツ
防塵と防爆は似た言葉に見えますが、現場の安全を考えると役割が大きく異なります。防塵は粉じんの侵入を防ぎ、機械の故障を減らすための対策です。粉じんは微粒子で空気中を漂い、機械の内部に入り込むと熱のこもりや不具合を引き起こします。防塵対策には外装の密閉性を高めることや埃がたまりにくい形状の設計、定期的な清掃や換気の確保が含まれます。現場では粉じんの発生源を把握し、作業手順を整え、清掃を徹底することが第一歩です。
粉じんは人体にも影響を与えることがあり、換気と呼吸保護具の着用が併用されます。
そこで重要なのは粉じんの種類と発生源の特徴を理解することです。
- 防塵の主な目的は機器内部の粉じん侵入を抑えること
- 適用範囲は家電から工場の機械設備まで幅広い
- 規格の目安として IP 系列の密閉性評価が使われることが多い
なぜ防塵と防爆は別物なのか
次の視点で見ると違いがはっきりします。防爆は爆発そのものを未然に防ぐための設計思想であり、爆発性混合物が存在する環境で機器が炎や爆風に耐えられるように作られます。可燃性ガスや粉じんが空気と混ざり炎が近づくと爆発が生じる可能性が高くなるため、外装を強化したり、爆発を外へ逃がす仕組みを組み込みます。国際規格では ATEX や IECEx などがあり、ゾーニングと機器の分類が重要です。
- 防爆は爆発のエネルギーを封じ込めず、伝播を抑える技術が中心
- 現場はゾーン区分と適用機器の選定が大きな決め手
- 爆発は二次災害を引き起こす可能性が高く、早期対策が求められる
日常の現場での適用例と注意点
私たちがよく見る場所でも防塵と防爆の考え方は実務に直結します。粉じんの多い工場や食品加工、化学品取り扱いの現場では、設備の外装を密閉にし清掃を日課にします。防爆が必要な場所では機器の分類と区画の設定を厳格に行い、可燃性ガスの存在を示す表示や停止ボタンの配置にも特別な配慾をします。実際の作業では、粉じんを作る工程を別の部屋に移す、換気を強化する、埃がたまりやすい隙間をコーキングで塞ぐ、定期的な点検を行うなどの具体的な対策が挙げられます。ここで大切なのは「現場の性質に合わせた適切な対策を選ぶこと」です。
同じ工場でも材料の性質が違えば必要な防塵防爆対策も変わります。
- 粉じんの性質を把握し作業手順を工夫する
- 定期的な清掃と点検を欠かさない
- 危険区域の表示と作業員の教育を徹底する
防塵と防爆の比較表と知っておくべきポイント
以下の表は basic な対比をまとめたものです。各項目を読んで自分の現場に適した対策を選ぶ参考にしてください。表だけでなく現場の実情に合わせた運用が大切です。ブレない判断基準を持つことで、予期せぬ事故を減らす助けになります。
防塵と防爆は目的が異なるため、同時に満たすべき条件を検討することが重要です。
友だちと学校の実験室の話を思い出してみよう。埃の多い作業台と静かな機械、どちらが安全かと問われたら、私なら間違いなく防塵の話を深掘りする。防塵は粉じんの侵入を防いで機械の寿命を延ばす役割がある。埃を完全になくすのは難しいけれど、適切な換気や密閉、清掃の習慣で機械の熱暴走を抑えられることを経験から知っている。もう一つのキーワード、防爆はもっと大きな視点だ。爆発が起きる場所では、機器の設計だけでなく周囲の区画分けや作業手順の見直しが必要になる。現場を守るのは私たち一人ひとりの意識と、正しい知識を持つことだと感じている。防塵と防爆、二つの視点を日常の安全意識に結びつけていきたい。





















